アルバート・バンデューラが提唱した「社会的学習理論(Social Learning Theory)」、後に発展させた「社会的認知理論(Social Cognitive Theory)」は、キャリアカウンセリングにおいて非常に重要な理論です。特に**「自己効力感(セルフ・エフィカシー)」**の概念は頻出ですので、必ず押さえておきましょう。
目次
1.最重要キーワード:「自己効力感(セルフ・エフィカシー)」
「自己効力感」は、バンデューラ理論の核となる概念です。
(1) 自己効力感とは?
「ある特定の状況や課題に対して、自分はそれをうまく遂行できる」という自信や期待感のこと。
【試験での注意点】
- 「自尊心(セルフ・エスティーム)」との違いを理解しておくことが重要です。
- 自己効力感: 「特定の課題(例:面接でうまく話す、PCスキルを習得する)ができる」という部分的な自信。
- 自尊心: 「自分には価値がある」という全般的な自己評価。
- 「結果予期」と「効力予期」の違いも問われることがあります。
- 結果予期: 「この行動をすれば、こういう結果になるだろう」という予測。(例:「一生懸命勉強すれば、試験に合格するだろう」)
- 効力予期: 「自分はその行動をうまくできるだろう」という予測。(例:「自分は最後まで集中して勉強をやり遂げることができるだろう」)
- キャリアカウンセリングでは、クライエントが「やればうまくいく」と分かっていても、「自分にできる自信がない(効力予期が低い)」ために行動できないケースが多く、この効力予期を高める支援が重要になります。
(2) 自己効力感を高める4つの情報源
ここが最も出題されやすいポイントです。4つの要因と、それを高めるための支援方法をセットで覚えましょう。
| 情報源 | 内容 | キャリア支援への応用例 |
|---|---|---|
| 1. 遂行行動の達成<br>(個人的達成・成功体験) | 自分自身が実際に何かを達成したり、成功したりする経験。<br>これが最も強力な情報源です。 | ・スモールステップの設定:大きな目標を小さな目標に分解し、成功体験を積ませる。<br>・過去の成功体験の棚卸しと再認識を促す。 |
| 2. 代理的経験<br>(モデリング) | 自分と似た他者が、課題を達成しているのを見聞きする経験。 | ・ロールモデル(目標となる人)の事例を紹介する。<br>・自分と似た境遇からキャリアチェンジに成功した人の話を聞く機会を作る。 |
| 3. 言語的説得 | 他者から「君ならできる」と励まされたり、能力を認められたりする言葉。 | ・カウンセラーがクライエントの強みや可能性を具体的に伝え、励ます。<br>・説得力のある人物(専門家や信頼できる人)からのフィードバックを得る。 |
| 4. 情動的喚起<br>(生理的・感情的状態) | 気持ちの高ぶりや不安、気分の状態。心身の状態をどう解釈するか。 | ・リラクセーション法を教え、面接などの際の過度な緊張や不安を和らげる。<br>・「緊張するのは、それだけ真剣な証拠」のように、ネガティブな感情の捉え方を変える(リフレーミング)。 |
2.観察学習(モデリング)
バンデューラは、人の行動は直接的な経験だけでなく、他者の行動を観察することによっても学習されると考えました。これを「観察学習(モデリング)」と呼びます。
観察学習の4つのプロセス
- 注意過程: モデルの行動に注意を向ける。
- 保持過程: 注意した行動を記憶する。
- 運動再生過程: 記憶した行動を実際にやってみる(再生する)。
- 動機づけ過程: その行動をやってみたいという意欲がわく。
【キャリア支援への応用】
- 職場でのOJT(On-the-Job Training)は、先輩社員の仕事ぶりを観察学習する典型例です。
- インターンシップで社員の働き方を間近で見ることも、キャリア選択における観察学習となります。
- 「代理的経験」は、この観察学習が自己効力感に影響を与えるプロセスを指しています。
3.相互決定的モデル(三者相互作用モデル)
人の行動は、個人の内的要因だけで決まるのではなく、「個人」「環境」「行動」の3つの要因が互いに影響し合っているとする考え方です。
- 個人 (P: Person)
- 認知、信念、価値観、感情、自己効力感など。
- 環境 (E: Environment)
- 物理的環境、社会的な人間関係、他者からのフィードバック、労働市場など。
- 行動 (B: Behavior)
- 実際の行動、選択、努力、発言など。
図: P ⇔ B ⇔ E (個人・行動・環境が双方向の矢印で結ばれているイメージ)
【キャリア支援への応用】 このモデルは、クライエントを多角的に理解する視点を与えてくれます。
- (例) 求職活動がうまくいかないクライエント
- 個人: 「自分は何をやってもだめだ」と自己効力感が低下している。
- 行動: その結果、応募書類の作成や面接対策への意欲がわかず、行動が停滞する。
- 環境: 不採用が続く(環境からのネガティブなフィードバック)。
- 悪循環: 不採用(環境)→ 自己効力感がさらに低下(個人)→ ますます行動しなくなる(行動)…という悪循環に陥る。
- カウンセラーの役割: この悪循環のどこかに介入し、好循環に変える支援を行います。例えば、スモールステップで成功体験を積ませて**自己効力感(個人)**を高めることで、行動を促し、環境からのポジティブな反応を引き出す、といったアプローチが考えられます。
試験対策のまとめ
- 最優先で覚えるのは「自己効力感」とその「4つの情報源」。それぞれの意味と具体例を説明できるようにしておく。
- 「自己効力感」と「自尊心」の違いを明確に区別する。
- 観察学習(モデリング)や相互決定的モデルも、自己効力感と関連付けながら理解しておくと、応用問題に対応しやすくなる。
- これらの理論が、カウンセラーとしてクライエントの**「行動変容」をどう支援するか**という視点に繋がっていることを意識する。


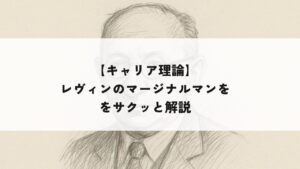
コメント