【設問1】 事例記録の中の「相談の概要」【略A】の記載に相当する、相談者がこの面談で相談したいことは何か。事例記録を手掛かりに記述せよ。
相談者は、定年退職後1年が経過し、一日の充実感がなく、再就職を考えているものの、介護への不安やワークライフバランスが不明確であるため、どうしたらいいのかよくわからなくなっており、この面談でそれらについて相談したいと考えている。
【設問2】 事例記録の【下線B】について、この事例を担当したキャリアコンサルタントがどのような意図で応答を行ったと考えるかを記述せよ。
キャリアコンサルタントは、相談者の「やっぱり少し働いた方がいいのかな」という気持ちを受け止めるとともに、両親のこともみながら働くことについて相談者がどのように考えているかを探ることで、不安や葛藤の言語化を促し、問題を明確にする意図があったと考える。
【設問3】 あなたが考える相談者の問題 (①) とその根拠 (②) について、相談者の言動を通じて、具体的に記述せよ。
① 問題 相談者は、現在の充実感のなさの解消策として漠然と働くことを考えているものの、自分が何を求めているか不明確な自己理解不足があり、また、仕事と介護の両立についても現実的な検討ができていないため、選択肢やその実現方法を描けず、どうしたらよいかわからなくなっていることが問題である。
② その根拠
1. 自己理解の不足:
◦ 「なんとなく一日が過ぎているように感じる」「一日の充実感がない」といった現在の充実感のなさの解消策として、「やっぱり少し働いた方がいいのかな」と仕事しか考えられていない。
◦ 仕事へのイメージも漠然としており、「仕事は大変だったがやりがいがあった」「毎日が充実し刺激があって楽しかった」という過去の仕事観と、現状の「世界が狭くなっている気がして」という感覚があるものの、具体的に「何を求めているのか」が不明確である。
2. 仕事理解と情報の不足:
◦ 「働きながら両親のこともみていくのは想像できない」「中途半端になってしまい新しい職場に迷惑をかけてしまうかも」「自分に都合よく働くのは自分勝手」「これまでそんな働き方をしてきていないし考えてもいなかった」といった発言から、仕事と介護の両立にネガティブな「思い込み」や印象を持っており、自身の状況に即した働き方を柔軟に考えられず、その実現方法も不明確であることが伺える。
◦ また、「今更、就職活動をするのも不安がある」と発言しており、就職活動に関する知識も不足していると考えられる。
【設問4】 設問3で答えた内容を踏まえ、今後あなたがこのケースを担当するとしたら、どのような方針でキャリアコンサルティングを進めていくか記述せよ。
今後このケースを担当するにあたり、以下の方針でキャリアコンサルティングを進めます。
1. 信頼関係の構築と傾聴: 相談者の「どうしたらいいのか…」という迷いや不安の気持ちに寄り添いながら、丁寧に傾聴を続け、更なる信頼関係の構築に努めます。また、在職中の多忙な日々や苦労について労いを示します。
2. 自己理解の促進: 「やっぱり少し働いた方がいいのかな」という思いの背景にある「充実感」「刺激」といった言葉に焦点を当てて深掘りし、相談者が本当に何を求めているのか、具体的な「求めるもの」の明確化を促します。
3. 選択肢の検討と拡大: 求めるものを得るための方法として、仕事のみならず、「学び直し」や「地域活動」といった仕事以外の活動も含めて検討を促し、相談者の選択肢を広げます。
4. 情報提供と仕事理解・両立支援:
◦ 仕事に関しては、「中途半端」といった介護との並行に対する否定的な印象を受け止めつつ、厚生労働省の「仕事と介護の両立事例」や関連制度、短時間勤務などの多様な働き方に関する情報を提供し、理解と検討を深めます。
◦ 仕事以外の活動については、相談者の希望に沿った内容を中心に情報収集を促し、理解を深め、検討の幅を広げられるよう支援します。
◦ 就職活動への不安に対しては、産業雇用安定センターの利用を提案するなど、具体的な情報提供を行います。
5. 主体的な意思決定の支援: 上記の支援を通じて、相談者が自身にとって最も望ましい選択肢を主体的に判断できるよう促し、その実現方法(仕事の場合は具体的な就職活動方法など)を理解することで、迷いや不安を軽減し、望む方向へ進めるよう支援します。
——————————————————————————–
解答を作成する際のポイントと思考の組み立て方
音声解説はコチラ
リアルな事例への対応
第29回試験の論述は、シニア女性の退職後の生活、再就職、そして親の介護という、現実の相談現場でよく見られる具体的な悩みを扱っています。このような事例では、単に知識を問うだけでなく、相談者の多面的な状況や感情を深く理解し、寄り添う姿勢が求められます。
「問題と根拠」の重視
今回のJCDAの論述試験がキャリアコンサルティング協議会の形式に「寄せている」という言及があるように、「相談者の問題」と「その根拠」を具体的な言動から明確に記述することが非常に重要です。
2. 思考の組み立て方(特に設問3と4)
事例の徹底的な読み込みと感情の把握
• 相談者の話した内容から、**「やりたいこと・求めていること(アクセル)」と、それに対して「ブレーキをかけている要因」**を詳細に抽出します。
◦ アクセル: 「充実感がない」「やりがいがあった」「刺激があって楽しかった」「世界が狭くなった気がする」「少し働いた方がいいのかな」。
◦ ブレーキ: 「働きながら両親をみるのは想像できない」「中途半端」「新しい職場に迷惑をかけるかも」「自分に都合よく働くのは自分勝手な気がする」「今更就職活動をするのも不安」。
• 相談者の抱える**「不安」や「葛藤」**(仕事と介護の両立、就職活動への不安など)を言語化します。
b. 問題の特定と「分割想定法」の適用
• 相談者の「アクセル」と「ブレーキ」を分析し、根本的な問題点を特定します。
◦ この事例では、「やりたいことはあるが、ブレーキがかかり、自分で解決策を見出せない」状況と捉えられます。
◦ 篠原氏は、この状況を解決するために**「分割想定法」が非常に重要だと述べています。これは、相談者が抱える複数の問題や不安(例:仕事したい気持ち、介護の心配、就職活動の不安)を一度に全て解決しようとせず、一つずつ切り離して考える**アプローチです。
• 具体的には、以下の3つの問題点を抽出できます。
1. 自己理解不足: 求められているものが曖昧であること。本当に仕事がしたいのか、何をしたいのかがはっきりしない。
2. 仕事と介護の両立に関する知識不足: 「中途半端」という思い込みがあるため、柔軟な働き方のイメージが持てない。
3. 就職活動に関する知識不足: 就職活動自体への不安。
• これらの問題点に対し、自己理解不足が最も優先して対処すべきものと考えることができます。なぜなら、本当に何をしたいのかが明確でなければ、両立方法や就職活動を真剣に考えることができないからです。
c. 今後の方針の立案(設問4)
• 特定した問題点と、相談者の**「どうしたらいいのかよくわからない」という気持ちに寄り添う**ことを出発点とします。
• 「分割想定法」の考え方に基づき、以下のステップで支援方針を具体化します。
1. 現状の共感と信頼関係の構築: 相談者の「分からない」気持ちを受け止める。
2. 自己理解の深掘り: 漠然とした「充実感」を具体的に言語化できるよう促す。
3. 情報提供による課題の払拭:
▪ 仕事と介護の両立: 厚生労働省の両立支援事例や制度の紹介により、「中途半端」という思い込みを払拭し、両立の可能性を示す。
▪ 就職活動: 産業雇用安定センターなどの利用を促し、不安の軽減を図る。
4. 選択肢の拡大: 仕事以外の活動(学び直し、地域活動など)も視野に入れ、多角的な選択肢を検討できるようにする。
5. 主体的な意思決定の支援: 最終的に相談者が自身の希望に基づき、具体的な行動に移せるよう支援する。
3. 回答作成時の具体的なコツ
• 事例記録の言葉を引用する: 相談者の発言を直接引用することで、根拠の具体性が増し、説得力のある解答になります。
• 「キャリアコンサルタントとして」の視点: 設問2や設問4では、キャリアコンサルタントとしてどのような意図で応答し、どのような支援を行うかを具体的に記述します。共感的理解、問いかけによる内省の促進、情報提供、主体性支援などがキーワードになります。
• 一貫性を持つ: 設問3で特定した問題点と根拠が、設問4の支援方針と論理的に繋がっていることが重要です。問題の解決に直接つながる支援策を提示します。
• 具体性: 漠然とした表現ではなく、「厚生労働省の事例」「産業雇用安定センター」といった具体的な情報源や支援機関を記述することで、実践的な解答になります。
• 制限時間と文字数を意識: 実際の試験では、限られた時間と解答欄の中で、簡潔かつ明確に記述する練習が求められます。
これらのポイントと思考プロセスを参考に、効果的な論述解答を作成してください。
ケース概要:Zさんの状況
このケーススタディでは、60歳で定年退職したZさん(女性)が直面するキャリアとライフプランの課題を探ります。仕事一筋の人生から一転、充実感の喪失と親のサポートという新たな役割の間で揺れ動くZさんの状況を理解しましょう。
相談の核心
「仕事はやりがいがあって充実していた。でも今は世界が狭くなった気がする。親のこともあるけれど、少し働いた方がいいのかな…でも、どうしたらいいのかわからない…」

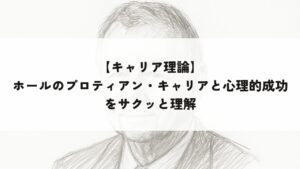

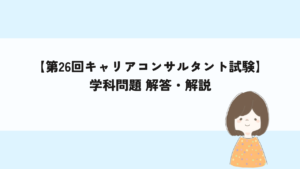
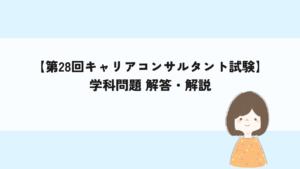
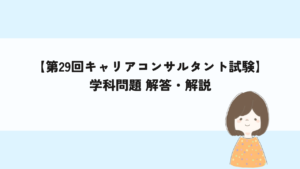
コメント