 チャチャ
チャチャ森田療法っていったいどんな療法なんだろう



「あるがまま」を受け入れることを重視する森田療法。しっかり理解しよう。
今回は、数あるカウンセリング理論の中から、日本独自の心理療法である森田療法(もりたりょうほう)について、試験で問われやすいポイントに絞って分かりやすく解説していきます。
不安を抱えるクライエントへの支援に応用できる視点として非常に重要ですので、しっかり押さえていきましょう。
・森田療法
・あるがまま
・絶対臥褥期(ぜったいがじょくき)
インフォグラフィック版
森田療法へようこそ
このページは、森田療法の核心的な概念を対話的に学ぶための学習ツールです。精神科医・森田正馬によって創始されたこの日本独自の心理療法は、不安を克服するのではなく「あるがまま」に受け入れ、建設的な行動をとることを目指します。各セクションのインタラクティブな要素を通じて、試験合格に必要な知識を深く理解しましょう。
森田療法の4つの重要概念
下のタブをクリックして、それぞれの概念を詳しく見ていきましょう。
精神交互作用
不安の悪循環が生まれるメカニズム。下の図の各要素にマウスを合わせると説明が表示されます。
(例:動悸)
他の理論との比較
森田療法と他の心理療法が「不安」にどうアプローチするかを比べてみましょう。下のメニューから比較したい理論を選んでください。
森田療法のアプローチ
不安は「あるがまま」に受け入れ、なくそうとしない。感情と行動を切り離し、目的本位の行動を促す。
認知行動療法のアプローチ
不安を引き起こす非合理的な認知(考え方のクセ)を見つけ、それを合理的・現実的なものに修正することを目指す。
理解度チェッククイズ
学習した内容が身についているか、簡単なクイズで確認しましょう。
ブログ版
1. 森田療法とは?まず全体像をつかもう!
森田療法は、精神科医の森田正馬(もりたまさたけ)によって創始された、神経症(現在の不安障害など)に対する心理療法です。
一番のポイントは、不安や症状を敵と見なして無くそうとするのではなく、「あるがまま」に受け入れ、やるべきこと(目的本位の行動)を行っていくという点にあります。この考え方は、キャリアの悩み、特に「失敗したらどうしよう」「人からどう見られるか不安」といった不安を抱える相談者への支援に大きなヒントを与えてくれます。
[森田正馬の画像]
## 2. 【最重要】試験に出る!森田療法の4つのキーワード
森田療法を理解するために、絶対に押さえておきたい4つのキーワードがあります。それぞれの意味と具体例、そしてキャリア支援への応用をセットで覚えましょう。
① 精神交互作用(せいしんこうごさよう)
これは、不安の悪循環が生まれるメカニズムを説明する言葉です。
- 仕組み:ある身体感覚に注意を集中すると、その感覚がますます鋭敏になり、さらにその感覚が気になって注意が固着してしまう、という悪循環のことです。
- 具体例:「人前で話すと動悸がする」→「動悸に注意が向く」→「ますます心臓がドキドキする」→「動悸が気になって話に集中できない」というループ。
- キャリア支援への応用:
- 面接:「うまく話さなきゃ」と意識しすぎて、頭が真っ白になる学生。
- 職場のプレゼン:「声が震えたらどうしよう」と不安になり、余計に声が震えてしまう若手社員。
- クライエントがこのような悪循環に陥っていることに気づかせ、「不安なのは自然なこと。完璧を目指さなくていい」と伝えることで、悪循環を断ち切るきっかけを作れます。
② あるがまま
森田療法の代名詞ともいえる、最も重要な概念です。
- 意味:不安、恐怖、不快な感情などを、無理になくそうとしたり、理想的な状態にしようとしたりせず、そのままにしておくことです。これは「諦め」や「開き直り」とは全く違います。
- ポイント:「感情は感情のままに、行動は行動として切り離す」という考え方です。不安を抱えたままで、今やるべきことをやる、という建設的な態度を指します。
- キャリア支援への応用:
- 適職が見つからない不安:「不安な気持ちはあっていい。その気持ちを抱えたまま、まずは一つ求人情報を見てみよう」と具体的な行動を促す。
- 職場復帰への不安:「また体調を崩すかも、という不安は当然です。その不安を認めつつ、まずは短時間勤務から始めてみませんか」と提案する。
- 「あるがまま」は、クライエントが感情に振り回されず、現実的な一歩を踏み出すことを力強く後押しする考え方です。
③ 目的本位(もくてきほんい)の行動
「あるがまま」とセットで理解したいのが、この「目的本位」です。
- 意味:自分の感情や気分(気分本位)に左右されるのではなく、建設的な目的や、今ここでなすべきことに基づいて行動することです。
- 対義語:気分本位(きぶんほんい)。「やる気が出ないからやらない」「不安だからやめる」といった行動です。
- キャリア支援への応用:
- 転職活動が停滞している相談者:「『気分が乗らない』という気持ちは分かります。ですが、あなたの『より良い環境で働きたい』という目的のために、今日は1社だけエントリーシートを書いてみませんか?」
- 資格取得の勉強が続かない相談者:「『面倒だ』という気分に流されるのではなく、『スキルアップしてキャリアの選択肢を広げる』という目的を思い出してみましょう。」
- クライエントが感情の波を乗りこなし、行動を継続できるよう支援するための強力なキーワードです。
④ 生の欲望(せいのよくぼう)
これは、人間の根源的なエネルギーに関する考え方です。
- 意味:人間には誰しも「より良く生きたい」「成長したい」「認められたい」という、**向上心や自己実現への欲求(生の欲望)**がある、という考え方です。
- ポイント:森田療法では、不安や悩みは「生の欲望」の裏返しだと捉えます。「失敗するのが怖い」という不安は、「立派にやり遂げたい」という強い欲望があるからこそ生まれる、と考えます。
- キャリア支援への応用:
- 一見ネガティブに見えるクライエントの悩みの中に、ポジティブな「生の欲望」を見つけ出す視点として使えます。
- 例:「人前で話すのが怖い」という悩み → 裏には「自分の考えをしっかり伝えたい、認められたい」という生の欲望があるのではないか?と捉え直す。
- 例:「転職に失敗するのが怖い」という悩み → 裏には「自分の力を発揮できる場所で活躍したい」という生の欲望があるのではないか?と探る。
- この視点を持つことで、クライエントの悩みを問題点としてだけでなく、成長のエネルギーとして捉え、自己肯定感を高める支援ができます。
## 3. 他の理論との違い(試験で問われやすい比較ポイント)
| 理論 | 不安へのアプローチの違い |
|---|---|
| 森田療法 | 不安は**「あるがまま」**に受け入れ、なくそうとしない。感情と行動を切り離し、目的本位の行動を促す。 |
| 精神分析療法 | 不安の原因を過去の無意識的な葛藤に求め、その洞察を目指す。 |
| 認知行動療法 | 不安を引き起こす非合理的な認知(考え方のクセ)を見つけ、それを合理的・現実的なものに修正することを目指す。 |
| 来談者中心療法 | カウンセラーの共感的理解・無条件の肯定的関心・自己一致により、クライエントが自ら不安を乗り越える力を引き出す。 |
森田療法の特徴は、原因追及や認知の修正よりも、「今、ここ」での具体的な行動を重視する点にあると覚えておきましょう。
## まとめ:試験合格に向けて
森田療法の講義は以上です。最後に、試験対策として最低限覚えておくべきことをまとめます。
- 基本姿勢:不安はなくそうとせず、あるがままに受け入れる。
- 行動指針:気分に流されず、目的本位で行動する。
- 不安のメカニズム:精神交互作用という悪循環を理解する。
- 悩みの捉え方:悩みの裏には生の欲望(向上心)が隠れている。
これらのキーワードとその意味を、キャリア支援の具体的な場面と結びつけて理解しておけば、試験で問われた際に必ず対応できます。頑張ってください!応援しています!👍

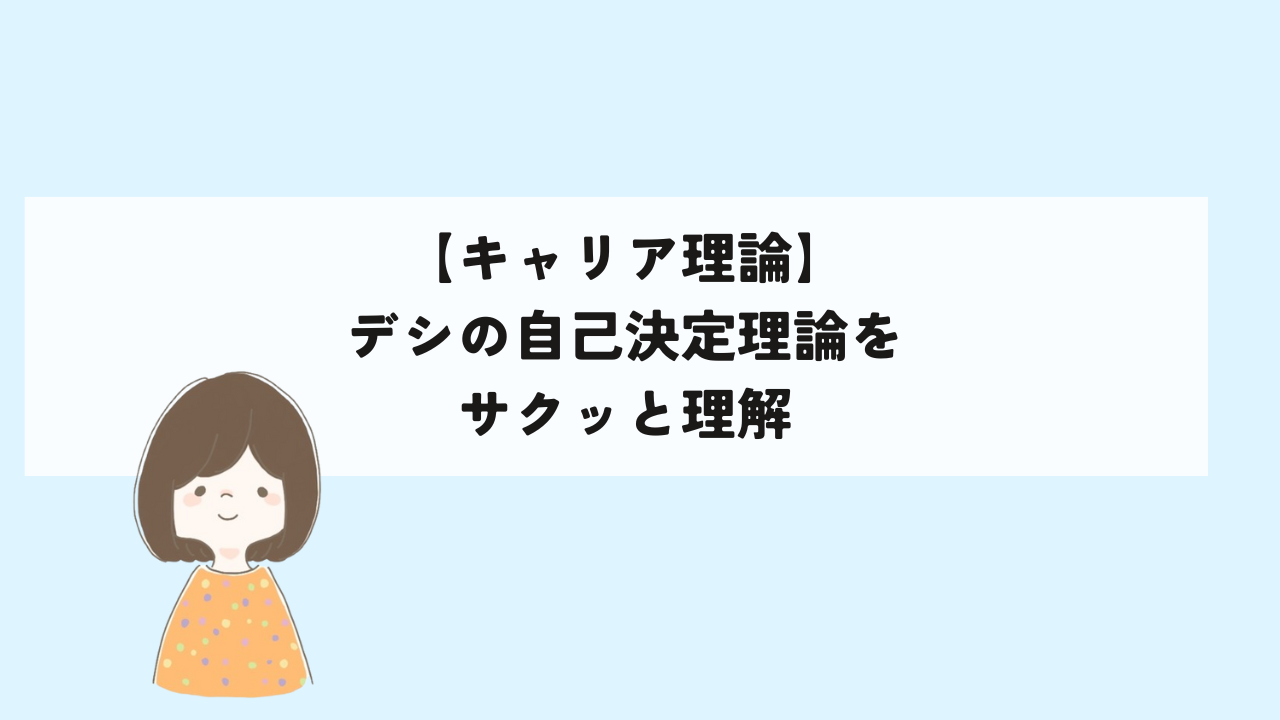
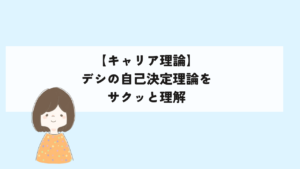
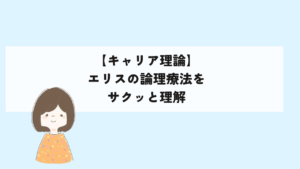

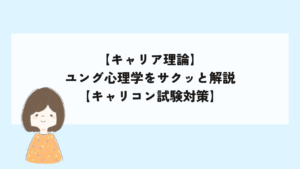
コメント