 チャチャ
チャチャ自律訓練法ってなんだ?
キャリアコンサルタント試験で問われるシュルツの理論について、特に重要な「自律訓練法」を中心に、ポイントを絞ってわかりやすく解説します。
ヨハネス・シュルツのキーワード
・自律訓練法
目次
1. 創始者と背景
- 創始者:ヨハネス・ハインリヒ・シュルツ(J.H. Schultz)(1884-1970)
-
- ドイツの精神科医です。試験では「シュルツ」という名前を覚えておけば十分です。
- 開発の背景:
- シュルツは、催眠状態にある患者が共通して「手足が重たい」「手足が温かい」といった感覚を体験することに着目しました。
- そこから、「自分自身で心身をリラックスさせ、催眠状態に似た心身の状態を意図的に作り出すことができるのではないか」と考え、体系化したのが自律訓練法(Autogenic Training)です。
2. 自律訓練法とは? – 重要なキーワード
自律訓練法は、自己催眠の一種であり、心身の緊張を和らげるためのリラクセーション技法です。以下のキーワードが試験対策として重要です。
- 目的: 自律神経系(交感神経と副交感神経)のバランスを整え、心身の過剰な緊張を緩和し、ストレス反応を軽減すること。
- キーワード:
- 受動的注意集中(Passive Concentration): 「〜しなければならない」と努力するのではなく、「〜な感じがする」と、自然に生じる感覚を受け身で待つ姿勢が重要です。頑張りすぎないことがポイントです。
- 背景公式: 訓練を始める前に「気持ちがとても落ち着いている」と心の中で唱え、リラックスした状態を準備します。
3. 公式練習(段階的リラクセーション)
自律訓練法の中核となるのが、以下の6つの公式を順番に行う「公式練習」です。この順番と感覚は必ず覚えておきましょう。
| 段階 | 公式の名称 | 感覚の内容 | 目的・効果 |
| 背景公式 | – | 気持ちが落ち着いている | 訓練に入るための準備 |
| 第1公式 | 重感練習 | 手足が重たい | 筋肉の弛緩(ゆるむこと) |
| 第2公式 | 温感練習 | 手足が温かい | 血管の拡張、血行促進 |
| 第3公式 | 心臓調整練習 | 心臓が静かに規則正しく打っている | 心拍の安定 |
| 第4公式 | 呼吸調整練習 | 楽に呼吸している | 呼吸の安定 |
| 第5公式 | 腹部温感練習 | お腹が温かい | 内臓の血行促進 |
| 第6公式 | 額部涼感練習 | 額が涼しい | 頭部の血管収縮、頭がスッキリする |
【試験のポイント】
- 第1・第2公式が最も基本であり、重要とされています。
- 手足の「重感」「温感」から始まり、身体の中心部へと進んでいく流れを理解しましょう。
- 最後に額を涼しくすることで、頭は冷静な状態を保ちます(のぼせを防ぐ)。
4. 消去動作(覚醒)の重要性
訓練を終える際には、消去動作と呼ばれる覚醒のための動作が必須です。これを怠ると、眠気やだるさが残ってしまう可能性があります。
- 消去動作の例:
- 両手の指を強く握ったり開いたりする。
- 両腕を力強く曲げたり伸ばしたりする。
- 大きく伸びをする。
- 最後に深呼吸をする。
「自律訓練法では、終了時の消去動作が重要である」という点は、正誤問題などで問われやすいポイントです。
5. キャリアコンサルティングにおける活用
キャリアコンサルタントとして、クライエントのストレスケアに自律訓練法の知識は役立ちます。
- ストレス対処: 職場の人間関係や過重労働、将来への不安などで強いストレスを感じているクライエントに対し、セルフケアの一環として情報提供ができます。
- 緊張緩和: 面接前など、極度の緊張を感じるクライエントの不安を和らげる手段として活用できます。
- 自己効力感の向上: 「自分で自分の心身をコントロールできる」という感覚は、クライエントの自己効力感(セルフ・エフィカシー)を高めることにつながります。
試験対策まとめ
- 創始者: シュルツ
- 技法: 自己催眠によるリラクセーション法
- キーワード: 受動的注意集中
- 公式練習: 重感 → 温感 → 心臓 → 呼吸 → 腹部温感 → 額部涼感 の順番
- 必須事項: 終了時の消去動作
この内容をしっかり押さえておけば、シュルツに関する問題には対応できるはずです。学習応援しています!


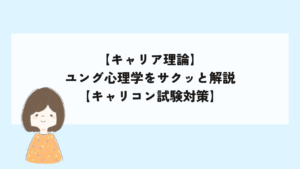

コメント