 チャチャ
チャチャ雇用政策研究会報告書も重要資料だけど、そんなに資料ばっかり読めないよ……



大丈夫。重要なポイントだけチェックしよっか
今回は、「雇用政策研究会報告書」について、試験に出題されそうな重要ポイントを、特に重要な数値データに焦点を当ててわかりやすく解説します。
雇用政策研究会報告書は、今後の日本の雇用政策の羅針盤となるもので、特に「多様性」「労働供給制約」「テクノロジーの活用」といった、キャリアコンサルタントとして知っておくべきキーワードが満載です。しっかり理解を深めていきましょう。
インフォグラフィック学習版
多様な個人が活躍できる労働市場へ
2024年8月の雇用政策研究会報告書は、人口減少という大きな課題に対し、個々の状況に関わらず誰もが包摂され、活躍できる社会を目指すための羅針盤です。本ダッシュボードで、その要点をインタラクティブに探ります。
2040年、労働市場の姿
少子高齢化が進む中、2040年の労働力人口は、女性とシニア層が大きな割合を占めると予測されています。これは、働き方の前提が根本的に変わることを意味します。多様な人材の活躍なくして、経済の成長はあり得ません。
政策の転換点
企業が労働者を「選ぶ」時代から、労働者に「選ばれる」時代へ。処遇改善や柔軟な働き方の提供が、企業の持続可能性を左右します。
多様な人材の活躍が鍵
女性、シニア、キャリアブランクを持つ方など、多様な背景を持つ人々が直面する課題は様々です。ここでは、報告書が示す現状のデータと課題をグループ別に可視化します。下のボタンで表示を切り替えてください。
男性の育児休業取得の現状
取得率は17.1%に留まり、その半数以上が2週間未満の短期取得です。制度利用が進まない背景には、収入減への懸念や職場の雰囲気があります。
女性管理職比率
12.9%
(2022年)
国際的に見ても低い水準にあり、キャリアアップの機会創出が急務です。
男女間の賃金格差
男性の賃金を100とした場合、女性の賃金水準は78.2。この差を埋めるための取り組みが求められています。
介護離職の現状
10.6万人/年
(2022年)
そのうち約8万人が女性であり、仕事と介護の両立支援が不可欠です。
女性特有の健康課題
月経や更年期症状などが仕事のパフォーマンスに与える影響は大きく、経済損失にも繋がっています。企業のヘルスリテラシー向上が生産性向上にも寄与します。
仕事とスキルの未来
生成AIなどの新たなテクノロジーは、仕事を奪うのではなく、仕事のやり方(タスク)を大きく変えます。これからのキャリア形成では、変化に対応するためのスキルの見直しが不可欠です。
タスクの変化
AIとの協働が当たり前に
人間が全てのタスク(情報収集、資料作成、分析、判断)を実行する。
AIが情報収集や資料作成の草案を担い、人間はAIの出力を評価・検証し、最終的な意思決定や創造的な業務に集中する。
今後、重要性を増すスキル
課題設定能力
ソーシャルスキル
批判的思考力
創造性
AIリテラシー
学び続ける力
新しい労働市場のインフラ
個人の主体的なキャリア形成を社会全体で支えるため、労働市場の仕組み(インフラ)の整備が急がれています。報告書が示す3つの重要な概念を紹介します。
セルフ・キャリアドック
企業が従業員に対し、キャリアコンサルティングや研修を定期的・体系的に提供する仕組み。従業員のキャリア自律を促し、組織の活性化と定着率向上に繋げます。
job tag(職業情報提供サイト)
様々な職業の仕事内容、求められるスキル、タスク等を網羅した公的なWebサイト。自己診断も可能で、個人のキャリア選択や学び直しの指針となります。
キャリアラダーの構築
「どのスキルを身につければ、どう処遇が向上するか」というキャリアの道筋を業界ごとに見える化する取り組み。個人の学習意欲を高め、スキルの適正な評価を目指します。
報告書の全体像:目指すは「多様な個人が活躍できる労働市場」
まず、この報告書が目指す大きな方向性を掴みましょう。
それは、タイトルにもある通り「多様な個人が置かれた状況に関わらず包摂され、活躍できる労働市場の構築」です。
人口減少と少子高齢化による「労働供給制約」という大きな課題を背景に、これまでのように企業が労働者を選ぶだけでなく、労働者から「選ばれる」企業になることが重要だと強調されています。実際に、2040年には労働力人口に占める女性の割合が47%、60歳以上が31%に達すると予測されており、多様な人材の活躍なくして経済成長はあり得ない、という強いメッセージが込められています。これは、キャリアコンサルティングの現場でも非常に重要な視点です。
それでは、具体的なポイントを見ていきましょう。
試験に出る!重要ポイント5選
ポイント1:2040年に向けた雇用政策の考え方の大転換
従来の雇用政策は、失業対策など「労働者の雇われる力」に重点が置かれていました。しかし、本報告書では、人手不足を背景に「(企業の)労働者から選ばれる力」や「労働者が活躍しやすい環境整備」を重視する政策へと、大きく舵を切ることを提言しています。
- キーワード:「労働者から選ばれる力」
- 背景: 労働供給制約(人手不足)
- 企業の取り組み: 賃金等の処遇改善、多様な働き方を可能にする環境整備、人材育成への注力
【キャリコン視点】
求職者支援だけでなく、企業に対して「どうすれば人材が集まり、定着するか」という視点でのコンサルティング(リテンションマネジメント)の重要性が増していることを示唆しています。
ポイント2:多様な個人の労働参加を促す具体的な取り組み
報告書の中で最も多くのページが割かれているのが、多様な人材の活躍促進策です。ここは具体的な数値と共に、細部まで問われる可能性が高いので、しっかり押さえましょう。
- 多様な正社員制度の普及と課題
- 職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」制度がある事業所は 23.5%(2023年度)。しかし、短時間正社員の実際の利用率は**3.2%**に留まるなど、制度の普及と利用促進が課題。
- ミドル・シニア世代のさらなる活躍
- シニアの就業率は上昇傾向にあり、60~64歳で74.0%、65歳以上でも25.2%(2023年)に。
- 一方で、70歳までの就業確保措置を設けている企業は29.7%(2023年)に留まっており、さらなる推進が求められる。
- 男女ともに活躍できる環境整備
- 男性の育児休業取得率は17.1%(2022年)と依然低く、さらに取得者の51.5%が2週間未満という短期間の取得に留まる。
- 女性の活躍も課題が多く、第一子出産前後の継続就業率は約7割、女性管理職比率は12.9%(2022年)と低い水準。
- 男女間の賃金格差も依然として大きく、男性を100とした場合、女性の賃金水準は78.2(2023年)。
- 介護を理由とした離職者数は年間10万6千人(2022年)にのぼり、そのうち約8万人が女性。
- 女性特有の健康課題(月経、更年期症状など)への対応。企業の生産性にも影響するため、ヘルスリテラシーの向上や、性別を問わず利用できるシックリーブ(病気休暇)制度の普及が求められる。
- キャリアブランクのある人への支援
- 育児中で無業の女性のうち、就業を希望している割合は61%、その数は80万人にのぼる。
- 自己実現(留学、ボランティア等)のために離職した人が円滑に再就職できる労働市場の構築。
【キャリコン視点】
これらの具体的な数値を把握しておくことで、論述や面接で現状の課題を説明する際に説得力が増します。相談者の属性(年齢、性別、健康状態、ライフイベントなど)に応じた、きめ細やかな支援の根拠となる情報が満載です。特に「女性特有の健康課題」は新しい視点として注目です。
ポイント3:生成AIなど新技術と雇用の共存
テクノロジーの進展、特に生成AIが雇用に与える影響についても詳述されています。
- 雇用の代替ではなく「タスクの変化」:多くの労働者の仕事内容(タスク)が変化する。
- 求められるスキルの変化:AIの示す結果を評価・検証するスキル、AIに代替されない対人スキル(ソーシャル・スキル)や課題設定能力の重要性が増す。
- 円滑な導入のための労使コミュニケーション:導入にあたっては、労働者の意見を十分に聞き、納得感を高めることが不可欠。
【キャリコン視点】
「AIに仕事が奪われる」という不安を抱く相談者に対し、どのようなスキルを身につければ価値を発揮し続けられるのか、具体的な助言を行う際の参考になります。
ポイント4:キャリア形成を支える「労働市場のインフラ整備」
キャリアコンサルタントの役割と直結する重要なパートです。
- 企業の役割:セルフ・キャリアドックの導入促進
- 従業員の主体的なキャリア形成を支援する仕組みとして、キャリアコンサルティング面談やキャリア研修を体系的・定期的に行う「セルフ・キャリアドック」の重要性を強調。
- 個人の役割:キャリアの棚卸しと学び直し
- キャリア形成・リスキリング支援センターなどでの無料キャリアコンサルティングの活用。
- 教育訓練給付制度の活用による、デジタル分野などのスキル習得。
【キャリコン視点】
セルフ・キャリアドックは頻出用語です。企業への導入支援や、個人に対する公的支援制度の活用を促す場面で、この報告書の内容が説得力を持つでしょう。
ポイント5:「労働市場の見える化」とキャリアラダーの構築
個人の主体的なキャリア選択を支援するため、「見える化」がキーワードとなっています。
- 見える化のツール:job tag(職業情報提供サイト)
- 職業内容、求められるスキル、タスク等の情報提供サイト。自己診断ツールもあり、学生のキャリア教育への活用も期待される。
- 目指すもの:キャリアラダーの構築
- 「どのようなスキルや経験を積めば、どの程度の処遇が得られるか」という道筋(キャリアラダー)を業界ごとに明確化し、個人のスキル習得のインセンティブを高める。
- これにより、スキルが適正に評価され、処遇改善につながる好循環を目指す。
【キャリコン視点】
相談者がキャリアプランを立てる際、「job tag」を使って自己分析や職業理解を深めたり、「キャリアラダー」の考え方を用いて目標設定を支援したりと、実践的な活用が考えられます。
まとめ
今回の報告書は、これからのキャリアコンサルタントが向き合うべき日本の労働市場の課題と、その解決策が具体的に示された「教科書」とも言える内容です。
- 企業は「選ばれる」存在へ
- 多様な人材(特に女性・シニア)の活躍が不可欠
- AI時代を生き抜くためのスキルシフトと学び直し
- キャリア形成を支えるインフラ(キャリコン、見える化)の重要性
これらのポイントを自分の言葉で説明できるよう、しっかり読み込んで試験に備えましょう!


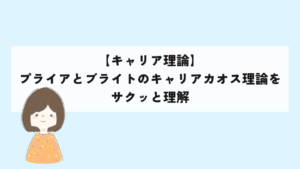

コメント