今回は、レント、ブラウン、ハケットの「社会的認知キャリア理論(SCCT)」について、詳しく解説していきます。
この理論は、「なぜ人はその職業に興味を持ち、目標を立て、達成していくのか?」という心の動きを説明する理論。
 まい
まい試験に出るポイントに絞って、一緒に見ていきましょう。
・社会認知的キャリア理論(SCCT)
インフォグラフィック学習版
理論の核心をなす3つの柱
自己効力感
「自分ならできる!」という自信
結果期待
「やったらどうなる?」という予測
個人的目標
「よし、やろう!」という決意
3つの主要モデル
実践への応用:コンサルタントの視点
自己効力感を育む
小さな成功体験を発見し、言語化することで、相談者の「できる」感覚を支援する。
結果期待を現実的に
過度な期待や思い込みを修正するため、客観的な情報提供を行い、現実的な見通しを立てる。
障壁の特定と対処
キャリア選択を阻む障壁(家族の反対など)を明確にし、具体的な対処法を共に考える。
選択肢の拡大
「これしかできない」という思い込みに気づかせ、早期に除外された可能性を再検討する。
はじめに:この理論の「キホン」
まず、この理論の正式名称は社会的認知キャリア理論(SCCT)です。アルバート・バンデューラという心理学者が提唱した社会的学習理論を、キャリア分野に応用したものです。
一番大事なポイント: 「個人の信念が、キャリアの興味や選択に大きな影響を与える」と考えている点です。
Part 1:SCCTを支える3つの「中心的な柱」
試験では、この3つのキーワードの意味を正確に理解しているかが問われます。
① 自己効力感 (Self-Efficacy)
- ひと言でいうと: 「自分なら、これをうまくやれるはずだ!」という自信や期待のこと。
- ポイント: これは「能力そのもの」ではありません。「自分はこの課題をどの程度うまくやれそうか?」という主観的な感覚です。自己効力感が高いと、人はその分野に挑戦しやすくなります。
- 自己効力感は何から作られる?(ここが超重要!)
- 個人的な遂行達成(最も強力): 自分で実際にやってみて「できた!」という成功体験。
- 代理経験: 自分と似た他人が成功するのを見て「あの人ができたなら自分もできるかも」と思うこと。
- 言語的説得: 周囲の人から「君ならできるよ!」と励まされること。
- 情緒的・生理的状態: ドキドキする、不安になる、逆にリラックスしている、といった心身の状態。
② 結果期待 (Outcome Expectations)
- ひと言でいうと: 「もし、それをやったら、どんな結果になるだろう?」という未来の結果の予測。
- ポイント: 自己効力感が「できるか?」という自信なのに対し、結果期待は「やったらどうなる?」という予測です。
- 例:「プログラマーになれたら(自己効力感)、高い給料がもらえそうだ(結果期待)」
- 例:「営業職に就けたら(自己効力感)、人脈が広がりそうだ(結果期待)」
③ 個人的目標 (Personal Goals)
- ひと言でいうと: 「よし、これをやろう!」と決意し、行動を持続させる意志のこと。
- ポイント: 自己効力感が高く、良い結果期待が持てると、人は「それを目標にしよう」と決めやすくなります。目標を持つことで、人は具体的な行動を起こし始めます。
Part 2:試験に出る!SCCTの3つの「主要モデル」
この3つの柱が、どのように相互作用してキャリアが形成されるのかを示したのが、以下の3つのモデルです。
1. 興味モデル(どうやって「好き」が生まれるか)
人の興味は、自己効力感と結果期待から生まれる、と考えます。
【流れ】
「これ、得意かも!(自己効力感)」 + 「やったら楽しそう!(結果期待)」
↓
「面白い!もっと知りたい!(興味の発生)」
- 試験のポイント: 興味は、単に「好きだから」で終わらせず、その手前にある「自己効力感」と「結果期待」が源泉になっている、と理解しておくことが重要です。
2. キャリア選択モデル(どうやって「道」を選ぶか)
興味が、どのようにして具体的なキャリアの選択につながるかを説明します。
【流れ】
興味 → 目標設定(〇〇になろう!と決める) → 行動(学校選び、就職活動など) → 遂行達成(経験を積む)
- 試験のポイント: この流れの途中に**「支援(サポート)」と「障壁(バリア)」**が影響を与えることを忘れてはいけません。
- 支援の例: 親の応援、奨学金制度、信頼できるキャリアコンサルタントの存在
- 障壁の例: 家族の反対、経済的な問題、性別による思い込み(ジェンダー・ステレオタイプ)
3. キャリア遂行モデル(どうやって「成果」を出すか)
選んだ道で、人がどれだけ成果を上げ、満足できるかを説明します。
- ポイント: ここでも自己効力感が鍵を握ります。
- 過去の成功体験や能力 → 高い自己効力感 → 高い目標設定 → 努力 → 良いパフォーマンス(成果)
- この「良いパフォーマンス」が、また新たな「成功体験」となり、自己効力感をさらに高める…という**好循環(ポジティブ・フィードバック・ループ)**が生まれます。
Part 3:キャリアコンサルティングでの活かし方(実践的視点)
理論を学ぶだけでなく、「だから、どう使うのか?」が問われるのがキャリコン試験です。
- 自己効力感を育む支援:
- 相談者が気づいていない**小さな成功体験(遂行達成)**を一緒に見つけ、言語化する。
- ロールプレイング(模擬面接など)で成功体験を積ませる(代理経験にもなる)。
- 「あなたならできますよ」と、根拠をもって伝える(言語的説得)。
- 結果期待を現実的にする支援:
- 「〇〇になったらバラ色の人生」のような、過度な期待や、「どうせ無理だ」というネガティブな思い込みを、客観的な情報提供(職業理解セミナー、OB/OG訪問など)を通じて修正する。
- 障壁の特定と対処:
- 相談者がキャリア選択をためらっている**「障壁」は何か**を明確にする。「家族の反対」が障壁なら、どうすれば理解を得られるか一緒に考える。
- 選択肢の拡大:
- 「私にはこれしかできない」という低い自己効力感によって、本来可能性があるはずの選択肢を自ら排除してしまっている(早期の選択肢の除外)ことに気づかせ、視野を広げる支援を行う。
まとめ:これだけは覚えよう!
- SCCTはレント、ブラウン、ハケットが提唱。
- 中心は「自己効力感」「結果期待」「個人的目標」の3つ。
- 自己効力感は「やれる!」という自信。4つの情報源(特に遂行達成)から作られる。
- 人の興味は、自己効力感と結果期待から生まれる。
- キャリア選択には支援と障壁が大きく影響する。
- コンサルタントは、相談者の自己効力感を高め、障壁を取り除く手助けをすることが重要。
この理論は、人の可能性を信じ、それを引き出すための強力なツールです。試験勉強、頑張ってくださいね!応援しています!

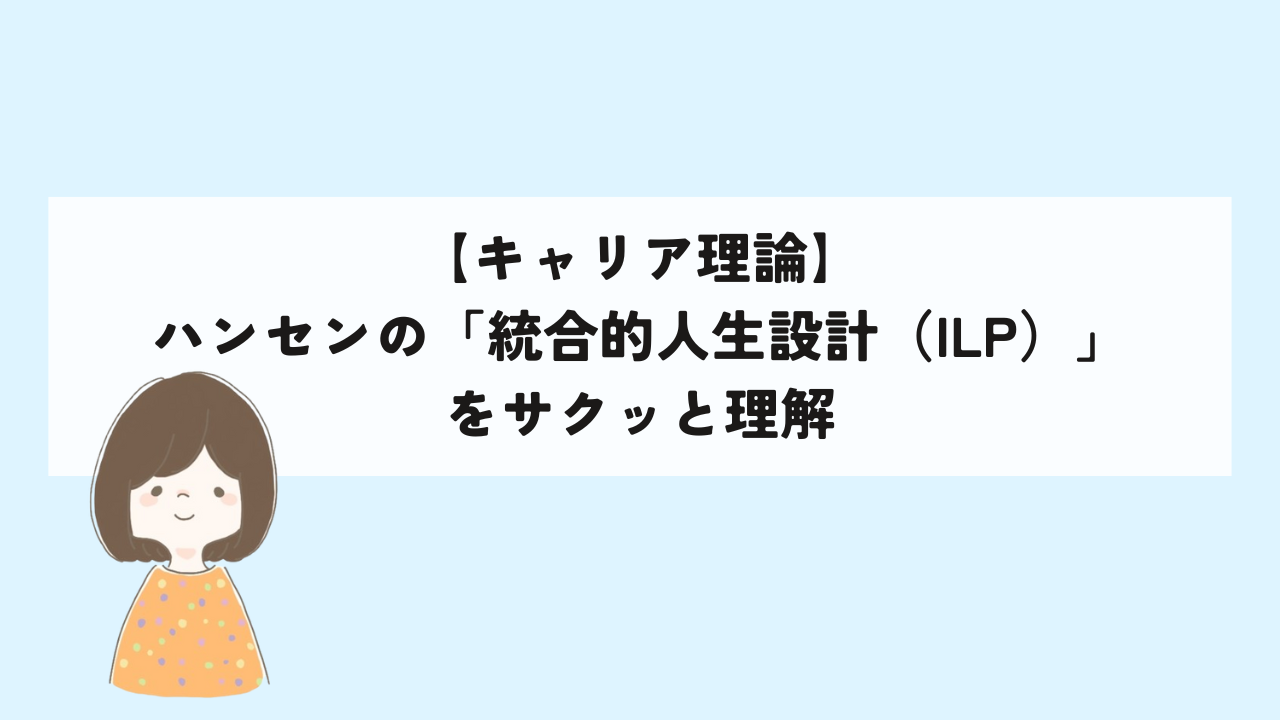
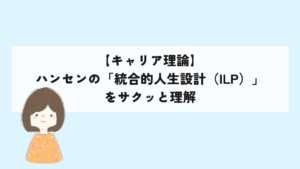
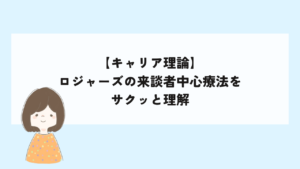

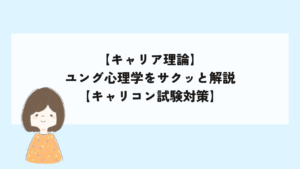
コメント