本日は、キャリアカウンセリングにおいて重要な心理学者、カール・グスタフ・ユングについて学びます。
ユングの考え方は、「一人の人間が、自分らしい人生全体をどう歩んでいくか」を深く見つめるもので、これはまさにキャリアコンサルタントの仕事の根幹に関わる部分なんです。クライエントの深い自己理解を助けるために、とても役立つ視点ですよ。
 まい
まい試験では、ユングの理論のキーワードと、それがキャリアにどう関係するかを理解しておくことが大切です。
インタラクティブ学習版
ポイント1:心の全体像
ユングは心を層状の構造として捉えました。下の図の各層にマウスを合わせると、説明が表示されます。このモデルは、人の行動の背後にある、目に見えない影響を理解するのに役立ちます。
各層にマウスを合わせてください。
解説
ポイント1:心の全体像を理解しよう!「意識」と「無意識」
ユングは、私たちの心をタマネギのように層になっていると考えました。
[氷山のイラスト:海面の上に見えている部分が「意識」、すぐ下の水面下が「個人的無意識」、そして海の奥深くが「集合的無意識」と示されている]
- 意識 (Consciousness)
- これは、私たちが「自分」だと認識している部分です。今、この文章を読んでいるあなたの心、それが意識です。
- 中心には**「自我(Ego)」**があり、自分自身をコントロールしている司令塔のようなものです。
- 個人的無意識 (Personal Unconscious)
- 意識の下にある層です。「忘れてしまった記憶」や「あまりに辛くて抑圧した感情」などがしまわれている、個人的な物置のような場所です。
- 例えば、子どもの頃に犬に追いかけられて怖かった経験を忘れていても、なんとなく犬が苦手、といった形で影響を及ぼすことがあります。
- 集合的無意識 (Collective Unconscious) ★最重要ポイント!
- これがユング理論の最大の特徴です!個人的な経験を超えて、人類が共通して持っている、生まれながらの心の設計図のようなものです。
- 神話や昔話のパターンが世界中で似ているのは、この集合的無意識があるからだとユングは考えました。
- この中には**「元型(アーキタイプ)」**と呼ばれる、様々なイメージの”原型”が入っています。
【試験でのポイント】 フロイトも無意識を説きましたが、ユングはさらに深い「集合的無意識」という概念を提唱した点が大きな違いです。この違いは覚えておきましょう。
ポイント2:集合的無意識の中身「元型(アーキタイプ)」
元型は、人が無意識に反応してしまう普遍的なイメージのことです。たくさんありますが、キャリアを考える上で特に重要なものを4つ紹介します。
- ペルソナ (Persona)
- 社会に適応するために身につけている**「外面的な仮面」**のことです。
- 私たちは、会社では「会社員」、家庭では「親」というように、状況に応じて様々なペルソナを使い分けています。
- キャリア相談での関連:
- クライエントが「会社での役割(ペルソナ)」に自分を同一化しすぎて、「本当の自分がわからない」と悩むケースは非常に多いです。
- 「課長としての自分」と「本来の自分」とのギャップに苦しむなど、ペルソナの問題はキャリアの悩みに直結します。
- シャドウ (Shadow)
- 自分自身が「認めたくない、見たくない」と感じている、心の**「影」の部分**です。
- 一般的にネガティブな側面(嫉妬、怒りなど)と捉えられがちですが、自分が気づいていない素晴らしい可能性や才能が隠されていることもあります。
- キャリア相談での関連:
- 「自分にはリーダーシップなんてない」と思い込んでいる人が、実はシャドウの中に人をまとめる力を隠しているかもしれません。
- クライエントが自分自身をより深く理解し、未開発の可能性に気づく手助けになります。
- アニマ・アニムス (Anima / Animus)
- すべての人が持つ、無意識の中の**「内なる異性像」**です。
- 男性の中の女性的な側面が「アニマ」、女性の中の男性的な側面が「アニムス」です。
- これが成熟すると、人はよりバランスの取れた豊かな人間性を持つことができます。
- 自己(セルフ, Self)
- 心の中心にあり、意識と無意識を統合する、究極的な全体性を目指す元型です。人生の目標地点とも言えます。
- 人が「自分らしく生きる」とは、この自己(セルフ)を実現していく過程のことです。これを**「個性化の過程(Individuation)」**と呼びます。
【試験でのポイント】 ペルソナとシャドウは、キャリア相談の現場でよく見られる問題と直結するので、特に重要です。
ポイント3:あなたの心の利き手は?「タイプ論(性格類型論)」
ユングのタイプ論は、有名な性格検査**MBTI(マイヤーズ・ブリッグス・タイプ指標)**の元になった理論で、試験の最重要項目の一つです!
ユングは、人の心のエネルギーの方向(態度)と、情報の受け取り方・判断の仕方(機能)にパターンがあると考えました。
① 2つの態度(エネルギーの方向)
- 外向 (Extraversion):関心が外界の物事や人に向かう。
- 内向 (Introversion):関心が**自分の内面(考えや気持ち)**に向かう。
② 4つの機能(心の働き) 人はこの4つのうち、どれかをメイン(主機能)で使い、どれかが苦手(劣等機能)です。
- <合理機能(判断のしかた)>
- 思考 (Thinking):論理的に、客観的な正しさで判断する。「これは正しいか?」
- 感情 (Feeling):好きか嫌いか、人間関係や調和を大切にして判断する。「みんなが納得するか?」
- <非合理機能(情報の受け取り方)>
- 感覚 (Sensation):五感を使って、事実をありのままに捉える。「現実はどうなっているか?」
- 直観 (Intuition):物事の裏にある可能性や全体像をひらめきで捉える。「将来どうなるか?」
[ユングの8つのタイプ論を示す図。外向・内向の軸と、思考・感情・感覚・直観の4機能が組み合わさっている]
【キャリア相談での関連】
- クライエントがどのタイプかを理解することで、その人の**強み(主機能)や陥りやすい悩み(劣等機能)**が見えてきます。
- 例えば、「思考」が強い人は論理的な仕事が得意ですが、人間関係で悩むかもしれません。「感覚」が強い人は現実的な作業は得意ですが、将来のビジョンを描くのが苦手かもしれません。
- 適職探しや自己理解の大きなヒントになります。
ポイント4:人生の正午をどう生きるか「人生のライフサイクル」
ユングは人生を「朝」と「午後」に分けました。
- 人生の午前(~40歳頃まで)
- 社会に出て、キャリアを築き、家庭を持つなど、外的な世界で自分を確立していく時期。
- ペルソナをしっかりと形成し、社会に適応することがテーマです。
- 人生の正午(40歳頃)
- 人生の折り返し地点。いわゆる**「中年の危機」**が訪れやすい時期です。
- これまで追い求めてきたもの(地位、名誉、お金など)に疑問を感じ、「私の人生、これでよかったのか?」と問い直すようになります。
- 人生の午後(40歳頃~)
- 関心が内的な世界へと向かう時期。
- これまで無視してきた自分の内面(シャドウなど)と向き合い、自分とは何かを探求します。
- 自己(セルフ)の実現を目指し、より統合された自分になっていく「個性化の過程」が本格化します。
【キャリア相談での関連】
- 40~50代のクライエントが抱えるモヤモヤした悩みは、まさにこの「人生の正午」の問題であることが多いです。
- 単に「次の仕事を探す」だけでなく、「これからの人生で何を大切にしたいか」という、より深いレベルでの支援が求められます。ユングのこの視点は、ミドル・シニア層のキャリア支援に不可欠です。
まとめ:試験で思い出すべきユングのキーワード
| 理論の分類 | キーワード | キャリア相談との関連 |
|---|---|---|
| 心の構造 | 集合的無意識、元型 | 人間の普遍的な心のパターンを理解する |
| 元型 | ペルソナ、シャドウ、自己 | 仕事上の役割と本当の自分、隠れた才能、自己実現 |
| タイプ論 | 外向・内向、思考・感情・感覚・直観 | MBTIの基礎。自己理解、強み・弱みの把握、適職探索 |
| ライフサイクル | 人生の午前・午後、中年の危機 | 中高年のキャリア転換期における内面的な課題の理解 |
ユングの理論は、人の心を「全体」として捉え、生涯にわたる「自己実現(個性化)」の旅を応援するものです。これは、私たちキャリアコンサルタントがクライエントの人生に寄り添う上で、非常にパワフルな羅針盤となってくれます。
まずは、これらのキーワードと、それがキャリアのどんな場面と結びつくのかを、ふんわりとでも掴んでおけば大丈夫です。
講義は以上です。試験勉強、応援しています!

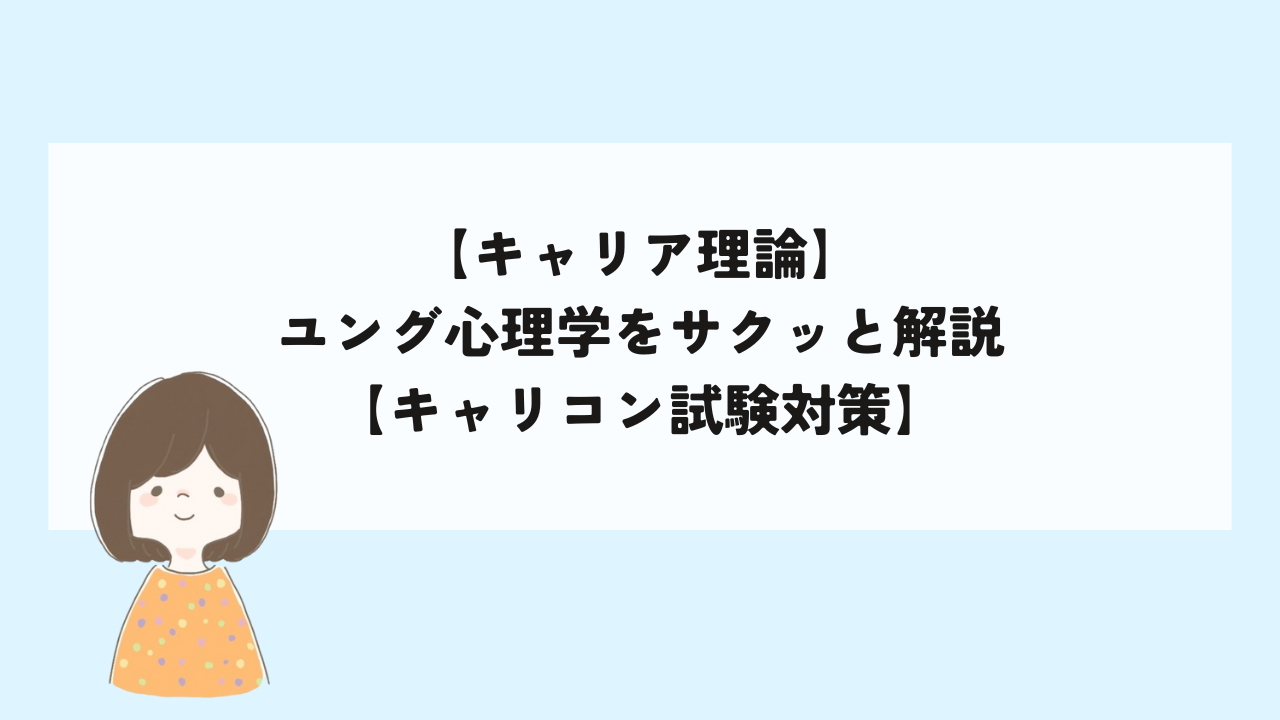

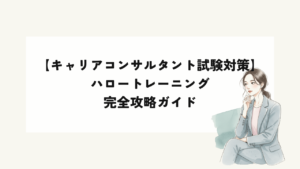

コメント