動機付け理論は、キャリアコンサルタント試験における必須知識であり、クライエントの「なぜやる気が出ないのか」「何がしたいのか」といった根本的な問いに答えるための強力なフレームワークです。
今回は、動機付け理論を「内容理論(What)」と「過程理論(How)」に分類し、各理論の核心と試験対策のポイント、そして実際のキャリアコンサルティング(キャリコン)現場での活用法を分かりやすく解説します。
解説
動機付け理論 徹底解説
動機付け理論の分類と重要性
 まい
まい動機付け理論は、人の行動を理解し、方向付け、持続させるために欠かせません。キャリアコンサルタントは、この理論を使いこなすことで、クライエントの自律的なキャリア形成を促すことができます。
学術的には、動機付け理論は以下の二つに分類されます。
- 内容理論(Content Theories):
- 「何が(What)」 人を動機付けるのか、その要因(欲求や動因)そのものに焦点を当てます。
- 理論例: マズロー、アルダファ、ハーズバーグ、マクレランドなど。
- 過程理論(Process Theories):
- 「どのように(How)」 動機付けが生まれ、行動として維持されるのか、その心理的プロセスに焦点を当てます。
- 理論例: ロック、アトキンソン、デシ、ハックマンなど。
キャリコンの実践では、まず内容理論で**「動機の源泉」を診断し、次いで過程理論で「具体的な介入や目標設定」を設計**するという二段階のアプローチが有効です。
動機付けの「内容理論」― 何が人を動かすのか
内容理論は、人の内面にある「欲求」を特定します。
1.1 マズローの欲求階層説
| 提唱者 | A. マズロー(Abraham Maslow) |
|---|---|
| 核心 | 人間の欲求は5つの階層をなし、低次の欲求が満たされると、高次の欲求が優位になる。 |
【5つの欲求階層】
- 生理的欲求:生命維持
- 安全の欲求:経済的安定、危険回避
- 社会的欲求:集団への所属、愛情
- 承認の欲求:他者からの尊敬、自己評価
- 自己実現の欲求:能力の最大限の発揮、成長
試験対策のポイント:
- 階層性と、満たされた低次欲求は動機付け要因になりにくいという不可逆性が原則です。
- 第1〜4段階を欠乏動機、第5段階を成長動機と呼ぶことも重要です。
1.2 アルダファのERG理論
| 提唱者 | C. アルダファ(Clayton Alderfer) |
|---|---|
| 核心 | マズロー理論を実証的に修正し、欲求を3つに集約。厳格な階層構造を柔軟にした。 |
【3つの欲求カテゴリー】
- 生存の欲求(E – Existence): 生理的・安全の欲求(賃金、労働環境など)。
- 関係の欲求(R – Relatedness): 社会的・承認の欲求の一部(人間関係、所属)。
- 成長の欲求(G – Growth): 承認の欲求の一部・自己実現の欲求(自己開発、創造的活動)。
試験対策のポイント:
- 欲求の並行性: 複数の欲求が同時に活性化することがある。
- 欲求の可逆性(Frustration-Regression): 高次の欲求(G)が満たされないと、その下の低次の欲求(R)をより強く求める「後戻り」現象が起こる。
- 例:成長機会がない人が、過度に職場の人間関係に固執する。
1.3 ハーズバーグの二要因理論(動機付け・衛生理論)
| 提唱者 | F. ハーズバーグ(Frederick Herzberg) |
|---|---|
| 核心 | 仕事の「満足」を引き起こす要因と、「不満足」を引き起こす要因は独立している。 |
【二つの独立した要因】
- 動機付け要因(Motivators): 充足されると満足につながる。仕事の内容に関連する内的な要因。
- 例:達成感、承認、仕事そのものへの興味、責任、成長。
- 衛生要因(Hygiene Factors): 不足すると不満につながるが、充足されても「不満がない」状態になるだけで、積極的な満足にはつながらない。仕事の環境に関連する外的な要因。
- 例:給与、労働条件、会社の経営方針、人間関係、監督。
試験対策のポイント:
- 非対称な関係: 満足の反対は「不満足でない状態」、不満の反対は「満足でない状態」ではない。
- *「給与(衛生要因)を上げても、積極的に仕事への満足度(動機付け)は高まらない」*ことを理解することが重要です。
1.4 マクレランドの達成動機理論
| 提唱者 | D. マクレランド(David McClelland) |
|---|---|
| 核心 | 動機は後天的に学習され、組織行動に影響を与える3つの主要動機がある。 |
【3つの主要動機】
- 達成欲求(nAch): 困難な目標を自力で達成したい欲求。
- 権力欲求(nPow): 他者に影響力を及ぼし、コントロールしたい欲求。
- 親和欲求(nAff): 他者と友好的な関係を築き、受け入れられたい欲求。



これらの3つの欲求に加え、失敗や困難な状況を避けようとする「回避欲求」が第四の動機として加えられることもあります
試験対策のポイント:
- 個人のキャリアパスや職務設計は、これらの欲求の強さに合わせて行うべきである。
- 達成欲求が高い人は、明確なフィードバックと挑戦的な目標が与えられる職務で能力を発揮しやすい。
第2部:動機付けの「過程理論」― どのようにやる気は生まれるのか
過程理論は、動機が行動につながる認知プロセスを解明します。
2.1 ロックの目標設定理論
| 提唱者 | E. ロック(Edwin Locke) |
|---|---|
| 核心 | 明確で挑戦的な目標を設定すること自体が、人のパフォーマンスを高める強力な動機付けとなる。 |
【効果的な目標の5つの要件】
- 明確性・具体性: 曖昧でなく測定可能であること。
- 困難度(挑戦的): 簡単すぎず、努力すれば手が届く難易度であること。
- 目標への関与(コミットメント): 本人が心から納得していること。
- フィードバック: 進捗状況を定期的に把握できること。
- タスクの複雑性: 複雑な場合は中間目標に落とし込むこと。
試験対策のポイント:
- 目標管理のフレームワークであるSMART原則(Specific, Measurable, Achievable/Aggressive, Relevant, Time-bound)と親和性が高い。
2.2 アトキンソンの達成動機理論
| 提唱者 | J. アトキンソン(John Atkinson) |
|---|---|
| 核心 | 行動は、「成功を追求したい動機」と「失敗を避けたい動機」の葛藤によって決定される。 |
動機付けの強さ(数式): $$\text{達成動機} = \text{成功動機} – \text{失敗回避動機}$$
試験対策のポイント:
- 成功動機が強い人は、自身の能力を試せる成功確率50%程度の適度に挑戦的な課題を最も好む。
- 失敗回避動機が強い人は、失敗の言い訳ができる簡単な課題か極端に難しい課題を選ぶ傾向がある。
2.3 デシの内発的動機付け理論(自己決定理論)
| 提唱者 | E. デシ & R. ライアン(Deci & Ryan) |
|---|---|
| 核心 | 持続的なパフォーマンスには、活動そのものから得られる楽しさに基づく内発的動機付けが重要である。 |
【重要概念】
- 内発的動機付け: 行動そのものが目的(興味、楽しさ、充実感)。
- 外発的動機付け: 外部の報酬を得るための手段(報酬、評価、罰の回避)。
- アンダーマイニング効果: 内発的に好きでやっていた活動に外的な報酬(特に金銭)を与えると、かえって自発的な意欲が低下する現象。
【3つの基本的心理欲求】 内発的動機付けを高めるための普遍的な3つの欲求。
- 自律性(Autonomy): 自分で決定したいという欲求。
- 有能感(Competence): 能力を発揮し、課題を乗り越えたいという欲求。
- 関係性(Relatedness): 他者と良好な関係を築き、貢献したいという欲求。
試験対策のポイント:
- 「アンダーマイニング効果」は最重要キーワード。
- 3つの基本的心理欲求を満たす環境を整備することが、キャリコン支援の根幹となる。
2.4 ハックマンの職務特性モデル
| 提唱者 | R. ハックマン & G. オルダム(Hackman & Oldham) |
|---|---|
| 核心 | 職務(仕事)そのものの特性を設計(ジョブデザイン)することで、内発的動機付けを高める。 |
【モデルのプロセス】 5つの中核的職務特性 $\rightarrow$ 3つの重要な心理状態 $\rightarrow$ 成果
【5つの中核的職務特性】
- 技能多様性(Skill Variety): 多様なスキルが求められる度合い。
- タスク完結性(Task Identity): 仕事の始めから終わりまで一連のまとまりとして関与できる度合い。
- タスク重要性(Task Significance): 仕事が他者や社会に影響を与えると感じる度合い。
- 自律性(Autonomy): 仕事の進め方を自分で決められる自由度の高さ。
- フィードバック(Feedback): 成果に関する明確な情報を得られる度合い。
試験対策のポイント:
- 上記5つの特性が、働く人に「仕事の有意味感(1〜3)」「結果への責任感(4)」「成果に関する知識(5)」という3つの心理状態を生み出し、最終的な成果(高い動機付け、満足度、業績)につながるという因果関係の流れを理解する。
第3部:キャリアコンサルティングへの応用と理論の統合
動機付け理論は、キャリコンの実践においてクライエントの課題を診断し、介入策を立案するための「ツールキット」となります。
実践における活用事例
| クライエントの課題 | 活用する理論 | 診断・介入の視点 |
|---|---|---|
| 「給料に不満はないが、やる気が出ない」 | ハーズバーグ | 衛生要因は充足されているが、動機付け要因(達成、承認、成長)が欠けているのではないか? |
| 漠然とした不安で目標が立てられない | ロックの目標設定理論 | SMART原則に基づき、クライエントがコミットできる具体的で挑戦的な短期・中期目標を設定する。 |
| 「仕事が単調でつまらない」 | ハックマンの職務特性モデル | 5つの特性をチェックリストとし、「自律性」や「技能多様性」を高めるためのジョブ・クラフティングを支援する。 |
| 転職で外発的要因(年収)ばかりに囚われる | デシの自己決定理論 | 3つの基本的心理欲求(自律性・有能感・関係性)に焦点を当て、内発的な価値観や「本当にしたいこと」を探求する。 |
理論の統合的理解: 過程理論のデシ、ロック、ハックマンの知見は相互補完的です。デシが内発的動機付けの源泉(自律性、有能感)を特定し、ハックマンがそれを職場で満たすための具体的な職務設計を提案し、ロックが行動を促すための目標設定方法を提供する、という流れで捉えると、より体系的な支援計画を立てることができます。
この知識を武器に、試験合格と、クライエントの心に火をつけるコンサルティングを目指してください。


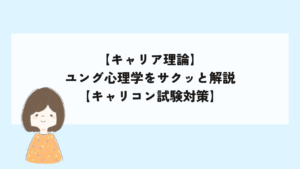

コメント