キャリアコンサルタントとして、企業の労働環境やダイバーシティ推進への取り組みを把握しておくことは非常に重要です。特に、厚生労働省が管轄する「くるみん」「えるぼし」といった認定制度は、少子高齢化や働き方の多様化といった社会背景から生まれたものであり、企業の働きやすさを客観的に示す指標として試験でも頻出のテーマです。
 まい
まいここでは、主要な認定制度の目的、根拠法、認定基準、そして企業や労働者にとってのメリットを詳しく解説します。
概要
くるみん認定
仕事と「子育て」の両立
赤ちゃんが「おくるみ」に優しく包まれている様子が名称の由来。子育てをサポートする企業を認定します。
主な認定基準
- 男性の育休取得率: 10%以上
- 女性の育休取得率: 75%以上
- 所定外労働の削減措置
- 月平均残業時間: 45時間未満
企業側のメリット
- マーク使用による企業イメージ向上
- 公共調達での加点評価
- 日本政策金融公庫による低利融資
えるぼし認定
「女性の活躍」の推進
「Lady」の『L』と「星」を組み合わせた名称。女性の活躍推進が優良な企業を認定します。
5つの評価項目
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等の働き方
- 管理職比率
- 多様なキャリアコース
企業側のメリット
- 企業イメージ向上、人材確保
- 公共調達や補助金で有利に
ユースエール認定
「若者の採用・育成」
若者を応援(エール)する、雇用管理が優良な**中小企業**を認定します。
主な認定基準
- 新卒者等の離職率: 20%以下
- 月平均残業時間: 20時間以下
- 有給取得率: 70%以上
- 育休取得実績が男女ともにいること
企業側のメリット
- ハローワーク等で重点的にPR
- 助成金の加算
- 低利融資の対象
ともにん認定
仕事と「介護」の両立
「仕事と介護を**ともに**両立できる職場」をイメージ。介護離職の防止に取り組む企業を認定します。
主な認定基準
- 男女ともに介護休業の取得実績
- 法定を上回る両立支援制度
- 研修の実施や相談窓口の設置
企業側のメリット
- 従業員が安心して長く働ける企業PR
- 介護離職による人材流出を防止
各制度のまとめ
| 認定名称 | 支援の対象 | 根拠法 |
|---|---|---|
| くるみん | 子育て | 次世代育成支援対策推進法 |
| えるぼし | 女性活躍 | 女性活躍推進法 |
| ユースエール | 若者雇用 | 若者雇用促進法 |
| ともにん | 介護 | 育児・介護休業法 |
なぜキャリアコンサルタントに重要か?
求職者への支援
客観的な「働きやすさ」の指標として提示でき、特にライフイベントを見据えた相談者に有効な情報となる。
企業への支援
採用・定着に悩む企業へ、認定取得を目標とした人事制度改善のコンサルティングが可能になる。
在職者への支援
認定企業の従業員に対し、活用できていない社内制度の利用を後押しし、キャリア継続に貢献できる。
解説
1. くるみん認定・プラチナくるみん認定:仕事と「子育て」の両立
赤ちゃんが「おくるみ」に優しく包まれている様子が名称の由来。仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む「子育てサポート企業」を認定する制度です。
- 目的: 仕事と子育ての両立支援を推進し、次世代の育成支援に貢献すること。
- 根拠法: 次世代育成支援対策推進法
- 認定機関: 厚生労働大臣(都道府県労働局へ委任)
認定の種類と主な基準
一般事業主行動計画を策定・届出し、その計画目標を達成するなどの一定の要件を満たすことで認定されます。
| 認定の種類 | 主な認定基準(一部抜粋) |
| くるみん認定 | ・男性の育児休業等取得率が10%以上。・女性の育児休業等取得率が75%以上。・3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための所定外労働の削減、短時間勤務制度等の措置を講じていること。・フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。 |
| プラチナくるみん認定 | ・くるみん認定を既に受けていること。・男性の育児休業等取得率が30%以上。・女性の育児休業等取得率が75%以上。・子の看護休暇制度や、育児・介護休業法を上回る水準の育児短時間勤務制度など、より高い水準の取り組みを行っていること。 |
| トライくるみん認定 | 2022年4月から新設。くるみんの認定基準が引き上げられたことに伴う経過措置的な位置づけ。 |
【企業側のメリット】
- 認定マークを商品や広告、求人情報に使用でき、企業のイメージアップや優秀な人材の確保・定着に繋がる。
- 日本政策金融公庫による低利融資の対象となる。
- 公共調達において加点評価される場合がある。
2. えるぼし認定・プラチナえるぼし認定:女性の活躍推進
「Lady(女性)」「Labor(労働)」の『L』と、評価が高いことを示す「星」を組み合わせた名称。女性の活躍推進に関する状況が優良な企業を認定する制度です。
- 目的: 企業における女性の活躍を推進し、ジェンダー平等の実現を目指すこと。
- 根拠法: 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)
- 認定機関: 厚生労働大臣(都道府県労働局へ委任)
認定の段階と評価項目
以下の5つの評価項目について、基準を満たした数に応じて3段階で認定されます。
- 採用: 男女別の採用における競争倍率が同程度であること。
- 継続就業: 「女性労働者の平均継続勤務年数 ÷ 男性労働者の平均継続勤務年数」が7割以上など。
- 労働時間等の働き方: 法定時間外労働と法定休日労働時間の合計の平均が、各月45時間未満であること。
- 管理職比率: 管理職に占める女性労働者の割合が、産業ごとの平均値以上であることなど。
- 多様なキャリアコース: 直近3事業年度で、女性の非正社員から正社員への転換などの実績があること。
| 認定段階 | 基準を満たした項目数 |
| 1段階目 | 上記項目のうち1〜2つの基準を満たす |
| 2段階目 | 上記項目のうち3〜4つの基準を満たす |
| 3段階目 | 上記項目のうち5つ全ての基準を満たす |
| プラチナえるぼし | えるぼし認定企業のうち、より長期間にわたる取り組み実績など、さらに高い水準の要件を満たした場合に認定。 |
【企業側のメリット】
- くるみん同様、認定マークの使用による企業イメージの向上、人材確保に繋がる。
- 公共調達や各種補助金などで有利になることがある。
3. ユースエール認定:若者の採用・育成
若者を応援(エール)する企業、という意味。若者の採用・育成に積極的で、雇用管理が優良な中小企業を認定する制度です。大企業は対象外という点がポイントです。
- 目的: 中小企業の人材確保を支援し、若者の安定的な雇用と育成を促進すること。
- 根拠法: 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)
- 認定機関: 厚生労働大臣(都道府県労働局へ委任)
- 主な認定基準(一部抜粋):
- 新卒者等の離職率が20%以下
- 正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下
- 正社員の有給休暇の年間取得率が70%以上
- 育児休業の取得実績が男女ともにいること
【企業側のメリット】
- ハローワーク等で重点的にPRされる。
- 若者雇用促進法に基づく助成金(キャリアアップ助成金など)が加算される。
- 認定マークの使用、日本政策金融公公庫の低利融資など。
4. ともにん認定:仕事と「介護」の両立
「仕事と介護をともに両立できる職場」をイメージした名称。介護離職の防止という社会課題に対し、仕事と介護の両立支援に取り組む企業を認定する制度です。
- 目的: 介護による離職を防止し、働きながら介護を行える職場環境の整備を促進すること。
- 根拠法: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)
- 認定機関: 厚生労働大臣(都道府県労働局へ委任)
- 主な認定基準(一部抜粋):
- 過去3年間で、介護休業の取得者が男女それぞれ1人以上いること。
- 育児・介護休業法を上回る介護のための短時間勤務制度など、両立支援のための制度を設けていること。
- 介護に関する研修の実施や相談窓口の設置など、労働者への支援を行っていること。
【企業側のメリット】
- 認定マークの使用により、従業員が安心して長く働ける企業であることをアピールできる。
- 介護離職による人材流出を防ぎ、経験豊富な従業員の定着を図れる。
5. 各制度のまとめ
| 認定名称 | 愛称の由来 | 支援の対象 | 根拠法 |
| くるみん | おくるみ | 子育て | 次世代育成支援対策推進法 |
| えるぼし | L(Lady)+星 | 女性活躍 | 女性活躍推進法 |
| ユースエール | Youth+エール | 若者雇用 | 若者雇用促進法 |
| ともにん | 共に両立 | 介護 | 育児・介護休業法 |
6. なぜキャリアコンサルタントに重要か?
これらの認定制度は、クライエント(相談者)や企業に対して、客観的な情報に基づいて具体的かつ説得力のある支援を行うための重要な知識となります。
- 求職者への支援: 求人票の文字情報だけでは分からない「企業の風土」や「働きやすさへの姿勢」を伝える材料となる。特にライフイベントを見据えたキャリアプランを考える相談者には、重要な企業選択の軸となり得る。
- 企業への支援: 採用難や従業員の定着に悩む企業に対し、認定取得を具体的な目標として設定し、人事制度の改善や職場環境整備のコンサルティングを行うことができる。これは企業の持続的成長に繋がる本質的な支援となる。
- 在職者への支援: 認定企業で働く相談者が、社内制度を十分に活用できていないケースは少なくない。キャリアコンサルタントとして制度の存在を伝え、利用を後押しすることで、相談者のワークライフバランス改善やキャリア継続に貢献できる。


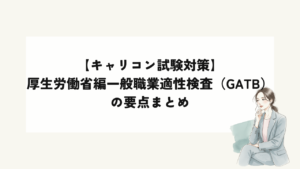
コメント