 チャチャ
チャチャキャリアコンサルティングって心理学の知識が必要だよね。いろんな心理療法、理論があって混乱しちゃう。



さまざまな心理療法を、提唱者とキーワードとともに整理しよう!
キャリアコンサルタント試験対策:主要な心理療法・カウンセリング理論のまとめ
| 理論/アプローチ名 | 主な提唱者 | 理論の要点・キーワード |
| 精神分析療法 | S. フロイト | ・人間の行動や感情は無意識の影響を受けると考える。 ・自由連想法や夢分析を用いて、抑圧された感情や欲求を意識化させる。 ・キーワード:リビドー、エディプス・コンプレックス、抵抗、転移 |
| 個人心理学 | A. アドラー | ・人間の行動は目標によって方向づけられると考える(目的論)。 ・劣等感を克服し、他者と協力して生きる共同体感覚を重視する。 ・キーワード:ライフスタイル、課題の分離、勇気づけ |
| 分析心理学 | C. G. ユング | ・意識と無意識のバランスを取り、自己実現を目指す(個性化の過程)。 ・個人的無意識の奥に、人類共通の集合的無意識や元型(アーキタイプ)が存在するとした。 ・キーワード:内向/外向、コンプレックス、中年期の危機 |
| 来談者中心療法 | C. ロジャーズ | ・人間には自ら成長し、問題を解決する力が備わっている(自己実現傾向)と信頼する。 ・カウンセラーの3条件(自己一致、無条件の肯定的関心、共感的理解)が重要。 ・キーワード:傾聴、非指示的、自己概念 |
| 行動療法 | J. ウォルピ、B. F. スキナー | ・問題行動は学習理論(古典的/オペラント条件づけ)によって後天的に学習されたものと捉える。 ・具体的な行動の変容に焦点を当て、望ましい行動を強化する。 ・キーワード:系統的脱感作法、モデリング、トークン・エコノミー |
| 認知行動療法 | A. T. ベック、A. エリス | ・出来事の捉え方(認知)が感情や行動に影響すると考える。 ・非現実的・非適応的な認知(自動思考、スキーマ)を特定し、修正することを目指す。 ・論理療法(REBT):エリスが提唱。ABC理論に基づき、非合理的な信念(イラショナル・ビリーフ)に働きかける。 |
| ゲシュタルト療法 | F. S. パールズ | ・「今、ここ」での体験や気づきを重視する。 ・未解決な問題や感情(未完結なゲシュタルト)に気づき、統合することで全体性を回復する。 ・キーワード:エンプティ・チェア(空の椅子)、アウェアネス |
| 現実療法 | W. グラッサー | ・5つの基本的欲求(生存、愛・所属、力、自由、楽しみ)を満たすために、人間は自ら行動を選択していると考える。 ・過去の原因追求ではなく、現在の行動と未来の計画に焦点を当てる。 ・キーワード:選択理論、上質世界 |
| 交流分析 | E. バーン | ・自我状態をP(親)、A(大人)、C(子供)の3つに分類し、自己分析や他者との交流を理解する。 ・対人関係における不毛なやり取り(ゲーム)や、無意識に作られた人生設計図(人生脚本)を分析する。 ・キーワード:ストローク、ディスカウント |
| ナラティブ・アプローチ | M. ホワイト、D. エプストン | ・人は自らの経験を物語(ナラティブ)として意味づけて生きていると考える。 ・問題をその人から切り離し(外在化)、支配的な物語を書き換え、新しい物語を共同で創造していく。 ・キーワード:ドミナント・ストーリー、オルタナティブ・ストーリー |
| ソリューション・フォーカスト・アプローチ(解決志向アプローチ) | S. ド・シェイザー、I. K. バーグ | ・問題の原因ではなく、解決(ソリューション)に焦点を当てる。 ・クライエントが既に持っている力や成功体験(例外)を見つけ、未来志向で対話を進める。 ・キーワード:ミラクル・クエスチョン、スケーリング・クエスチョン |
心理療法について詳しくみていこう!
精神分析療法(フロイト)
「自分でも気づいていない『心の奥底』を探る旅」
これは、人の心には自分でも気づいていない「無意識」という領域が、海に浮かぶ氷山のように、見えている部分よりずっと大きく存在している、と考える方法です。
例えば、なぜか分からないけど特定の人が苦手だったり、同じ失敗を繰り返してしまったり…。それは、心の奥底にある「無意識」が影響しているのかもしれません。
この療法では、カウンセラーと自由に話をしたり(自由連想法)、見た夢の内容を分析したり(夢分析)して、自分でも気づかなかった本心や過去の経験を探っていきます。自分の心の謎を解き明かす冒険のようなイメージですね。
2. 個人心理学(アドラー)
「“未来の目標”が、今の君を動かしている!」
「トラウマがあるから、前に進めない…」と考えるのがフロイトなら、「未来にこうなりたい、という目標があるから、今は前に進まない選択をしている」と考えるのがアドラーです。
これを目的論といいます。 例えば、「人見知りだから友達ができない」のではなく、「人と関わって傷つきたくない、という目的があるから、人見知りという性格を使っている」と考えるんです。
誰にでもある「劣等感」は、悪いものではなくて、もっと良くなりたい!というバネになると考えます。そして、周りの人と協力する気持ち(共同体感覚)を持つことで、人は幸せになれると教えてくれます。
3. 分析心理学(ユング)
「君の心は、人類の歴史とつながっている」
ユングもフロイトと同じように「無意識」を大切にしましたが、さらにその奥に、人類みんなが共通して持っている「集合的無意識」というものがあると考えました。 世界中の神話やおとぎ話に「ヒーロー」や「賢いおじいさん」のような似たキャラクターが出てくるのは、この集合的無意識の中に共通のイメージ(元型)があるからだと考えたのです。 自分の意識と、個人的・集合的な無意識のバランスをとって、自分らしい自分(自己実現)になっていくことを目指します。心の探検が、人類の歴史にまで広がる壮大なイメージです。
4. 来談者中心療法(ロジャーズ)
「答えは、すべて君の中にある」
この考え方の基本は、「人は誰でも、自分の中に成長していく力を持っている」という信頼です。 植物の種が、水や太陽があれば自然に芽を出して育っていくように、人も「安心できる環境」さえあれば、自分で問題の答えを見つけて成長できると考えます。
カウンセラーは、アドバイスをするのではなく、ただひたすら相手の話を聴き(傾聴)、どんな話も否定せず(無条件の肯定的関心)、相手の気持ちを自分のことのように理解しようとします(共感的理解)。
カウンセラーという「安全な鏡」に自分を映し出すことで、自分で答えを見つけていくのを手伝う方法です。
5. 行動療法(ウォルピ、スキナー)
「苦手なことも、練習すれば変えられる!」
これは、私たちの悩みや問題行動は、「習慣」や「学習」によって身についたものだと考える、とてもシンプルな方法です。
例えば、「犬が怖い」という悩みは、過去に犬に吠えられた経験から「犬=怖い」と学習してしまった結果だと考えます。 なので、その逆の学習をすればいい!というのがこの療法の考え方。
まずは犬の写真をみて、次に遠くから本物の犬を見て、少しずつ慣れていく(系統的脱感作法)。このように、行動をステップ・バイ・ステップで変えていくトレーニングのようなイメージです。
6. 認知行動療法(ベック、エリス)
「出来事を変えるのは難しい。でも『考え方』は変えられる」
何かイヤなことがあった時、気分が落ち込むのは、その「出来事」のせいだけじゃない。その出来事をどう「解釈した(考えた)か」が原因だ、と考えます。これを認知と言います。
例えば、友達からLINEの返信が来なかった(出来事)とします。 A君:「嫌われたかも…」→ 不安になる B君:「忙しいのかな?」→ 特に気にしない このように、考え方のクセ(自動思考)を見つけて、それをより楽になる考え方に変えていく練習をします。心の筋トレのようなイメージですね。
7. ゲシュタルト療法(パールズ)
「『今、ここ』の自分に、全身で気づいてみよう」
「あの時こうすれば良かった…」「将来が不安だ…」と、過去や未来に心がとらわれていると、今の自分を生きられなくなってしまいます。 この療法は、「今、ここ」で感じている気持ちや体の感覚に、とにかく集中することを目指します。
例えば、誰も座っていない椅子(エンプティ・チェア)に、普段言いたいけど言えない相手がいると想像して話しかけてみる、といったユニークな方法を使います。頭で考えるだけでなく、体験を通して心と体の声に気づき、スッキリさせることを目指します。
8. 現実療法(グラッサー)
「過去は変えられない。でも、今の行動と未来は選べる」
「なぜそうなったのか」という過去の原因を探るより、「これからどうしたいのか」という未来の目標に焦点を当てます。 そして、その目標を達成するために、「今、自分にできることは何か?」という具体的な行動を自分で選択していくことを手伝います。
私たちには「愛・所属」や「楽しみ」など5つの基本的な欲求があり、それを満たすために行動を選んでいると考えます。自分の人生のハンドルは、他の誰でもなく、自分が握っているんだ!と気づかせてくれる、パワフルなアプローチです。
9. 交流分析(バーン)
「自分の中にいる『親・大人・子ども』と仲良くなろう」
私たちの心の中には、親のように厳しくも優しい「P(親)」、冷静に物事を判断する「A(大人)」、子どものように自由に感情を表現する「C(子ども)」という3つの自分がいる、と考えます。
人とのコミュニケーションがうまくいかない時は、この3人のうち、どの自分が出てきているのかを分析します。例えば、相手が「A(大人)」で冷静に話しているのに、自分が「C(子ども)」で感情的になってしまうと、会話がすれ違ってしまいます。
自分や相手の心の状態を理解することで、よりスムーズな人間関係を築くことを目指す、自己分析ツールのような心理学です。
10. ナラティブ・アプローチ(ホワイト、エプストン)
「君は、君の人生という物語の『主人公』だ!」
これは、私たちの人生を一本の「物語(ナラティブ)」として捉える考え方です。 悩みがある時、私たちは「自分はダメな人間だ」というような、つらくてネガティブな物語に支配されがちです。これを「ドミナント・ストーリー(支配的な物語)」と呼びます。
このアプローチでは、まず「君がダメなんじゃない。君を苦しめている『問題』が悪いんだ」というように、問題と本人を切り離して考えます(外在化)。 例えば、「私は引っ込み思案だ」ではなく、「『引っ込み思案』というヤツが、あなたを支配しようとしている」と捉え直すんです。
そしてカウンセラーと一緒に、「でも、あの時は少しだけ積極的になれたな」「実はこんな良いところもあるな」といった、支配的な物語とは違う、ポジティブな側面や出来事を探していきます。そうやって、これからの人生について、**新しい希望の持てる物語(オルタナティブ・ストーリー)**を一緒に創り上げていく。君が自分の人生の作者になるのを手伝う、というイメージのアプローチです。
11. ソリューション・フォーカスト・アプローチ(シェイザー、バーグ)
「『問題』じゃなくて、『解決した未来』にピントを合わせよう!」
これは、その名の通り、問題の「原因」を掘り下げるのではなく、どうなったら「解決」なのか、その未来像に焦点を当てる、とても前向きでシンプルなアプローチです。 車がパンクした時に、「なぜパンクしたんだろう?」と原因をずっと考えるより、「どうすればスペアタイヤに交換できるか?」と解決策を考える方が早い、という考え方に似ています。
そのために、こんなユニークな質問を使います。
- ミラクル・クエスチョン:「もし夜寝て、朝起きたら、すべての問題が奇跡のように解決していたとしたら、何がどう変わっていますか?」 → これで、自分が本当に望んでいる「ゴールの姿」がハッキリします。
- 例外探しの質問:「問題がなかった時、少しでもマシだった時はありますか?その時は何が違いましたか?」 → これで、自分の中にすでに解決のヒントや力があることに気づけます。
- スケーリング・クエスチョン:「最悪を0点、奇跡の状態を10点とすると、今は何点くらいですか?1点上げるには、何をすればいいでしょう?」 → これで、大きな目標を達成するための、小さな一歩が見えてきます。
過去の原因探しではなく、未来と、今できることに焦点を当てる、希望を見つけるためのアプローチです。



心理療法について主要なポイントを押さえて得点源につなげよう!



さらっとでも見ておくと試験で慌てないね。

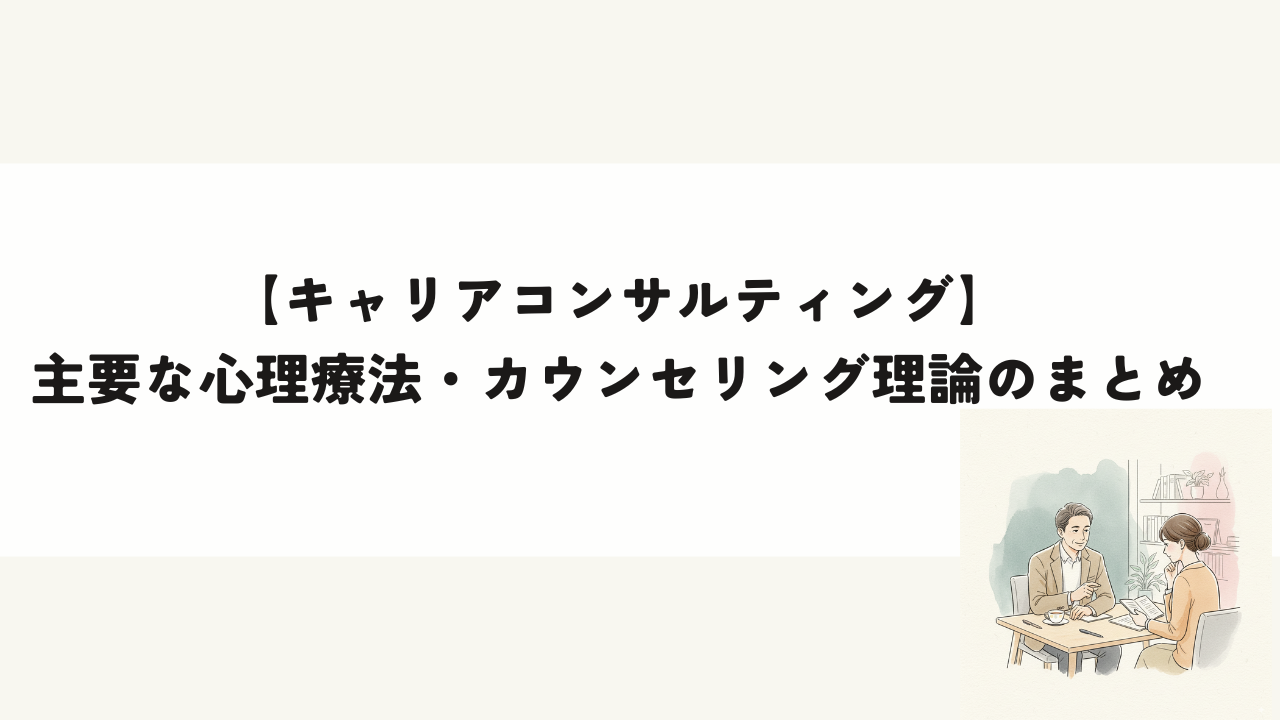
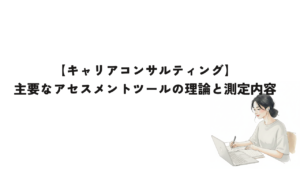
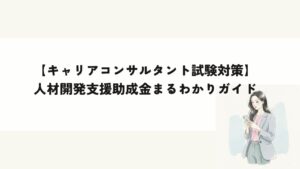

コメント