キャリアコンサルタントの実技試験は、どちらの団体で受験しても「相談者に寄り添い、その人らしいキャリア形成を支援する」という本質は同じです。しかし、そのアプローチや面談で重視する点に、それぞれの団体の思想が反映されています。
このガイドでは、キャリアコンサルティング協議会(以下、協議会)と日本キャリア開発協会(以下、JCDA)それぞれの特徴を深く掘り下げ、口頭試問で評価されやすいポイントを徹底的に解説します。
第1部:キャリアコンサルティング協議会(CCC)編

協議会が重視する視点:「問題解決」と「構造的な面談」
協議会の面談は、「相談者が抱える問題を明確にし、解決に向けた具体的な行動を支援する」というプロセスを重視する傾向があります。評価の際には、行き当たりばったりではなく、論理的で構造化された面談ができているかどうかが見られます。
信頼関係の構築 → 問題の把握 → 目標の設定 → 方策の実行
相談者のパートナーとして、問題解決のプロセスをリードし、具体的な情報提供やツールの活用も視野に入れた支援を行う。
評価区分の理解と口頭試問への活かし方
協議会の評価区分は「態度」「展開」「自己評価」の3つです。口頭試問は、特に「展開」と「自己評価」の能力をアピールする絶好の機会です。
- 態度: 基本的な傾聴姿勢。ロープレで見られます。
- 展開: 面談を構造的に進め、問題把握から目標設定、具体的方策まで導けているか。
- 自己評価: 自分の面談を客観的に振り返り、意図や課題を説明できるか。
【協議会向け】口頭試問・回答のポイント(最新傾向版)
質問1:「今回の面談で、良かった点と悪かった点は何ですか?」
(※「振り返っていかがでしたか?」と、まとめて聞かれることもあります)
- ポイント: 面談の「構造」と「意図」を明確に言語化すること。 なぜその質問をしたのか、その結果どうなったかをセットで答えるのが重要です。
- 良い回答例(良かった点): 「相談者が複数の悩みを話され、混乱しているご様子でしたので、『関係構築』の段階でまずはお気持ちを受け止めつつ、『問題把握』に進むために『一番気になっていることは何ですか?』と問いかけました。その結果、相談者がご自身の課題に優先順位をつけるきっかけとなり、面談の焦点を絞ることができた点が良かった点です。」
- 良い回答例(悪かった点): 「相談者の問題を見立てた後、その問題を解決するための具体的な目標設定について、相談者と共有・合意形成するプロセスが不十分でした。私の見立てを伝えるだけでなく、相談者ご自身が『それを目標としたい』と思えるような働きかけが課題です。」
質問2:「相談者は何を一番伝えたかったと思われますか?(主訴)」
- ポイント: 事実+感情+どうしたいか(Want)の3点セットで捉えること。相談者の言葉の奥にある「なりたい姿」や「理想の状態」まで踏み込みます。
- 良い回答例: 「上司との関係に悩んでいるという状況(事実)の裏にある、正当に評価されず悔しい(感情)というお気持ち、そして**『この先、今の会社で自分の能力を正当に評価され、やりがいを持って働き続けるにはどうすればいいか』を知りたい**、という点が最も伝えたかったことだと捉えました。」
質問3:「キャリアコンサルタントとして捉えた相談者の問題は何ですか?(見立て)」
- ポイント: 主訴の実現を「阻害している要因」を専門用語で指摘すること。 なぜその問題が、この相談者の主訴の実現を妨げているのか、という繋がりを明確に説明します。
- 良い回答例: 「『やりがいを持って働きたい』というお気持ちがありながら、その実現を阻んでいる要因として、ご自身の強みや周囲から評価されている点を客観的に認識できていない『自己理解の不足』と、その強みを活かせる社内でのキャリアパスや選択肢を知らない『仕事理解の不足』、この2点が問題であると捉えました。」
質問4:「この後、面談をどのように進めていきたいですか?(今後の展開)」
- ポイント: 見立てた「問題」を解決するための具体的な計画を提示すること。 前の質問で答えた「見立て」と、ここでの「展開」に一貫性があることが絶対条件です。
- 良い回答例: 「まず、先ほど捉えた『自己理解の不足』という問題を相談者と共有し、今後の支援目標として合意形成を図ります。その上で、具体的な方策としてジョブ・カードなどを活用し、過去の成功体験を振り返ることで強みや価値観を言語化する作業をご一緒し、自己理解を深めるご支援を計画します。それが、相談者の『やりがいを持って働く』という目標に繋がると考えます。」
ケース別】良い回答例
ここからは、ロープレで想定される様々な相談者ケースについて、4つの質問に対する回答例を具体的にご紹介します。
ケース1:非正規雇用で、正社員を目指したい30代相談者
- 良かった点・悪かった点:
- (良かった点): 「将来への漠然とした不安を訴えられたため、まずはそのお気持ちに寄り添い、受容・共感的な態度で丁寧にお話を伺うことに注力しました。結果として、安心して話せる関係性が構築でき、スキルへの自信のなさといった、より具体的なお悩みをお話しいただけた点が良かったです。」
- (悪かった点): 「相談者が『スキルがない』と繰り返された際に、その言葉をそのまま受け止めてしまい、これまでのご経験を具体的に深掘りする問いかけが不足していました。結果として、相談者自身も気づいていない強みや能力を明確にする段階まで至らなかった点が課題です。」
- 主訴: 「契約社員として働く中で将来への不安(感情)を感じており、安定した正社員になりたいが、自分にどんな可能性があるのか分からず、具体的な一歩をどう踏み出せばいいか知りたい(Want)、という点が主訴だと捉えました。」
- 見立て: 「正社員になりたいという目標の実現を阻んでいる要因として、これまでの業務経験で培ったポータブルスキルを客観的に認識できていない**『自己理解の不足』と、正社員としてどのような能力が求められるかという『仕事理解の不足』**が問題であると捉えました。」
- 今後の展開: 「まず、『ご自身の強みを明確にし、それを活かせる仕事を探す』ことを今後の目標として共有します。その上で、職務経歴の棚卸しを行い、成功体験や工夫した点を具体的に伺うことで、相談者ご自身の強みを言語化する支援をします。併せて、ハローワークの求人情報などを一緒に見ながら、企業が求めるスキルとの接続を図っていきたいです。」
ケース2:キャリアの停滞感に悩む40代の中堅社員
- 良かった点・悪かった点:
- (良かった点): 「『このままでいいのか』という焦りと諦めが入り混じった複雑なお気持ちを話された際に、急いで解決策を提示せず、『〇〇さんは、そう感じていらっしゃるのですね』と、感情の言葉を丁寧に返すことで、ご自身の気持ちを整理する時間を確保できた点が良かったと思います。」
- (悪かった点): 「面談の後半で、私自身が『何か新しい目標を見つけなければ』と焦ってしまい、少し誘導的な質問をしてしまいました。相談者自身の内発的な動機を待つ姿勢が不十分だった点が課題です。」
- 主訴: 「長年同じ業務を続ける中で、成長実感を得られず張り合いがない(感情)と感じており、この先のキャリアをどう描けばいいのか、意欲を取り戻すきっかけが欲しい(Want)、という点が主訴だと捉えました。」
- 見立て: 「意欲の低下の背景には、これまでの経験で培った強みや専門性を、環境の変化に合わせてどう活かしていくかという視点が持てていない『自己理解の不足』と、役割の拡大や後進育成といった、今後のキャリアの選択肢に関する『仕事理解の不足』が問題であると捉えました。」
- 今後の展開: 「まず、これまでのキャリアを振り返り、ご自身の強みや価値観を再確認することを目標として設定します。その上で、キャリア・アンカーなどのツールも参考にしながら、仕事において何を大切にしたいのかを明確にする支援を行います。その軸が見えた上で、社内公募制度や、管理職としての役割など、今後の具体的な選択肢について情報提供を行いたいです。」
ケース3:入社3年目、仕事のミスマッチで退職を考える若手社員
- 良かった点・悪かった点:
- (良かった点): 「『もう辞めたい』という強い言葉の裏にある、期待と現実のギャップへの戸惑いや、誰にも相談できない孤独感に焦点を当てて傾聴しました。その結果、相談者が徐々に落ち着きを取り戻し、ご自身の状況を客観的に話せるようになった点が良かった点です。」
- (悪かった点): 「退職したい理由を伺う中で、会社の制度や人間関係といった環境要因に話が集中してしまいました。相談者自身が仕事に何を求めているのか、どういう時にやりがいを感じるのかといった、内面を深掘りする関わりが不足していた点が課題です。」
- 主訴: 「希望して入社したはずの会社で、思い描いていた仕事ができず、失望感や焦り(感情)を感じており、このまま働き続けるべきか、あるいは転職すべきか、判断軸が持てず悩んでいる(Want)、という点が主訴だと捉えました。」
- 見立て: 「退職という意思決定ができない根本的な要因として、ご自身が仕事に求める価値観や興味の方向性が明確になっていない『自己理解の不足』と、安易な転職のリスクや、現職での異動の可能性といった選択肢を十分に検討できていない『意思決定における問題』があると捉えました。」
- 今後の展開: 「まず、『ご自身が納得できる意思決定をするために、判断の軸を明確にする』ことを目標として共有します。その上で、まずは現職のメリット・デメリット、そして転職した場合のメリット・デメリットを書き出し、客観的に比較検討するご支援をします。併せて、ご自身の興味や価値観を探るために、VPI職業興味検査などのアセスメントツールの活用も提案したいです。」
第2部:JCDA(日本キャリア開発協会)編
JCDAが重視する視点:「経験代謝」と「自己概念の成長」
JCDAの面談は、「相談者自身の語り(経験)にじっくりと耳を傾け、本人が自分の経験の意味に気づき、成長していくプロセス」を何よりも大切にします。問題解決を急がず、相談者の内面に寄り添う姿勢が求められます。
協議会の面談は、「相談者が抱える問題を明確にし、解決に向けた具体的な行動を支援する」というプロセスを重視する傾向があります。評価の際には、行き当たりばったりではなく、論理的で構造化された面談ができているかどうかが見られます。
経験代謝(経験の再現 → 意味の出現 → 意味の構成)、自己概念、ありのままの自分
相談者が安心して自分を語れる場を作り、その人自身の気づきや学びを促進するファシリテーター。
評価区分の理解と口頭試問への活かし方
JCDAの評価区分は「主訴・問題の把握」「具体的展開」「傾聴」です。特に「主訴・問題の把握」では、言葉の背景にある感情や価値観、その人らしさ(自己概念)まで捉えられているかが問われます。
- 主訴・問題の把握: 相談者の経験や感情、自己概念をどこまで深く理解できたか。
- 具体的展開: 相談者の自己探索を促すような関わり方ができているか。
- 傾聴: 相談者の世界に入り込み、共に経験を味わうような深い聴き方ができているか。
【JCDA向け】口頭試問・回答のポイント
質問1&2:「できた点」と「できなかった点」
- ポイント: 相談者の「感情」や「経験」にどう寄り添えたかを答える。
- 良い回答例(できた点): 「相談者が過去の失敗談を話された際に、『その時、どんなお気持ちでしたか?』とお尋ねすることで、事実だけでなく、その経験に伴う感情にも焦点を当て、ご自身の気持ちを深く見つめるきっかけ作りができた点です。」
- 良い回答例(できなかった点): 「相談者の話が堂々巡りになっていると感じた際、焦ってしまい、相談者の言葉の背景にある感情や価値観を問うのではなく、事実確認の質問に終始してしまいました。もっとご本人の内面に寄り添うべきだった点が課題です。」
質問3:「主訴」の捉え方
- ポイント: 「~したい自分」と「~できない自分」の葛藤として捉える。
- 良い回答例: 「新しいことに挑戦したい(ありたい自分)と思いながらも、周囲の評価を気にして一歩踏み出せずにいる(現実の自分)、その葛藤の中でどう自分らしく振る舞えばいいのか分からずにいるお気持ちが、最も訴えたい点だと捉えました。」
質問4:「キャリアコンサルタントから見た問題(見立て)」
- ポイント: 「自己概念の歪み」や「未統合の経験」として見立てる。
- 良い回答例: 「相談者は『自分には何もない』と仰っていましたが、お話を伺う中で見えた強みやこだわりについて、ご自身でまだ意味づけができておらず、価値あるものとして自己概念に統合できていない点が、一歩踏み出せない根本的な問題だと見立てました。」
質問5:「今後の展開」
- ポイント: 「経験代謝を促す」ための関わりを計画する。
- 良い回答例: 「まずは、ご自身がまだ価値を認められていないご経験について、さらに詳しくお話いただき(経験の再現)、その中にあったお気持ちやこだわりを一緒に探していく関わりを続けたいです。その中でご本人がご自身の経験の意味に気づき(意味の出現)、それを未来につなげていける(意味の構成)よう、じっくりとご支援いたします。」
まとめ:両団体の違い
| 観点 | キャリアコンサルティング協議会(CCC) | JCDA(日本キャリア開発協会) |
|---|---|---|
| ゴール | 問題解決、目標達成、行動変容 | 自己理解、自己受容、自己概念の成長 |
| 面談の進め方 | 構造的、論理的、計画的 | 受容的、共感的、相談者のペースを重視 |
| 見立ての言葉 | 自己理解不足、仕事理解不足 | 自己概念の歪み、経験の意味づけ不足 |
| コンサルタント | パートナー、支援者 | ファシリテーター、伴走者 |
どちらの団体で受験するにしても、この違いを理解し、口頭試問で使う言葉を意識的に選ぶことで、評価者の意図に沿った、より説得力のある回答ができます。


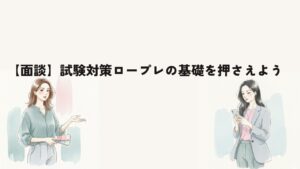
コメント