今回は、厚生労働省の報告書『働く環境の変化に対応できるキャリアコンサルタントに関する報告書』を基に、キャリアコンサルタントに求められていることをキャリコン試験に出そうな要点に絞りまとめたものです。
 まい
まい学科試験・実技試験双方の対策として、ぜひご活用ください。
学習しよう!
まず、現代のキャリアコンサルタントにどのような役割が期待されているかを理解することが、学習の土台となります。
変化への対応力
「人生100年時代」「DX」「働き方の多様化」といった社会の変化を捉え、それに対応できる支援が求められています。
「キャリア自律」の支援
労働者一人ひとりが主体的にキャリアを形成していく「キャリア自律」を支援することが、最も重要なミッションです。
伴走者としての役割
相談者のキャリア形成に寄り添う「伴走者」であり、キャリアに関する「かかりつけ医」のような身近な存在であることが期待されています。
【学習のポイント】
これらの背景を意識することで、各理論や施策が「なぜ必要なのか」という視点で理解を深めることができます。
① セルフ・キャリアドック
- 概要: 企業が主体となり、定期的に「キャリアコンサルティング」や「キャリア研修」を実施する総合的な仕組み。
- 目的: 従業員のキャリア自律を促し、組織活性化に繋げること。
【学習のポイント】
組織的な視点を理解することが不可欠です。
② ジョブ・カード
- 概要: 職務経歴や学習歴等をまとめ、自己理解を深めキャリアプランニングに役立てるツール。
- 近年の動向: デジタル化が進み、利便性が向上。
【学習のポイント】
「キャリアプランニング機能」と「能力証明機能」を理解しましょう。
③ 組織への働きかけ
- 提案力: 組織課題を分析し、経営層や人事部に改善策を提案する力。
- 協業する力: 人事担当者と連携し、支援策を企画・実行する力。
【学習のポイント】
個人支援に加え、会社全体に対して何ができるかを考えましょう。
- 理論と実践を結びつける: キャリア理論が、現代のどんな悩みに活用できるか考えましょう。
- 国の施策を正確に理解する: 厚生労働省のWebサイトで最新情報を確認しましょう。
- ロープレ練習での視点: 傾聴を基本としつつも、相談の背景にある組織的な問題は何かを考えましょう。
- 時事問題への関心: 「リスキリング」等のキーワードがどう繋がるか考える習慣をつけましょう。
理解度チェッククイズ
1. キャリアコンサルタントに今、求められていること(全体像の理解)
まず、現代のキャリアコンサルタントにどのような役割が期待されているかを理解することが、学習の土台となります。
- 変化への対応力: 「人生100年時代」「DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展」「働き方の多様化(リモートワーク、副業・兼業など)」といった社会の変化を捉え、それに対応できる支援が求められています。
- 「キャリア自律」の支援: 企業にキャリアを委ねるのではなく、労働者一人ひとりが主体的にキャリアを形成していく「キャリア自律」を支援することが、最も重要なミッションです。
- 伴走者としての役割: キャリアコンサルタントは、単に助言するだけでなく、相談者のキャリア形成に寄り添う「伴走者」であり、キャリアに関する「かかりつけ医」のような身近な存在であることが期待されています。
【学習のポイント】 これらの背景を意識することで、各理論や施策が「なぜ必要なのか」という視点で理解を深めることができます。
2. 学科・実技で問われる最重要キーワード
試験で頻出する、国の重要施策や概念について解説します。
① セルフ・キャリアドック
これは最重要キーワードの一つです。
- 概要: 企業が主体となり、従業員のキャリア形成を促進するために、定期的に「キャリアコンサルティング」や「キャリア研修」などを実施する総合的な仕組みのこと。
- 目的: 従業員のキャリア自律を促し、モチベーション向上や組織の活性化に繋げること。
- コンサルタントの役割:
- 個別のキャリアコンサルティングの実施。
- キャリア研修の企画・実施。
- 経営層や人事部門への制度導入・運用の働きかけ、コンサルティング結果から見えた組織課題のフィードバック。
【学習のポイント】 単なる「キャリア面談」ではなく、「企業の生産性向上にも繋がる仕組み」という組織的な視点を理解することが不可欠です。論述試験でもこの視点は問われやすいです。
② ジョブ・カード
キャリアコンサルティングの場面で活用される重要なツールです。
- 概要: 個人の職務経歴、学習歴、職業訓練の経験などをまとめることで、自己理解を深め、キャリアプランニングに役立てるツール。
- 活用場面:
- 職業訓練の前後。
- 企業でのキャリア面談(1on1ミーティングなど)。
- 自己分析やキャリアの棚卸し。
- 近年の動向: スマートフォンなどで作成・管理できるデジタル化が進んでおり、利便性が向上しています。
【学習のポイント】 ジョブ・カードが持つ「キャリアプランニング機能」と「能力証明機能」を理解し、どのような場面でどう活用できるかを具体的にイメージできるようにしておきましょう。
③ 企業領域での役割:組織への働きかけ
近年の試験で特に重視されているのが、個人の支援に留まらない「組織への働きかけ」です。
- 求められる能力:
- 提案力: キャリアコンサルティングを通じて見えてきた組織全体の課題(例:コミュニケーション不足、若手の離職率の高さなど)を分析し、経営層や人事部に改善策を提案する力。
- 協業する力: 人事担当者と連携し、人材育成方針に沿ったキャリア支援策を企画・実行する力。
- 調整・構築力: 制度を円滑に運用するための、各部門との調整や関係構築力。
【学習のポイント】 「もし自分がこの企業の担当コンサルタントなら、個人への支援に加えて、会社に対して何を提案できるか?」という視点を常に持って学習を進めましょう。
3. 効果的な学習法
- 理論と実践を結びつける: キャリア理論を学ぶ際は、「この理論は、現代のどんな悩みを持つ相談者に活用できるだろう?」と考えながら学習しましょう。(例:計画された偶発性理論 → 予期せぬ異動で悩む相談者)
- 国の施策を正確に理解する: セルフ・キャリアドックやジョブ・カードについては、厚生労働省のウェブサイトで最新の情報を確認し、制度の目的や概要を自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。
- ロープレ練習での視点: 実技のロープレ練習では、傾聴を基本としつつも、「相談者の話の背景にある組織的な問題は何か?」という視点を持つと、より多角的な見立てができるようになります。
- 時事問題への関心: 新聞やニュースで「リスキリング」「人的資本経営」「多様な働き方」といったキーワードに関心を持ち、キャリアコンサルティングとどう繋がるかを考える習慣をつけましょう。
おわりに
キャリアコンサルタントの資格取得はゴールではなく、専門家としての学びを続けるスタートラインです。試験勉強を通じて得られる知識やスキルは、資格取得後、多くの人のキャリアを支えるための大切な基盤となります。
体調管理に気を付けて、ご自身のペースで学習を進めてください。応援しています!


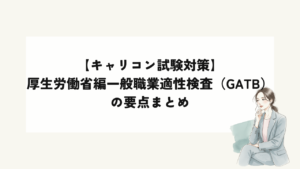
コメント