 チャチャ
チャチャアドラーといえば「嫌われる勇気」が思い浮かんじゃって、キャリアと結びつかないよ
アルフレッド・アドラー(Adler, A.)が提唱した「個人心理学」は、キャリアカウンセリングの現場で非常に実践的な示唆を与えてくれます。彼の理論の根底にあるのは、「人間の行動には必ず目的がある」という「目的論」。
過去の原因(トラウマなど)に囚われるのではなく、未来の目標に向かって自ら人生を創造していく存在として人間を捉えます。



この前向きな人間観が、キャリア支援の考え方と非常にマッチします!
・目的論
・全体論
・劣等感
・勇気づけ
・共同体間隔
インタラクティブ学習版
アドラー心理学
基本の考え方:目的論 vs 原因論
原因論 (Causality)
「過去の原因が、現在の私を決定している」と考える。行動の理由を過去に求める。
例:「過去に面接で失敗したから、不安で次の一歩が踏み出せない。」
目的論 (Teleology)
「未来の目的を達成するために、現在の感情や行動を創り出している」と考える。行動の理由を未来に求める。
例:「面接に行かないことで『失敗する可能性』を回避するという目的のために、不安という感情を創り出している。」
アドラー心理学の根幹をなす5つの理論
試験に出る!重要概念の解説
ライフタスク
人が生きていく上で直面する3つの課題。
勇気づけ vs 褒める
勇気づけ
水平関係(対等)
プロセス・貢献を承認
「ありがとう、助かるよ」
褒める
垂直関係(上下)
結果・能力を評価
「すごいね、えらい!」
知識の定着度をチェック!
【最重要!】アドラー心理学の基本5大理論
まず、アドラー心理学の根幹をなす5つの理論を理解しましょう。このどれもが試験で問われる可能性があります。
- 自己決定性 (Self-Determination)
- 内容: 人間は、遺伝や環境に支配されるのではなく、自分自身の人生を主体的に選択し、創造することができる存在である。
- キャリア支援への応用: クライエントは「会社のせい」「景気のせい」と原因を探しがちですが、「その状況で、あなたはどうしたいですか?」と問いかけ、主体性を取り戻す支援を行います。自分のキャリアは自分で決めるという基本姿勢を支える理論です。
- 目的論 (Teleology)
- 内容: 人間の行動や感情には、必ず何らかの「目的」があると考えます。フロイトの「原因論」(過去の原因が現在を決定する)と対比して覚えてください。
- 例: 「不安で面接に行けない」という人がいる場合、原因論では「過去の失敗が原因だ」と考えますが、目的論では「面接に行かないことで、失敗して傷つく可能性を回避するという目的がある」と考えます。
- キャリア支援への応用: クライエントの行動の「目的」を一緒に探ることで、本当の課題に気づかせ、一歩踏み出すための支援につなげます。
- 全体論 (Holism)
- 内容: 人間を「分割できない全体」として捉えます。意識と無意識、理性と感情、心と身体などを分けて考えません。
- キャリア支援への応用: 「仕事の悩み」だけを切り離して考えるのではなく、その人の生活全体(家族、趣味、健康など)との関連性を見ながら支援することが大切になります。
- 社会埋没感 (Social Embeddedness) / 共同体感覚 (Community Feeling)
- 内容: 人は社会的な存在であり、他者と関わり、所属し、貢献したいという欲求を持っていると考えます。この**「共同体感覚」**こそが、精神的な健康の指標であるとアドラーは説きました。
- キャリア支援への応用: 「この仕事を通じて、どのように社会に貢献できるか」「どんな仲間と働きたいか」といった視点は、クライエントの働く意欲を高め、仕事のやりがいを見出す上で非常に重要です。
- 仮想論 (Fictionalism)
- 内容: 人は、自分なりの主観的な思い込みや信念(仮想的な目標)を持って生きており、その目標が行動を方向づけていると考えます。
- キャリア支援への応用: 「安定した大企業に入れば幸せになれる」といったクライエントの信念(仮想)を尊重しつつ、それが本当にその人自身の幸せにつながるのかを一緒に考え、必要であればより現実的な目標設定を支援します。
【試験に出る!】重要キーワード解説
次に、選択肢などで直接問われやすいキーワードを解説します。
1. 劣等感と優越性の追求 (Inferiority & Pursuit of Superiority)
- 劣等感: 人間が持つ普遍的な感情であり、理想の自分と現在の自分とのギャップから生まれます。アドラーは、劣等感そのものは悪いものではなく、**努力や成長を促すバネ(健全な劣等感)**になると考えました。
- 優越性の追求: 劣等感を克服し、より向上したい、より良くありたいと願う普遍的な欲求です。これも人間を成長させる原動力となります。
- 注意点:
- 劣等コンプレックス: 劣等感をバネにせず、「自分はダメだ」と言い訳にして課題から逃げる状態。
- 優越コンプレックス: 劣等感を隠すために、あたかも自分が優れているかのように見せかける状態。
- キャリア支援では、クライエントが劣等感を健全なエネルギーに変えられるよう支援します。
2. ライフスタイル (Lifestyle)
- 内容: その人固有の「人生の設計図」や「生き方のクセ」のようなもの。自己概念(自分についてどう考えているか)、世界像(世界についてどう考えているか)、自己理想(どうありたいか)から成り立ちます。
- 特徴: 4〜5歳頃までに原型が作られるとされますが、いつでも自分自身の意志で変えることができるとアドラーは考えました。
- キャリア支援への応用: クライエントの物事の捉え方や行動パターン(ライフスタイル)を理解することで、なぜ特定のキャリア課題でつまずいているのかが見えてきます。そして、必要であれば新しいライフスタイル(考え方や行動)を再選択する支援を行います。
3. ライフタスク (Life Tasks)
- 人間が生きていく上で直面せざるを得ない課題を3つに分類しました。これらは互いに深く関連しています。
- 仕事のタスク (Work): 生計を立て、社会に貢献すること。
- 交友のタスク (Friendship): 他者と信頼関係を築くこと。
- 愛のタスク (Love): パートナーと親密な関係を築くこと。
- キャリア支援への応用: 「仕事のタスク」がうまくいかない背景に、「交友のタスク」(職場の人間関係)が影響していることは頻繁にあります。クライエントの悩みがどのタスクに関連しているかを見極め、統合的に支援する視点が求められます。
4. 勇気づけ (Encouragement)
- 内容: クライエントが困難を克服する活力を与えるためのアプローチ。課題に立ち向かう勇気を取り戻してもらうことが目的です。
- 「褒めること」との違い:
- 褒める (Praise): 「すごいね」「えらいね」など、能力や結果に対する上から目線の評価(垂直関係)。
- 勇気づけ (Encourage): 「ありがとう、助かったよ」「頑張っているね」など、存在そのものやプロセス、貢献に対する感謝や共感(水平関係)。
- キャリア支援での実践: 結果が出なくても、クライエントが行動したこと自体を尊重し、そのプロセスを承認することが「勇気づけ」となり、次の一歩を後押しします。
まとめ:キャリアコンサルタントとしての心構え
アドラー心理学は、クライエントを「かわいそうな人」「できない人」として扱うのではなく、**「自分の人生を切り拓く力を持った対等なパートナー」**として尊重する姿勢を教えてくれます。
- 原因探しより、未来志向で
- 評価するのではなく、勇気づける
- クライエントの自己決定を信じ、支援する
これらの視点は、キャリアコンサルタントの倫理綱領にも通じる非常に大切な考え方です。理論の暗記だけでなく、その背景にある温かい人間観を感じ取ることが、合格への一番の近道です。
試験勉強、応援しています!

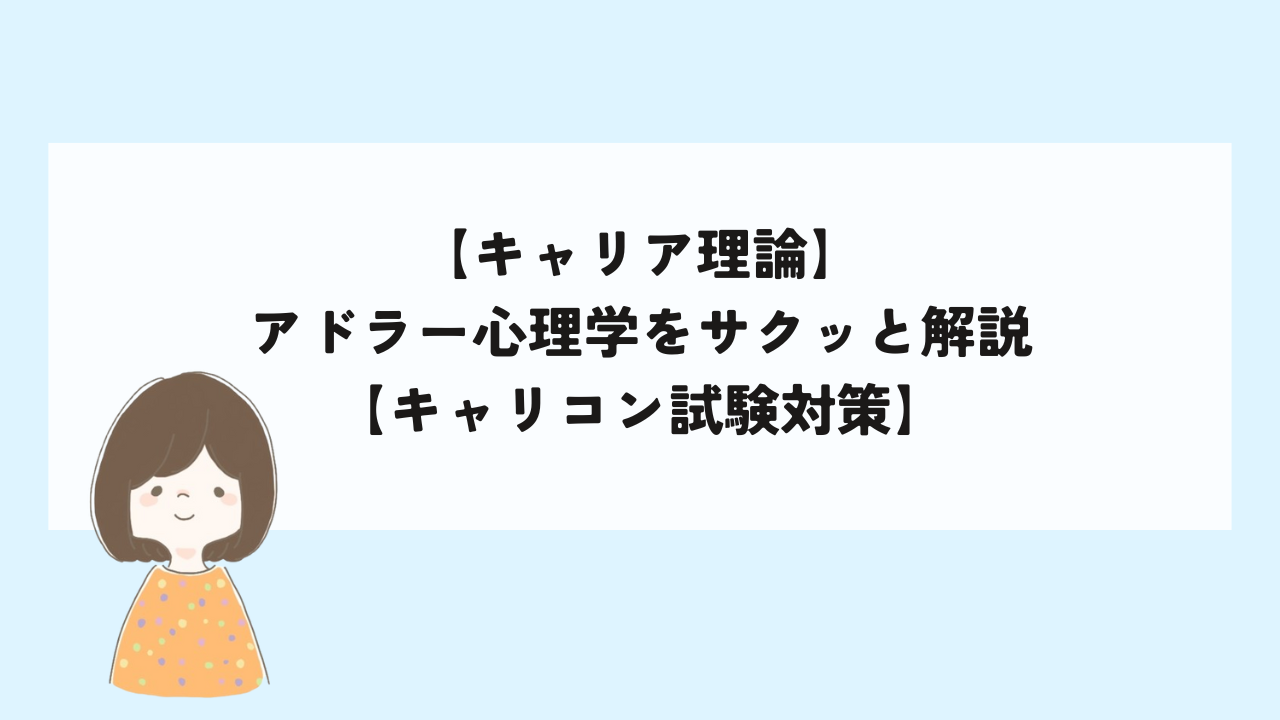
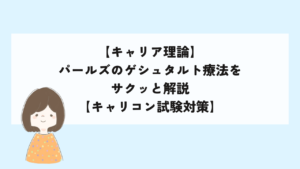


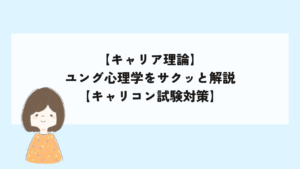
コメント