 チャチャ
チャチャ「防衛機制」は高校の倫理でやった覚えがある!うっすら覚えているよ!



自分もなんとなく経験のあることだから、理解しやすいかもしれないね
・防衛機制
心優しい娘アンナ・フロイト


アンナ・フロイトは、「精神分析の父」として超有名なジークムント・フロイトの末娘さんです。
でも、ただの「偉大なお父さんを持つ娘」ではなかったんです。彼女自身も、心理学の世界で大きな足跡を残した、すごい研究者でした。
特にアンナが得意としたのが、「子どもの心の分析」の分野です。
お父さんのフロイトが、大人の心の奥底にある複雑な「無意識」の世界を探検したのに対し、アンナはもっと私たちの身近な心の働きに注目しました。
例えば、私たちがストレスを感じた時に、つい言い訳を考えたり(合理化)、嫌なことを忘れようとしたり(抑圧)しますよね。こうした「心を守るための無意識の工夫」、つまり「防衛機制」を、誰にでも分かりやすく整理して体系化したのが、アンナの大きな功績の1つ。



お父さんが心の「地下室(無意識)」の探検家だとしたら、アンナは、私たちが日々生活する「1階(意識的な自分)」で、どうやって上手に悩みやストレスと付き合っていくか、その知恵を教えてくれた人、という感じかな。



特に子どもたちの心に寄り添い、その健やかな成長を助けることに情熱を注いだ、心優しいパイオニアだったらしいです。
防衛機制をサクッと理解しよう
防衛機制とは?
防衛機制とは、受け入れがたい思考、感情、または外部からの脅威によって生じる不安や苦痛から、私たち自身(自我)を守るために、無意識的に働く心理的なメカニズムです。アンナ・フロイトによって体系化されたこの概念は、心のバランスを保ち、社会に適応するために不可欠な働きですが、過度な依存は問題を引き起こす可能性もあります。
防衛機制の成熟度レベル
防衛機制は、その適応性によって「成熟」「神経症的」「未熟」のレベルに分類できます。成熟した機制ほど、現実へのより良い適応につながります。
ストレスと防衛機制(仮想データ)
強いストレス下に置かれると、人はより未熟な防衛機制に頼る傾向があります。このチャートは、平常時と高ストレス時の傾向を仮想的に示しています。
10の代表的な防衛機制
1. 否認 (Denial)
不快な現実や事実を、証拠があっても文字通り認めようとしない。
例:重病の診断を受けても「何かの間違いだ」と信じようとしない。
2. 抑圧 (Repression)
苦痛な記憶や欲求を、無意識の領域へと締め出し、忘れてしまう。
例:子供時代の辛い体験の記憶がすっぽり抜け落ちている。
3. 反動形成 (Reaction Formation)
受け入れがたい欲求と正反対の態度や行動をとる。
例:嫌いな相手に、過剰なほど親切に振る舞う。
4. 投影 (Projection)
自分の認めたくない感情を、他人が持っているかのように感じる。
例:自分が相手を嫌っているのに「相手が私を嫌っている」と思い込む。
5. 退行 (Regression)
ストレスに直面した際、より幼い発達段階の行動に戻る。
例:弟が生まれ、赤ちゃん返りする子供。
6. 知性化 (Intellectualization)
感情を切り離し、出来事を理屈や知的な言葉で分析し距離を置く。
例:失恋の辛さを、恋愛心理学の観点から淡々と語る。
7. 合理化 (Rationalization)
自分の不合理な行動にもっともらしい理由をつけて正当化する。
例:試験に落ちたのを「先生の教え方が悪かった」と考える。
8. 取り消し (Undoing)
罪悪感を伴う考えや行為を、別の行動で打ち消そうとする。
例:悪い考えを抱いた後、罪滅ぼしに良い行いをする。
9. 同一視 (Identification)
優れた他者の特徴を取り入れ、自分の価値を高めようとする。
例:尊敬する上司の話し方や服装を真似る。
10. 昇華 (Sublimation)
社会的に認められにくい欲求を、価値ある活動に転換する。
例:攻撃的な衝動を、スポーツに打ち込むことで発散する。


カウンセリング中に起こり得る状態・用語についてもサクッと理解
アンナ・フロイトの理論とは異なりますが、カウンセリング中に起こり得る状態についてもここで理解しておきましょう。



過去問にも出たポイントだよ!
精神分析の力動学
治療空間における無意識の相互作用を探る
治療関係のダイナミクス
下の図の各要素をクリックすると、詳細な解説に移動します。これは、治療者とクライエントの間で繰り広げられる、無意識的な感情のやり取りを視覚化したものです。
クライエント
治療者
1. 抵抗 (Resistance)
「抵抗」とは、治療のプロセスで無意識の葛藤や抑圧された記憶が意識に上ることに、クライエントが無意識的に抵抗し、治療の進行を妨げようとする働きです。これは苦痛な内容から自我を守るための防衛反応であり、意図的な妨害ではありません。
抵抗の現れ方(具体例)
- 予約を忘れる、遅刻する
- 話が核心に近づくと黙り込む、話題をそらす
- 治療者の解釈に理屈で反論する(知性化)
- 「話すことが何もありません」と言う
治療における意味
抵抗は単なる障害物ではなく、クライエントが最も触れたくない、しかし最も重要な無意識の葛藤を示す「道しるべ」です。治療者はこの抵抗を分析し、クライエントがそれを乗り越えられるよう援助します。
2. 転移 (Transference)
「転移」とは、クライエントが過去(主に幼少期)の重要な他者(特に両親)に対して抱いた感情や欲求を、無意識のうちに現在の治療者に向け、過去の関係性を再現しようとする心理現象です。
陽性転移(肯定的)
治療者に対して愛情、尊敬、信頼、理想化といった肯定的な感情を向けます。
例:治療者を完璧な父親のように感じ、その言うこと全てを信じる。
陰性転移(否定的)
治療者に対して怒り、不信、憎しみ、反抗といった否定的な感情を向けます。
例:些細な一言を、かつての批判的な親の言葉のように感じ、激しく反発する。
治療における意味
転移は精神分析の中心的な治療の道具です。クライエントは転移を通じて過去の未解決な葛藤を安全に再現します。治療者はこの感情を解釈し、クライエントが自身の対人関係パターンの起源を洞察し修正していくのを助けます(転移分析)。
3. 逆転移 (Countertransference)
「逆転移」とは、クライエントの転移に反応して、治療者の側にも引き起こされる無意識的な感情反応です。治療者がクライエントに対して抱く、個人的な感情や葛藤が反映された反応を指します。
逆転移の捉え方の変化
古典的な見方:治療の「邪魔者」
当初、逆転移は治療者が客観性を失った状態であり、治療の妨げになるため克服すべきものだと考えられていました。
治療における意味
現代では、逆転移はクライエント理解の重要な情報源とされます。治療者は自身の逆転移に気づき自己分析することで、その感情をクライエント理解に活用します。治療者の自己覚知と訓練が極めて重要です。

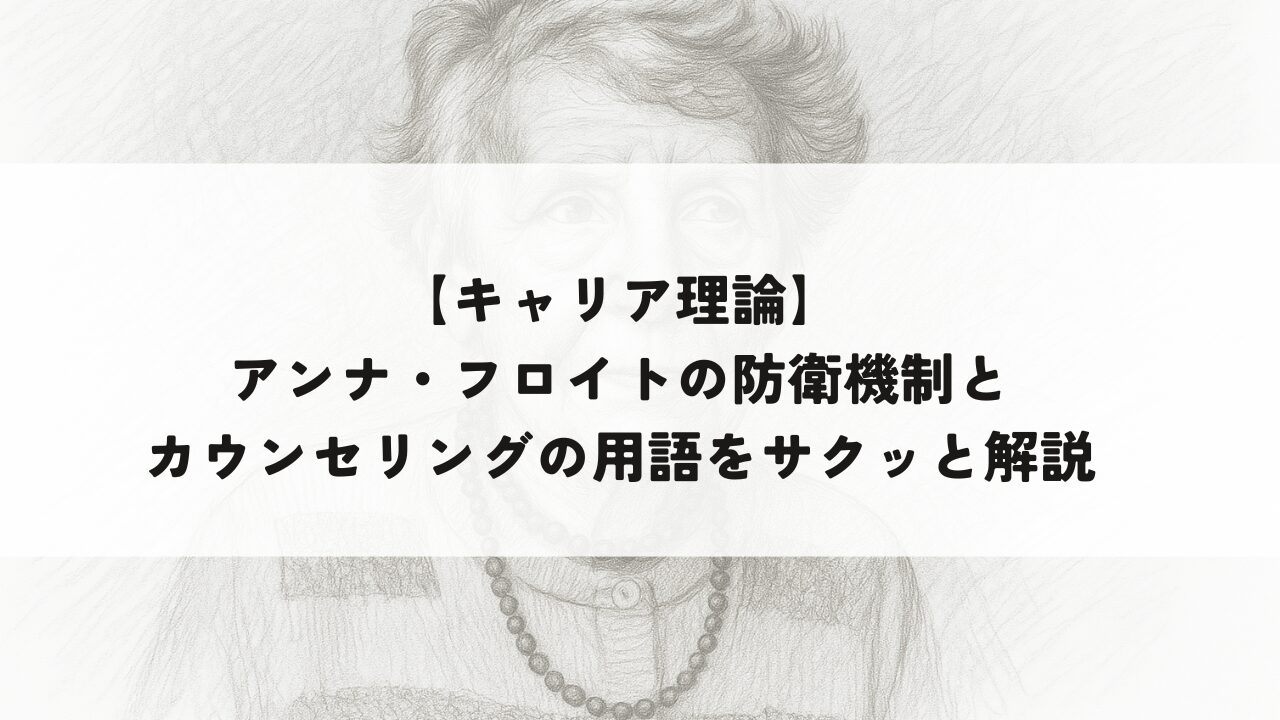
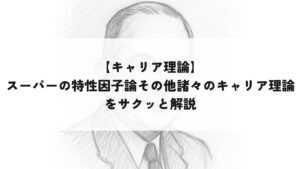

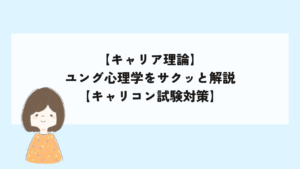
コメント