 チャチャ
チャチャ動機づけででてくるデシ先生。意外と有名なんだね……あんまり理解していないよ……



デシ先生はアンダーマイニング効果を発見した先生だね。
本日は、試験で頻出の重要人物、エドワード・デシが提唱した自己決定理論(Self-Determination Theory: SDT)について、ポイントを絞って徹底的に解説します。
・内発的動機付け
・自己決定理論(SDT)
・アンダーマイニング効果
インフォグラフィック版
試験ポイント①:2つの動機づけ
内発的動機づけ
活動そのものが楽しい、面白いと感じることから生まれる「内なるやる気」です。
例:
- パズルが面白いから夢中になる
- 知的好奇心から本を読む
- 成長が実感できて仕事が楽しい
キーワード: 興味, 楽しさ, 好奇心, 成長感
外発的動機づけ
報酬を得る、罰を避けるなど、外部からの働きかけで生まれる「外からのやる気」です。
例:
- お給料をもらうために働く
- 叱られたくないから宿題をする
- 昇進したいから頑張る
キーワード: 報酬, 罰, 強制, 評価, 期待
試験ポイント②:アンダーマイニング効果
「ご褒美で釣ったら、やる気がなくなった」
内発的に動機づけられていた活動に対し、報酬という外発的動機づけを与えると、かえって元々のやる気が低下する現象です。
理由:
パズルを解く目的が「楽しいから」→「お金のため」にすり替わるためです。
試験ポイント③:認知評価理論
外的報酬は常にやる気を削ぐわけではありません。報酬を「どう受け取るか」によって、その効果は変わります。
統制的側面
報酬が「行動をコントロールされている」「やらされている」と感じさせる側面。
内発的動機づけ → 低下 ▼
例:「ノルマを達成しないとボーナスが出ないぞ」
情報的側面
報酬が「自分は有能だ」「よくやった」というメッセージとして伝わる側面。
内発的動機づけ → 維持・向上 ▲
例:「素晴らしい成果だったので、特別ボーナスを支給します」
試験ポイント④:3つの基本的心理欲求
人が幸福感を高く保ち、内発的に動機づけられるために不可欠な、生まれながらに持つ3つの欲求です。
自律性 (Autonomy)
自分の行動は自分自身で選択・決定したい。
支援視点:クライエント自身の意思決定を尊重する。
有能感 (Competence)
「自分はできる」と感じ、課題を乗り越えたい。
支援視点:成功体験を振り返り、強みを見つける。
関係性 (Relatedness)
他者と尊重し合える良い関係を築きたい。
支援視点:職場での人間関係の重要性を伝える。
最終チェック・クイズ
ブログ解説
はじめに:なぜデシの理論が重要なのか?
キャリアコンサルティングにおいて、クライエントの「やる気」、つまり**動機づけ(モチベーション)**を理解することは非常に重要です。デシの理論は、この動機づけの本質を解き明かし、「人はどうすれば自ら進んで、イキイキと活動できるのか?」という問いに答えてくれます。クライエントが主体的なキャリアを築く支援の根幹となる理論ですので、しっかり押さえましょう。
試験ポイント①:すべての基本「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」
デシの理論は、この2つの動機づけを区別するところから始まります。
- 内発的動機づけ (Intrinsic Motivation)
- 活動そのものが楽しい、面白い、興味深いと感じることから生まれる「内なるやる気」です。
- 例:「パズルが面白いから夢中になる」「知的好奇心から本を読む」「成長が実感できて仕事が楽しい」
- キーワード: 興味、楽しさ、好奇心、成長感
- 外発的動機づけ (Extrinsic Motivation)
- 報酬を得る、罰を避けるなど、外部からの働きかけによって生まれる「外からのやる気」です。
- 例:「お給料をもらうために働く」「叱られたくないから宿題をする」「昇進したいから頑張る」
- キーワード: 報酬、罰、強制、評価、期待
【試験での問われ方】 具体的な事例が示され、「これは内発的動機づけか、外発的動機づけか」を問う問題が考えられます。まずはこの基本をしっかり区別できるようにしましょう。
試験ポイント②:超頻出!「アンダーマイニング効果」
ここがデシの理論で最も有名で、試験にも出やすい部分です。
アンダーマイニング効果とは?
内発的動機づけによって行われていた活動に対して、報酬などの外発的な動機づけを与えると、かえって内発的動機づけが低下してしまう現象。
簡単に言うと、「ご褒美で釣ったら、やる気がなくなっちゃった」という現象です。
- デシの有名な実験(ソーマパズル実験)
- 学生を2つのグループに分ける。
- 両グループに面白いパズル(内発的動機づけの源)を解いてもらう。
- 一方のグループにだけ「1問解くごとに報酬(お金)をあげます」と伝える(外発的動機づけを与える)。
- 実験後、自由時間に学生の様子を観察すると、報酬をもらっていたグループの方が、もらっていなかったグループよりパズルで遊ぶ時間が短くなった。
- なぜこうなるのか? 報酬をもらった学生は、パズルを解く理由が「楽しいから」から「お金のため」にすり替わってしまったのです。そのため、お金がもらえない自由時間になると、パズルをやる理由がなくなり、モチベーションが低下しました。
【キャリアコンサルティングへの応用】
「給料や待遇(外的報酬)さえ良ければ、クライエントは満足するだろう」という安易な考えへの警鐘となります。仕事そのものの面白さややりがい(内的報酬)をいかに見出すかが重要である、という支援の視点につながります。
試験ポイント③:アンダーマイニング効果をさらに深掘り「認知評価理論」
では、外的報酬は常にやる気を削ぐのでしょうか?デシは「そうとは限らない」と言います。そのカギは、報酬を「どう受け取るか」にあります。
外的報酬には2つの側面があります。
- 統制的側面 (Controlling Aspect)
- 報酬が「行動をコントロールされている」「やらされている」と感じさせる側面。
- これが強調されると、自律性が損なわれ、内発的動機づけは低下します。(例:「ノルマを達成しないとボーナスが出ないぞ」)
- 情報的側面 (Informational Aspect)
- 報酬が「自分は有能だ」「よくやった」というメッセージとして伝わる側面。
- これが強調されると、有能感が高まり、内発的動機づけは維持・向上します。(例:「素晴らしい成果だったので、特別ボーナスを支給します」)
【試験での問われ方】 「外的報酬は常に内発的動機づけを低下させる」といった選択肢は誤りです。報酬の持つ側面(統制的か、情報的か)によって影響が異なる、という点を正確に理解しておきましょう。
試験ポイント④:自己決定理論の核!「3つの基本的心理欲求」
デシとライアンは、人が幸福感(ウェルビーイング)を高く保ち、内発的に動機づけられるためには、生まれながらに持つ以下の3つの心理欲求が満たされることが不可欠だと考えました。これは最重要項目です。
- 自律性 (Autonomy) の欲求
- 自分の行動は「自分自身で選択・決定したい」という欲求。
- キャリア支援の視点: クライエント自身に意思決定させる、選択肢を提示する、自己理解を深め主体性を尊重する。
- 有能感 (Competence) の欲求
- 「自分はできる」「能力がある」と感じたい、課題を乗り越えたいという欲求。
- キャリア支援の視点: 成功体験を振り返る、強みを見つける、挑戦的な目標設定(ストレッチ目標)を支援する、フィードバックを与える。
- 関係性 (Relatedness) の欲求
- 他者と尊重し合える良い関係を築きたい、集団に所属したいという欲求。
- キャリア支援の視点: 職場での人間関係の重要性を伝える、ロールプレイで対人スキルを向上させる、メンターや仲間を見つける支援をする。
【試験での問われ方】 この3つの欲求は、名称と内容を必ずセットで覚えましょう。「自律性とは何か?」を説明させる問題や、具体例がどの欲求に当てはまるかを問う問題が出題されます。
まとめ:試験対策の最終チェック
- 内発的動機づけと外発的動機づけの違いを説明できますか?
- アンダーマイニング効果とは何か、ソーマパズルの実験を例に説明できますか?
- 外的報酬がやる気を下げるのは統制的側面が強い時、逆に上げる可能性があるのは情報的側面が強い時、と理解していますか?
- 3つの基本的心理欲求、「自律性」「有能感」「関係性」を暗記し、それぞれが何を指すか説明できますか?
これらの問いに自信を持って「はい」と答えられれば、デシの理論に関する問題は怖くありません。
クライエントが「自分で決め(自律性)、できると感じ(有能感)、周りと繋がりながら(関係性)」キャリアを歩めるよう支援するのが、我々キャリアコンサルタントの役目です。デシの理論は、そのための強力な羅針盤となります。
試験勉強、頑張ってください!

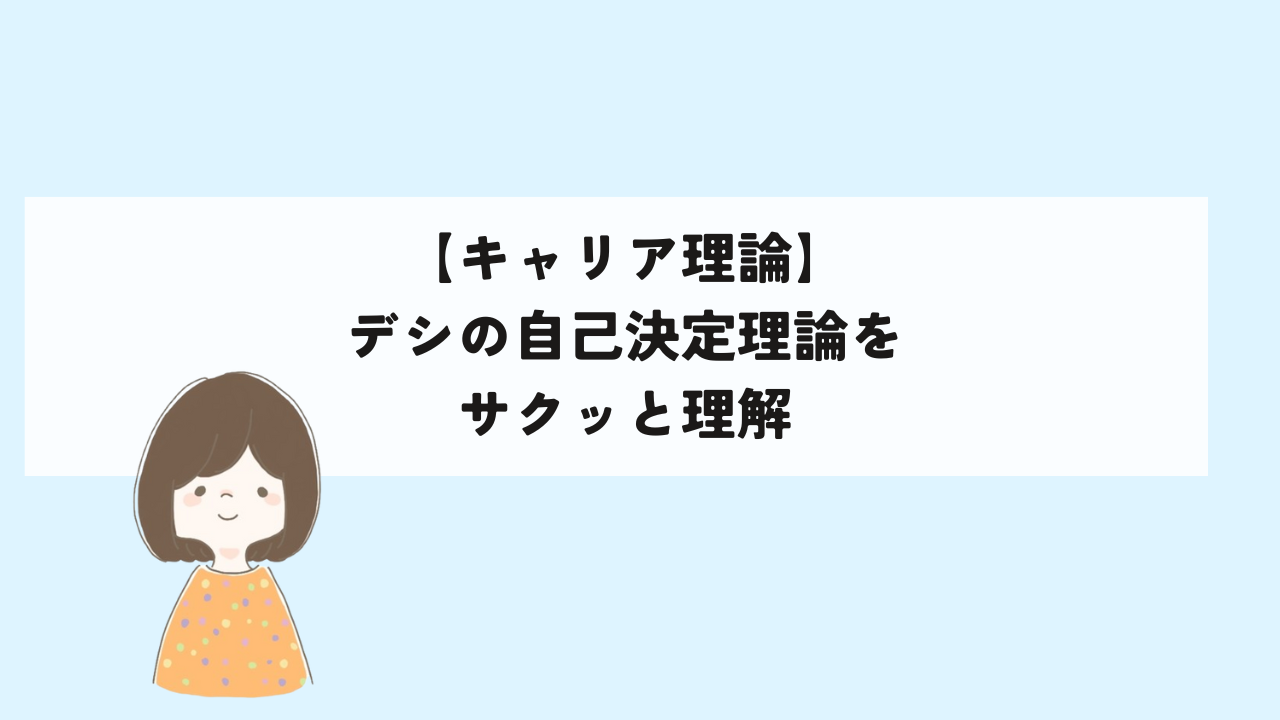
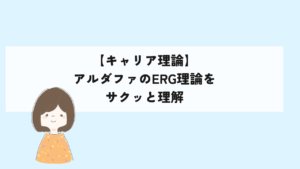
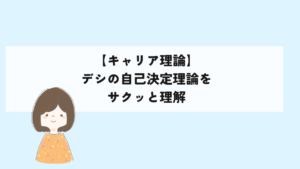

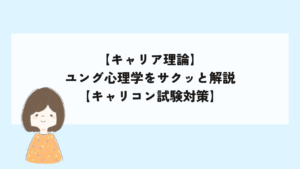
コメント