 チャチャ
チャチャ岡本祐子先生ってキャリコン試験で重要みたいだけど、どうしてだろう



岡本祐子先生は、エリクソンの理論をもとにしたライフサイクルの第一人者。臨床心理士であり、教育学博士だよ。
今日はそんな岡本祐子先生の各理論をサクッと理解。関係性に基づくアイデンティティやアイデンティティのラセン式発達モデルなどの重要ポイントを、わかりやすく解説していきます!
・個としてのアイデンティティ
・関係性にもとづくアイデンティティ
・アイデンティティのラセン式発達モデル
日本カウンセリングの母 岡本祐子先生


岡本祐子(1954~)先生は、日本のキャリアカウンセリングの世界で、とても有名で重要な先生です。大学の先生として、たくさんのキャリアコンサルタントを育ててこられました。
一言でいうと、「あなたの物語こそが宝物ですよ」と教えてくれる先生。一人ひとりの心の中にある「主観」や「物語」を何よりも大切にし、その人が自分らしいキャリアを築くのを温かくサポートする、という考え方を広めた、日本のキャリアカウンセリングにおける母のような存在です。



「お前がはじめた物語だろ!」とは絶対に言わない



……母のような岡本祐子先生の理論を見て行きましょう!
岡本祐子先生の重要な概念
岡本祐子先生は、日本の発達心理学者であり、特に成人期、とりわけ中年期の発達に関心を持ち、多くの重要な概念を提唱されました。エリクソンなどの欧米の理論を日本の文化的文脈の中で捉え直し、独自の理論を展開しています。



ここでは、先生の主要な概念について解説します。
1. 個としてのアイデンティティと関係性に基づくアイデンティティ
伝統的なアイデンティティ論(エリクソンなど)では、「自分は何者か」という問いに対し、他者や社会から独立した「個」としての自己確立が重視される傾向がありました。



岡本先生は、これに加えて「関係性に基づくアイデンティティ」の重要性を指摘しました。
これは、他者との具体的な関わりの中で「〇〇の母」「〇〇会社の部長」「〇〇のパートナー」といった役割を通じて形成され、自己を認識するあり方です。
重要なのは、この二つが対立するものではないという点です。
個と関係性のアイデンティティ
岡本祐子先生の提唱する二つのアイデンティティの側面
👤 個としてのアイデンティティ
状況や他者との関係によらない、一貫した「自分はこういう人間だ」という自己の中核部分。
- 普遍性: どのような状況でも変わらない、自分の中の核となる信念や価値観。
- 自律性: 他者から独立して自己を定義しようとする志向性。
- 伝統的視点: 西洋の心理学(エリクソンなど)で特に重視されてきた自己のあり方。
🤝 関係性に基づくアイデンティティ
「〇〇の母」や「△△会社の社員」など、他者との具体的な関係性の中で認識される自己。
- 状況依存性: 関わる相手や場面によって変化し、柔軟に現れる自己の側面。
- 相互性: 他者との関わりの中で「生かされている自分」として自己を認識する。
- 日本的文脈: 岡本先生が特に日本の文化的文脈において重要性を指摘した概念。
重要な視点:二つのアイデンティティのバランス
岡本先生は、これら二つが対立するものではなく、人は生涯を通じて両方のアイデンティティのバランスを取りながら、より豊かで成熟した自己を形成していくと考えました。



ぼくは「ぼく」でもあるし、まいさんに飼われているさわだ家の飼い犬でもある。



特に日本では、欧米に比べて関係性の中で自己を捉える傾向が強いとされています。
2. 岐路としての中年期
中年期(およそ40歳〜65歳)は、しばしば「中年の危機(ミッドライフ・クライシス)」としてネガティブに語られがちです。しかし、岡本先生は中年期を「人生の岐路」として捉え直しました。
これは、中年期がこれまでの人生を振り返り、これからの生き方を問い直し、再選択・再構築するための重要な転換期であるという視点です。
岐路としての中年期
岡本祐子先生が提唱する、中年期を「危機」ではなく「転機」と捉える視点
1. 課題
人生の正午を迎え、様々な変化や喪失に直面する時期。
- 身体的変化: 体力の衰えや健康問題など、老いの兆候を自覚する。
- 社会的役割の変化: 子の独立(空の巣)、親の介護、職場での立場の変化。
- 時間意識の変化: 「残された時間」を意識し始め、焦りや問いが生まれる。
2. 問い直し
直面した課題をきっかけに、これまでの生き方や価値観を見つめ直す。
- アイデンティティの問い: 「本当にこのままで良いのか?」「自分にとって大切なものは何か?」
- 人生の意味の探求: これまでの人生を振り返り、新たな意味や目的を探し始める。
- 価値観の棚卸し: 社会や他者から与えられた価値観ではなく、自らの内なる声に耳を傾ける。
3. 再構築
問い直しを経て、新たな価値観に基づき、後半の人生を再設計する。
- 新たな自己像の確立: 変化を受け入れ、より統合された新たなアイデンティティを築く。
- 新しい目標設定: 仕事、家庭、趣味など、人生の各領域で新しい目標や関心事を見出す。
- 人生の受容: 過去の選択を受け入れ、未来に向けてより主体的に生きる姿勢を獲得する。
重要な視点:中年期は「衰退」ではなく「発達の機会」
岡本先生は、この「課題→問い直し→再構築」というプロセスを経ることで、中年期が人生をより深く、豊かにするための積極的な発達の機会となりうると考えました。
このように、中年期は単なる衰退期ではなく、人生をより豊かにするための積極的な発達の機会となりうるのです。



まいさんも岐路に立たされているんだね



たくさんの先生のいろいろな理論を勉強しているからね。危機ではなく転機ととらえられているよ!
3. ライフスタイルとケア役割
中年期のアイデンティティ形成には、その人のライフスタイル(仕事、家庭、趣味など、生活の様々な領域の組み合わせ)が大きく影響します。
中でも岡本先生が特に注目したのが「ケア役割」です。これは、子育てや親の介護といった、他者の世話をする役割を指します。
ライフスタイルとケア役割
中年期のアイデンティティ形成に影響を与える生活のあり方
ライフスタイル
仕事、家庭、趣味など、生活の様々な領域の組み合わせがアイデンティティに影響を与える。
中年期には、これまでのライフスタイルが問い直されることが多くなります。仕事での役割の変化、子どもの独立による家庭環境の変化など、生活全体のバランスが変動し、それが自己認識、つまりアイデンティティの見直しを促すきっかけとなります。
ケア役割
特に岡本先生が注目した、子育てや親の介護といった他者を世話する役割。
- 自己の変容: 大きな負担であると同時に、自己中心的な視点から他者中心の視点へと価値観を転換させ、自己を大きく変容させる契機となる。
- 関係性の深化: ケアを通じて他者との深い結びつきを経験し、自己の存在価値や生きる意味を再認識する。
- アイデンティティの再構築: 他者のために生きる意味を見出す経験は、関係性に基づくアイデンティティを豊かにし、個としてのアイデンティティをも再構築する力を持つ。
重要な視点:ケアは負担であると同時に、自己変容の機会
ケア役割を担う経験は、単なる時間や労力の消費ではなく、自己をより深く理解し、アイデンティティを豊かに再構築するための重要なプロセスであると岡本先生は捉えました。



自分のことだけを考えているのもしんどいかも。ケアは負担ではあるけど、自分の役割を感じられアイデンティティにも影響を与えると思うな



ま、バランスも大事だね
4. 世代継承性(ジェネラティビティ)
世代継承性(ジェネラティビティ)
次の世代を育て、文化や技術を伝えていこうとする関心や関わり
🌱 世代継承性とは?
エリクソンが提唱した成人期の発達課題で、自己の関心を超え、次世代のために何かを生み出し、世話をすることへの関心。中年期にこの課題を達成することが、精神的な健康や生きがいにつながるとされます。
👨👩👧👦 親性(ケア)
子どもを産み、育てることを通じて、次の世代へ直接的に生命や愛情を伝える関わり。
自分の子どもだけでなく、教育者として生徒を指導したり、地域の子どもを見守ったりすることも含まれます。ケアを通じて、自己の経験や価値観を伝達します。
🛠️ 技術の継承
職場で後輩に知識やスキルを教え、育てていくこと。師弟関係などもこれにあたる。
自分が培ってきた専門的な技術やノウハウを次の世代に伝えることで、組織や社会の発展に貢献します。これは自己の能力を社会に還元する行為です。
🏛️ 文化の継承
芸術作品の創作、研究、地域の伝統文化の担い手など、文化的な遺産を創造・維持する活動。
形に残るものを通じて、時代や世代を超えて価値観や思想を伝えます。個人の死を超えて、自己の生きた証を後世に残すことにつながります。
🌍 社会への貢献
ボランティア活動や社会制度の改善など、より良い社会を築き、次世代に残そうとする関わり。
直接的な個人への関わりだけでなく、より広い共同体や社会全体の未来を良くしようとする意志や行動も、重要な世代継承性の一環です。
重要な視点:自己の超越と人生の意味
世代継承性は、自分自身の存在を超えて、より大きな何かの一部となる感覚をもたらします。これは、人生の有限性を受け入れ、死への不安を和らげ、人生に深い意味と満足感を与える重要な働きを持つとされています。
5. アイデンティティのラセン式発達モデル
岡本先生は、アイデンティティの発達が青年期に完成して終わるのではなく、生涯にわたって続くプロセスであると考え、「ラセン(螺旋)式発達モデル」を提唱しました。
これは、アイデンティティが以下のサイクルを繰り返しながら、螺旋階段を上るように、より成熟し、深まっていく様子を表したモデルです。



アイデンティティなんて難しいもの、青年期に完成するわけない!とぼくも思うのだ!
アイデンティティのラセン式発達モデル
生涯を通じてアイデンティティが発達していくプロセス
1. 安定・達成
ある時点でアイデンティティが確立され、自己認識が安定している状態。
青年期に確立した自己像や、中年期にある特定の役割(親、管理職など)に満足し、自分自身について明確な感覚を持っている段階です。「自分はこういう人間だ」という感覚が揺るがない時期を指します。
2. 揺らぎ・葛藤
ライフイベント等をきっかけに、既存のアイデンティティが揺らぎ、葛藤が生じる状態。
失業、転職、子どもの独立、病気といった出来事に直面し、これまでの自己像では対応できなくなります。「これで本当に良いのか?」「自分は何者なのか?」といった問いが再び生まれ、自己認識が不安定になる段階です。
3. 再体制化
葛藤や問い直しを経て、新たな要素を取り込み、より高次の次元でアイデンティティを再構築する。
葛藤の時期を乗り越え、新たな経験や価値観を自己像に統合します。これにより、以前よりも複雑で、成熟し、深みのある自己認識を獲得します。アイデンティティが一段階上のレベルで再び「安定」へと向かう段階です。
重要な視点:発達は「円環」ではなく「ラセン(螺旋)」
このサイクルは、単に同じ場所をぐるぐる回るのではなく、螺旋階段を上るように、繰り返すたびにアイデンティティをより豊かで統合されたものへと発達させていく、というのがこのモデルの核心です。
このサイクルを繰り返すことで、アイデンティティは単に元に戻るのではなく、以前よりも豊かで統合されたものへと発達していくのです。中年期の「岐路」は、このラセン式発達における重要な転換点と言えます。

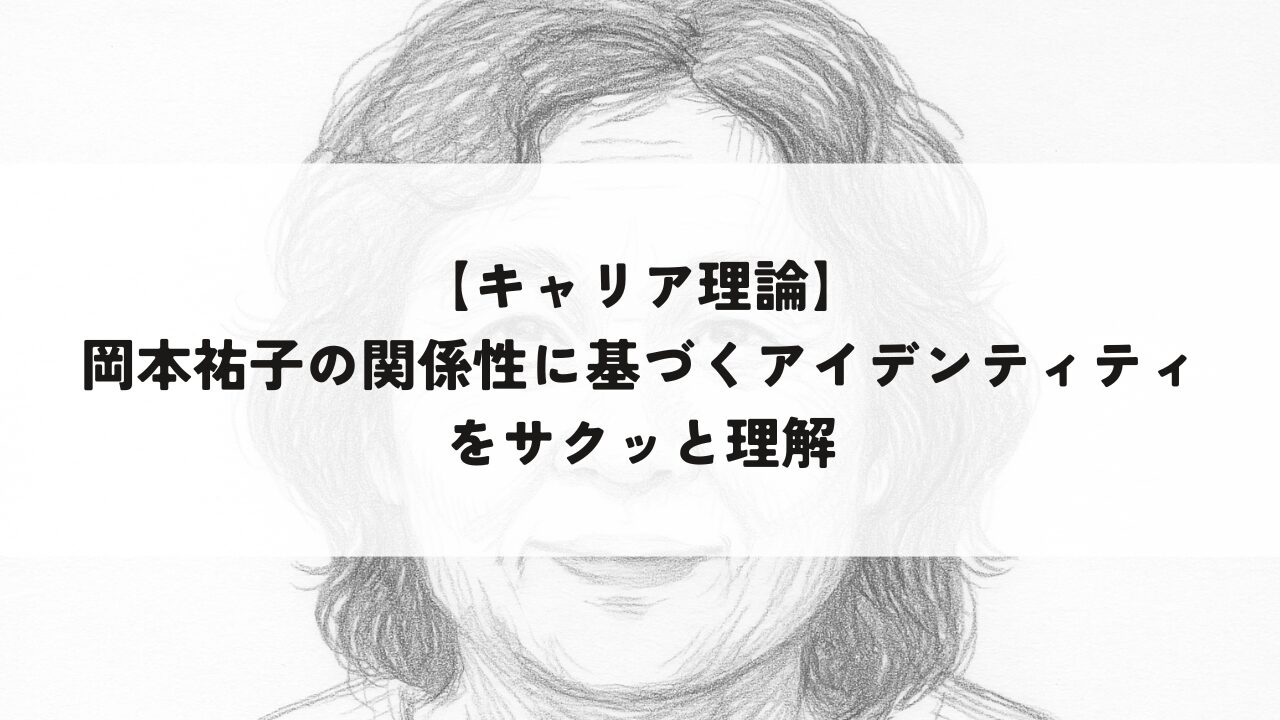
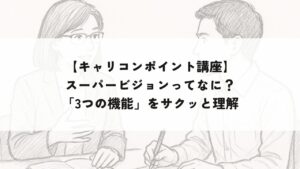
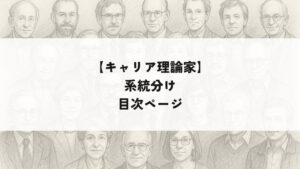

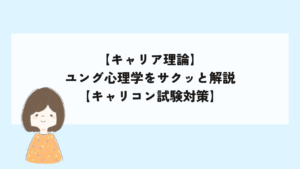
コメント