 チャチャ
チャチャキャリコン試験で出てくる心理療法やアプローチ法ってさ、「どの理論が誰によって提唱されたのか」「それぞれの理論の要点は何だったか」混同しちゃって頭の中が混乱。
この記事では、そんな悩みを抱えるあなたのために、国家資格キャリアコンサルタント試験で問われる可能性のある12の重要な心理療法・アプローチを、試験対策に特化して分かりやすく整理しました。



各理論のポイントをしっかり押さえ、クライエント支援の引き出しを増やすことで、学科試験はもちろん、論述や面接実技試験にも自信を持って臨めるようになります。さあ、一緒に学んでいきましょう!
概要
キャリアコンサルタント試験対策:主要な心理療法・アプローチ一覧
神経症(不安障害)を対象とした日本の精神療法。「あるがまま」の姿勢を重視し、不安や症状を排除しようとせず、そのまま受け入れることを促します。人間の持つ「生の欲望」を発揮させ、建設的な行動に注意を向けることで、症状にとらわれずに生きていくことを目指します。
出来事(A)が直接、結果(C)を引き起こすのではなく、その人の非合理的な信念(イラショナル・ビリーフ)(B)が介在して不適切な結果を生むとする「ABC理論」が中核。この非合理的な信念に論駁(D)し、効果的な信念(E)へ変容させることを目指します。
自己洞察を深めるための日本の心理療法。特定の他者(主に母)に対して「してもらったこと」「して返したこと」「迷惑をかけたこと」という3つの視点で、過去の自分を繰り返し調べる(調身)ことを通じ、自己中心的な考え方に気づき、他者への感謝の念を深めることを目指します。
うつ病の治療理論として開発。現実を否定的に捉える「認知の歪み」と、その背景にある「自動思考」に焦点を当てます。クライエントとの協同作業(コラボレーション)を通じて、自動思考の現実妥当性を検証し、より適応的な考え方ができるように支援します。
自己催眠によるリラクセーション法。「背景公式(気持ちが落ち着いている)」と6つの「公式練習(手足の重感・温感など)」を心の中で繰り返すことで、心身の緊張を解き、自律神経系のバランスを整えます。ストレス緩和や心身症の改善に用いられます。
行動分析学の創始者。ある行動の直後に好ましい結果(強化子)が与えられると、その行動の頻度が増すという「オペラント条件づけ」を提唱。行動の原理を解明し、望ましい行動を形成・維持するための「強化」や、望ましくない行動を減少させる「罰」「消去」などの技法を体系化しました。
不安や恐怖症の治療に用いられる行動療法。「不安とリラクセーションは同時に成り立たない」という「逆制止」の原理を利用します。まずリラクセーション法を習得させ、次に不安を感じる場面を段階的にリスト化した「不安階層表」を作成し、低い段階からリラックス状態でイメージさせることで不安を克服します。
過去の原因探しではなく「現在の行動」に焦点を当てます。人間は「生存」「愛・所属」「力」「自由」「楽しみ」の5つの基本的欲求を満たすために自ら行動を選択しているという「選択理論」が基礎。より効果的な行動を選択し、欲求を満たせるよう支援します。
日本で開発されたグループアプローチ。リーダーが意図的に設定したエクササイズ(課題)を通して、メンバー間の本音の交流を促進し、自己理解、他者理解、自己受容、自己成長を促します。教育現場などで広く活用されています。
カウンセリングを具体的なスキル(技法)の集合体として捉え、一つ一つの技法を階層的にトレーニングする体系的な教育技法。「かかわり行動」「質問」「はげまし」などの技法をまとめた「基本的傾聴の連鎖(BLS)」が有名。カウンセラー養成の基礎として広く用いられています。
ロジャーズの弟子。カウンセリングを「ヘルピング」と呼び、カウンセラーの「共感的理解」「尊重」「純粋性」などの態度が重要であるとしました。これらの技法をマイクロスキルとして体系化し、効果的な援助関係の構築を目指すモデルを提唱しました。
思考のクセと向き合う!認知・現実主義的アプローチ
ここでは、人の感情や行動は、その人の「考え方」や「選択」によって決まると考えるアプローチを見ていきます。クライエントが抱える思考のパターンを理解し、より現実的で建設的な考え方ができるようサポートするための、非常に実践的な理論です。
アルバート・エリス: 論理療法 (REBT)
どんな理論? 1955年に臨床心理学者アルバート・エリスが提唱した、認知行動療法の先駆けともいえるアプローチです 。論理療法の核心は、**「私たちの悩みを引き起こすのは、出来事そのものではなく、その出来事をどう受け止めるかという『信念(ビリーフ)』である」**という考え方にあります 。カウンセラーは、クライエントの非合理的で思い込みの強い信念(イラショナル・ビリーフ)に積極的に働きかけ、より現実的で合理的な考え方ができるよう手助けをします 。
重要キーワード
- イラショナル・ビリーフ (iB): 「~ねばならない」「~べきだ」という断定的な思い込みのこと 。例えば、「常に完璧でなければならない」「誰からも好かれなければならない」といった非現実的な信念が、心理的な問題を引き起こします 。
- ABCDEモデル: 問題を分析し、解決に導くためのフレームワークです 。
- A (Activating Event): 出来事: 問題のきっかけ(例:昇進試験に落ちた) 。
- B (Belief System): 信念: 出来事に対する思い込み(例:「絶対に合格すべきだった。落ちた私は無能だ」) 。
- C (Consequence): 結果: 信念によって引き起こされる感情や行動(例:ひどい落ち込み、退職を考える) 。
- D (Dispute): 論駁(ろんばく): 非合理的な信念(B)に対して、カウンセラーが「その考え方の根拠は?」「そう考え続けるメリットは?」と問いかけ、論理的に反論すること 。
- E (Effect): 効果: 論駁によって、より合理的で健全な考え方と感情を手に入れること(例:「残念だが、この経験を次に活かそう」) 。
キャリア支援での活かし方 キャリアの悩み、特に完璧主義や失敗への過度な恐怖心を持つクライエントに有効です 。例えば、面接に一度落ちただけで「自分はもうダメだ」と思い詰めるクライエントに対し、ABCDEモデルを使って支援します。問題は面接の失敗(A)ではなく、「面接には絶対に成功しなければならない」という信念(B)にあることを示し、その信念に一緒に論駁(D)することで、クライエントが不必要な不安から解放され、粘り強く活動を続けられるようサポートします 。
アーロン・ベック: 認知療法 (CT)
どんな理論? 1960年代に精神科医アーロン・ベックが、うつ病治療のために開発したアプローチです 。ベックは、うつ病の人が持つ特有の悲観的で否定的な思考パターン(認知)に着目し、それを修正することを目指しました 。カウンセラーとクライエントが協力して、クライエントの考えが「事実」なのか、それとも単なる「仮説」なのかを客観的に検証していく「協同的経験主義」が特徴です。
重要キーワード
- 自動思考: ある状況で、瞬間的に頭に浮かぶ考えやイメージのこと。多くは否定的で、吟味されずに事実として受け入れられがちです 。例:上司に少し注意されただけで「私は仕事ができないダメな人間だ」と思ってしまう 。
- 認知の歪み: 「全か無か思考(白黒思考)」や「過度の一般化」など、否定的な考え方を維持させてしまう思考のエラーパターン 。
- スキーマ: 幼少期の経験などから形成される、自分や世界に対する中核的な信念(例:「私は無能だ」) 。
キャリア支援での活かし方 【試験ポイント】 エリスの論理療法が信念の「論理性」に焦点を当て、対決的なアプローチを取るのに対し、ベックの認知療法は思考の「証拠」に焦点を当て、より協同的なアプローチを取る、という違いを明確に理解しておきましょう 。
キャリア支援では、自信のなさから行動できずにいるクライエントに非常に有効です。「自分には能力が足りないから応募できない」という自動思考を持つクライエントに対し、「コラム法(思考記録表)」などを用いて、その考えを裏付ける証拠と、それに反する証拠を一緒に探します 。これにより、クライエントはよりバランスの取れた考え方ができるようになり、新たな一歩を踏み出す勇気を得ることができます 。
ウィリアм・グラッサー: 現実療法
どんな理論? 1960年代に精神科医ウィリアム・グラッサーが創始したアプローチで、「選択理論」に基づいています 。この理論では、私たちの全ての行動は自らの「選択」であり、その目的は生まれながらに持つ「5つの基本的欲求」を満たすためだと考えます。過去の原因を探るのではなく、「今、ここ」で何を選択し、どう行動するかに焦点を当てる、未来志向のセラピーです 。
重要キーワード
- 5つの基本的欲求: 全ての行動の動機となるもの。「生存」「愛と所属」「力」「自由」「楽しみ」 。
- WDEPシステム: 現実療法を実践するための具体的な4ステップの質問プロセスです 。
- W (Wants): 欲求の明確化: 「あなたは本当に何を望んでいますか?」 。
- D (Doing/Direction): 現在の行動の確認: 「その望みを叶えるために、今何をしていますか?」 。
- E (Evaluation): 自己評価: 「今のあなたの行動は、望みを叶える助けになっていますか?」 。
- P (Plan): 計画の立案: 「これから、これまでと違うどんな行動をしますか?」 。
キャリア支援での活かし方 「会社のせい」「上司のせい」と環境に不満を抱えるクライエントに対し、他者を変えるのではなく、自分自身の「選択」と「行動」に焦点を移す手助けをします。WDEPシステムは非常に実践的で、仕事に不満を持つクライエントが、他者への不満を述べる段階から、自分自身の行動計画を立てて主体的に問題解決に取り組む段階へと移行するのを効果的にサポートできます。
行動を変える!行動主義的アプローチ
ここでは、私たちの行動は「学習」によって身についたものだと考えるアプローチを紹介します。問題となる行動を減らし、より望ましい行動を増やしていくための具体的な技法が中心となります。
B.F. スキナー: 行動療法とオペラント条件づけ
どんな理論? 行動主義心理学の代表的人物であるB.F. スキナーが体系化した「オペラント条件づけ」は、現代の行動療法の基礎となっています 。その中心的な考え方は、行動は、その直後に伴う「結果」によってコントロールされるというものです。
重要キーワード
- オペラント条件づけ: ある行動の結果(ご褒美や罰など)によって、その行動が将来起こりやすくなったり、起こりにくくなったりする学習の仕組み 。
- 強化: 行動の頻度を「高める」こと。
- 正の強化: 望ましい行動の後に、良い刺激(褒め言葉、報酬など)を与えること。
- 負の強化: 望ましい行動の後に、嫌な刺激(小言など)を取り除くこと。
キャリア支援での活かし方 就職活動のような、すぐには結果が出にくい長期的な行動のモチベーションを維持するのに役立ちます。例えば、活動を先延ばしにしがちなクライエントに対し、「求人情報を5社調べる」という小さな目標を立て、それが達成できたら「好きなコーヒーを飲む」といった自己報酬(正の強化)を設定するよう助言します。これにより、クライエントは行動を起こしやすくなり、活動を継続できるようになります 。
ジョセフ・ウォルピ: 系統的脱感作法
どんな理論? 1950年代に精神科医ジョセフ・ウォルピが開発した、恐怖症や不安障害に特化した行動療法の技法です 。**「不安とリラックスは同時に存在できない」**という「逆制止」の原理に基づいています 。不安を感じる状況を、リラックスした状態で少しずつイメージすることで、不安反応を弱めていくことを目指します。
重要キーワード
- 逆制止: 不安と相反するリラックス状態を利用して、不安反応を打ち消すこと 。
- 不安階層表: 不安を感じる状況を、最も弱いものから最も強いものまでリストアップし、段階付けしたもの 。
キャリア支援での活かし方 面接やプレゼンテーションなど、特定の状況に強い不安を感じるクライエントに非常に有効です。まず、漸進的筋弛緩法などのリラクセーション法を習得してもらいます。次に、クライエントと一緒に「面接に関する不安階層表」(例:求人票を見る→書類を送る→電話面接→対面面接)を作成します。そして、リラックスした状態で、不安階層表の最も弱い段階から順にイメージしてもらう、というプロセスを繰り返すことで、体系的に不安を克服する手助けができます 。
日本生まれの心理療法:受け入れることの力
ここでは、西洋の心理学とは異なる、東洋的な哲学を背景に持つ日本独自の心理療法を紹介します。症状を取り除くのではなく、「あるがまま」に受け入れるという視点が特徴です。
森田正馬: 森田療法
どんな理論? 20世紀初頭に精神科医の森田正馬によって創始された、不安障害(神経質)に対する日本独自の治療法です 。治療の目的は、不安や恐怖といった症状を消し去ることではありません。むしろ、不安を自然な感情として「あるがまま」に受け入れ、症状にとらわれず、今やるべきことに集中することで、建設的な生活を送れるようになることを目指します 。
重要キーワード
- あるがまま: 不安や不快な感情を、無理になくそうとせず、そのままに受け入れる態度 。
- 生の欲望: 人間が本来持っている「よりよく生きたい」というポジティブなエネルギー 。
- 精神交互作用: 症状に注意を向ければ向けるほど、その感覚が鋭敏になり、さらに注意が固着してしまう悪循環 。
- 目的本位の行動 / なすべきをなす: 感情がどうであれ、今ここでやるべき建設的な行動に集中すること 。
キャリア支援での活かし方 「不安がなくなるまで、就職活動を始められません」と訴えるクライエントに、森田療法の考え方は大きな助けとなります。「不安な気持ちはそのままに、まずはその不安を感じながら、今日できる小さな一歩(例えば、求人サイトを開いてみるだけ)を踏み出してみませんか?」と働きかけます。行動することで、自信や満足感は後からついてくる、という視点を提供し、行動の第一歩を後押しします 。
吉本伊信: 内観療法
どんな理論? 浄土真宗の信仰者であった吉本伊信によって創始された、構造化された自己内省法です 。母親など、身近な他者との関係を、以下の3つの問いだけを使って振り返ることで、自己中心的な視点から抜け出し、感謝の念を育むことを目的とします。
重要キーワード
- 内観三項目:
- してもらったこと
- して返したこと
- 迷惑をかけたこと (※「迷惑をかけられたこと」という問いが意図的に外されている点がポイントです)
キャリア支援での活かし方 職場での人間関係に悩み、「自分は正当に評価されていない」といった被害者意識を持つクライエントに、新たな視点を提供できます。もちろん、クライエントの辛い気持ちを否定するわけではありません。その上で、「少し視点を変えて、今の上司から『してもらったこと』は何がありますか?」といった内観的な問いかけをすることで、関係性をより多角的・客観的に捉え直す手助けができます。これにより、クライエントはより冷静な判断を下せるようになります 。
カウンセリングの土台を作る!統合的・スキルベースのアプローチ
ここでは、特定の理論に偏るのではなく、様々なアプローチの良いところを統合し、カウンセリングの具体的な進め方やスキルを体系化したモデルを紹介します。
アレン・アイビィ: マイクロカウンセリング
どんな理論? 1960年代にアレン・アイビィが開発した、カウンセラーのためのトレーニング技法です 。複雑なカウンセリングのプロセスを、具体的で習得可能なスキルに分解し、ピラミッド状の階層で整理しました。多様なカウンセリング理論に共通する技法を体系化した「メタモデル」とされています 。
重要キーワード
- マイクロ技法の階層表:
- レベル1: かかわり行動: 視線、姿勢、声の調子など、傾聴の土台となる非言語的スキル 。
- レベル2: かかわり技法: 開かれた質問、言い換え、感情の反映、要約など、話を深めるための基本的な言語的スキル 。
- レベル3: 積極技法: 指示、解釈、自己開示、対決など、クライエントの行動変容を促すための、より積極的なスキル 。
キャリア支援での活かし方 キャリアコンサルタントにとって、まさに「基本の型」です。特に、面接実技試験では、これらの技法を意識的に使い分けることが求められます。例えば、面談の序盤では「かかわり行動」や「かかわり技法」で信頼関係を築き、クライエントが意思決定に迷っている場面では、「積極技法」の一つである「論理的帰結」を用いて、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを一緒に検討する、といったように、面談のプロセス全体を構造的に組み立てるための羅針盤となります 。
ロバート・カーカフ: ヘルピング技法
どんな理論? カール・ロジャーズの弟子であるロバート・カーカフが提唱した、統合的・段階的なアプローチです 。来談者中心療法のような非指示的なアプローチと、行動療法のような指示的なアプローチを統合している点が特徴です 。カウンセリングを、クライエント(ヘルピー)が「現在地」から望ましい「目的地」へと旅するのを、カウンセラー(ヘルパー)が支援するプロセスとして捉えます 。
重要キーワード
- ヘルピングの段階:
- 事前段階: かかわり技法: 信頼関係を築く。
- 第一段階: 応答技法: クライエントが自己を探求し、「現在地」を明らかにするのを助ける。
- 第二段階: 意識化技法: クライエントが「目的地(どうなりたいか)」を理解するのを助ける。
- 第三段階: 手ほどき技法: 「現在地」から「目的地」へ至るための具体的な行動計画を立てる 。
キャリア支援での活かし方 キャリアカウンセリングのプロセスそのものを表す、非常に分かりやすいモデルです。キャリアの方向性に悩むクライエント(現在地が不明確)に対し、まずは応答技法でじっくりと話を聞き、価値観や興味を探ります。次に意識化技法で理想のキャリア像(目的地)を一緒に描き、最後にてほどき技法で、その理想を実現するための具体的なアクションプラン(履歴書作成、情報収集など)を立てていきます 。
國分康孝: コーヒーカップモデルと構成的グループエンカウンター
どんな理論? 日本のカウンセリング界を代表する國分康孝が提唱した、実践的で分かりやすいモデルです。
重要キーワード
- コーヒーカップモデル: カウンセリングのプロセスをコーヒーカップに例えたもの。安定した「受け皿」がカウンセラーとクライエントの信頼関係(リレーション)を表し、その上に乗る「カップ」が問題解決のプロセスを表します。どんなに優れた技法(カップ)も、安定した信頼関係(受け皿)がなければ成り立たない、ということを示しています 。
- 構成的グループエンカウンター (SGE): 國分が開発したグループアプローチ。リーダーが明確なルールや手順(エクササイズ)を用意することで、参加者が安全な環境で本音のふれあい(エンカウンター)を体験し、自己理解や他者理解を深めることを目指します 。
キャリア支援での活かし方 コーヒーカップモデルは、何よりもまずクライエントとの信頼関係構築が最優先である、というカウンセリングの基本姿勢を常に思い出させてくれます。また、SGEは、グループ形式のキャリア研修などで非常に有効です。「ライフラインチャートを描く」などのエクササイズを用いることで、参加者が楽しみながら自己分析を深め、相互に学び合う場を作ることができます 。
心と体を整える!自己調整と動機づけのアプローチ
ここでは、ストレスを自分で管理するためのリラクセーション技法と、仕事のモチベーションがどこから来るのかを理解するための理論を紹介します。
J.H. シュルツ: 自律訓練法 (AT)
どんな理論? 1930年代にドイツの精神科医シュルツが開発した、自己催眠を利用したリラクセーション技法です 。決まった言葉(公式)を心の中で繰り返すことで、心と体の緊張を自分で解きほぐし、深いリラックス状態に導きます 。
重要キーワード
- 標準練習の公式:
- 背景公式: 「気持ちがとても落ち着いている」
- 第1公式: 「両腕・両脚が重たい」(重感練習)
- 第2公式: 「両腕・両脚が温かい」(温感練習)…など、段階的に練習を進めます 。
- 消去動作: 練習の終わりには、手足を曲げ伸ばしするなどして、しっかりと覚醒状態に戻ることが重要です 。
キャリア支援での活かし方 面接前の緊張や、仕事のプレッシャーによるストレスを抱えるクライエントに、自分でできるストレスマネジメントのスキルとして教えることができます。クライエントがセルフケア能力を高め、落ち着いて物事に取り組めるよう支援する、実践的なツールとなります 。
フレデリック・ハーズバーグ: 二要因理論
どんな理論? 1959年に心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱した、職場のモチベーションに関する理論です 。この理論の最も重要なポイントは、仕事の「満足」に関わる要因と、「不満足」に関わる要因は、全く別の種類のものである、という点です。
重要キーワード
- 衛生要因: これが満たされないと「不満足」になるが、満たされても「満足」にはつながらず、「不満がない」状態になるだけ。会社の制度、給与、人間関係、労働条件などがこれにあたります 。
- 動機づけ要因: これが満たされると「満足」につながる要因。達成感、承認、仕事そのものの面白さ、責任、成長などがこれにあたります 。
キャリア支援での活かし方 「今の仕事に不満がある」というクライエントの悩みを分析するための強力なツールとなります。その不満の原因は、給与や人間関係といった「衛生要因」なのか、それとも仕事のやりがいや成長実感といった「動機づけ要因」の欠如なのかを切り分けて考えます。もしクライエントが衛生要因(例:給与)の改善だけを求めて転職しても、動機づけ要因が満たされなければ、また同じような不満を抱える可能性があります。クライエントが長期的なキャリア満足を得るために、本当に大切にしたい「動機づけ要因」は何かを一緒に見つけていくことが重要です 。
まとめ:理論を力に、最適な支援を
ここまで、12の重要な心理療法・アプローチを見てきました。一つひとつの理論は、クライエントを理解するための「レンズ」のようなものです。優れたキャリアコンサルタントは、一つのレンズに固執するのではなく、クライエントの状況に応じて、これらのレンズを柔軟に使い分け、統合していきます。
例えば、まずはマイクロカウンセリングの技法で信頼関係を築き、クライエントが抱える否定的な思い込みには認知療法の視点でアプローチし、具体的な行動計画を立てる際には現実療法のWDEPシステムを活用する、といった形です。
試験対策としては、以下の総括表を活用して、各理論の提唱者、キーワード、そしてキャリア支援への応用例をセットで覚えておくと、知識が整理しやすくなります。
理論の学習は、単なる試験対策に留まりません。それは、多様な悩みを持つクライエント一人ひとりに寄り添い、根拠に基づいた質の高い支援を提供するための、私たち専門家にとっての不可欠な土台となるのです。
主要心理療法・アプローチ総括表
| 理論/アプローチ (Theory/Approach) | 提唱者 (Proponent) | 中核概念 (Core Concept) | 主要モデル/技法 (Key Model/Technique) | キャリアカウンセリングへの応用例 |
| 論理療法 (REBT) | アルバート・エリス | 非合理的な信念(iB)が情緒的混乱を引き起こす。 | ABCDEモデル、論駁(Dispute) | 面接に落ちて「自分は無価値だ」と思い込むクライエントに対し、その信念の非論理性を論駁し、より現実的な捉え方を促す。 |
| 認知療法 (CT) | アーロン・ベック | 自動思考、認知の歪み、スキーマが感情や行動を規定する。 | 協同的経験主義、コラム法、ソクラテス的対話 | 「自分は期待されていない」という自動思考を持つクライエントと共に、その考えを支持・反証する証拠を検討し、思考のバランスを取る。 |
| 現実療法 (Reality Therapy) | ウィリアム・グラッサー | 全ての行動は5つの基本的欲求を満たすための選択である。 | 選択理論、WDEPシステム | 仕事に不満なクライエントに「本当に望むこと(W)」「現在の行動(D)」「その有効性(E)」を問い、具体的な行動計画(P)を立てる。 |
| 行動療法 (Behavior Therapy) | B.F. スキナー | 行動は結果(強化・罰)によって学習・維持される。 | オペラント条件づけ、行動変容技法 | 転職活動を先延ばしにするクライエントに対し、小さな行動(求人1件検索)ごとに自己報酬を与えるシステムを作り、行動を強化する。 |
| 系統的脱感作法 | ジョセフ・ウォルピ | 不安とリラクセーションは両立しない(逆制止)。 | 不安階層表、リラクセーション訓練 | プレゼン恐怖症のクライエントに、リラックス状態で徐々に不安度の高い場面を想像させ、不安反応を消去していく。 |
| 森田療法 (Morita Therapy) | 森田正馬 | 不安を「あるがまま」に受け入れ、目的本位の行動を行う。 | あるがまま、生の欲望、なすべきをなす | 「自信がつくまで待つ」クライエントに、不安を抱えたままでも目標達成のための具体的な行動(情報収集など)を始めるよう促す。 |
| 内観療法 (Naikan Therapy) | 吉本伊信 | 他者との関係を3つの問いで内省し、自己中心性から脱却する。 | 内観三項目(してもらったこと、して返したこと、迷惑をかけたこと) | 上司への不満が強いクライエントに、視点を変えて上司から受けた恩恵や自身の貢献を振り返らせ、関係性を多角的に捉え直す。 |
| マイクロカウンセリング | アレン・アイビィ | カウンセリングは階層的な具体的スキル群から構成される。 | マイクロ技法の階層表(かかわり行動、かかわり技法、積極技法) | 面接のロールプレイングで、傾聴(感情の反映、要約)から働きかけ(フィードバック、対決)まで、体系的なスキルを実践する。 |
| ヘルピング技法 | ロバート・カーカフ | 援助は「現在地」から「目的地」への旅を支援するプロセス。 | ヘルピングの段階(かかわり、応答、意識化、手ほどき) | キャリアの方向性に悩むクライエントの現状(現在地)を共に探り、理想の姿(目的地)を描き、そこへ至る行動計画を立てる。 |
| コーヒーカップモデル | 國分康孝 | 安定した関係性(受け皿)が問題解決(カップ)の土台となる。 | コーヒーカップモデル、カウンセラーの4つの人間性 | どのような技法を用いるにせよ、まずクライエントとの信頼関係(受け皿)の構築を最優先し、面談の安定した基盤を作る。 |
| 自律訓練法 (AT) | J.H. シュルツ | 言語公式を用いた自己催眠により、心身の深い弛緩を導く。 | 標準練習の6公式(重感、温感など) | 面接前など、強いストレスを感じるクライエントに、不安を自己管理するための実践的なリラクセーションスキルとして教える。 |
| 二要因理論 | フレデリック・ハーズバーグ | 仕事の満足(動機づけ要因)と不満足(衛生要因)は別次元。 | 動機づけ要因と衛生要因の区別 | 「給料が低い」と訴えるクライエントに、不満の原因(衛生要因)だけでなく、真の満足(動機づけ要因:成長、承認など)は何かを探る。 |


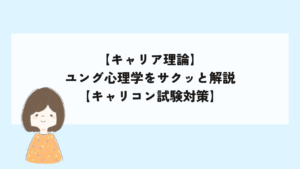

コメント