今回は、多くの受験生が知識の整理に苦労する「中高齢期のキャリア」に関する理論を特集します。
このライフステージは、キャリアの安定と同時に、大きな変化や転機(トランジション)が訪れやすい時期です。だからこそ、試験でもその支援に関する知識が問われます。
今回は、数ある理論の中から特に重要な理論家をピックアップし、「試験に出るポイント」をわかりやすく解説します!
インタラクティブ学習版
年代別タイムライン
各理論家が提唱する年代別の発達段階や転機を視覚的に比較します。
インタラクティブ比較
比較したい理論家を選択して、キーワードや視点を並べて確認できます。
1.ドナルド・スーパー(D. Super):キャリアは一生涯発達する
スーパーの理論はキャリア理論の王道ですが、中高年期を理解する上でも欠かせません。
[中高年の男女が話し合っている様子の画像]
理論の概要
スーパーは、キャリアを「生涯にわたるプロセス(ライフスパン)」と「様々な役割の組み合わせ(ライフスペース)」で捉えました。人のキャリアは、若い頃に選択して終わりではなく、一生涯をかけて発達・変化していくと考えたのです。
試験に出る!重要ポイント
中高年期に該当するのは、主に以下の2つの発達段階です。
- 維持段階(Maintenance Stage):45歳〜65歳頃
- 確立したキャリアや地位を「維持」しようとする時期。
- 安定している一方で、技術革新や組織の変化により、自身の知識やスキルの陳腐化に直面することも。
- キーワード:
安定、更新、停滞
- 解放段階(Disengagement Stage):65歳以降
- かつては「衰退段階」と呼ばれていましたが、現在はよりポジティブな捉え方がされています。
- 仕事中心の生活から解放され、新しい役割や活動に関心を移していく時期。
- キーワード:
引退、役割変化、ワーク・ライフ・バランスの再構築
✅ここを覚えよう! スーパーの理論で問われるのは、各段階の名称とその特徴です。特に「維持段階」の課題と、「解放段階」がポジティブな意味合いで使われる点を押さえましょう。
2.ダニエル・レビンソン(D. Levinson):人生の四季と転機
レビンソンは、人の生涯を「四季」にたとえ、安定期と過渡期(転機)を繰り返しながら発達すると考えました。
理論の概要
人の生涯は、成人前期、成人中期、成人後期という大きな発達期で構成され、それぞれの間に「転機」と呼ばれる移行期が存在すると提唱しました。特に「人生半ばの転機」は非常に重要です。
試験に出る!重要ポイント
中高年期を理解する上で、絶対に外せないのが「人生半ばの転機」です。
- 人生半ばの転機(Mid-life Transition):40歳〜45歳頃
- これまでの人生(生活構造)を見直し、人生の後半に向けて修正を行う重要な時期。
- 「本当にこのままで良いのか?」という問いに直面し、キャリアや生き方そのものを問い直します。
- この転機を乗り越えることで、より統合された「成人中期」の安定した生活構造を築くことができます。
- キーワード:
生活構造の見直し、中年期の危機、アイデンティティの再構築
✅ここを覚えよう! レビンソンといえば「人生半ばの転機」と「生活構造」です。40歳〜45歳という具体的な年齢と、そこで何が行われるのか(人生の見直し)をセットで記憶してください。
3.エリク・エリクソン(E. Erikson):世代継承性と停滞
エリクソンの心理社会的発達理論も、人の生涯を見通す上で非常に重要です。
[ベテラン社員が若手社員に指導している様子の画像]
理論の概要
エリクソンは、人の一生を8つの発達段階に分け、各段階で乗り越えるべき心理社会的な「危機(発達課題)」があるとしました。この課題を乗り越えることで、人は健全な自我(アイデンティティ)を発達させていきます。
試験に出る!重要ポイント
中高年期(成人期)に該当するのが、7番目の発達段階です。
- 第7段階:世代継承性 vs 停滞(Generativity vs. Stagnation):40歳〜65歳頃
- この時期の課題は、次の世代のために何かを生み出し、貢献することです。
- 世代継承性(生産性): 子育て、後進の指導、 mentoring、地域社会への貢献など、自分以外のもののために尽くすこと。これを達成することで、人は満足感やケアの感覚を得ます。
- 停滞: 次世代への関心が持てず、自分のことばかりに興味が向かってしまう状態。生産的な活動が見出せないと、孤立感や虚しさを感じやすくなります。
- キーワード:
世代継承性(生産性)、停滞、次世代育成、貢献
✅ここを覚えよう! エリクソンの中高年期は「世代継承性 vs 停滞」の葛藤です。キャリアの文脈では、「後輩を育てる」「培った技術や知識を伝承する」といった役割が、この発達課題を乗り越える上で重要になります。
4.ロバート・ハヴィガースト(R. Havighurst):乗り越えるべき「発達課題」
ハヴィガーストは、各ライフステージで達成すべき「発達課題」があると考えました。
理論の概要
発達課題とは、個人の成長と社会からの期待によって生じる課題のことです。その課題を達成することで、人は幸福感を得て、次のステージへとうまく移行できるとしました。
試験に出る!重要ポイント
中高年期に相当する「壮年期(30〜60歳頃)」の主な発達課題を見てみましょう。キャリアに関連する項目が多く含まれます。
- 壮年期の発達課題
- 一人前の大人としての市民的・社会的責任を果たす
- 経済的な生活水準を確立し、維持する
- 10代の子どもが責任ある大人になれるように援助する
- 配偶者と人格的な関係を築く
- 中年期における生理的変化を受け入れ、適応する
- 老いていく親に適応する
✅ここを覚えよう! ハヴィガースト=「発達課題」です。特に壮年期では、仕事上の役割(経済的安定)だけでなく、親・子・配偶者との関係、社会的な責任など、多岐にわたる課題に直面する点を押さえましょう。
5.エドガー・シャイン(E. Schein):自分を突き動かすキャリア・アンカー
シャインの理論は、個人の内的なキャリア観に焦点を当てます。
理論の概要
キャリア・アンカーとは、個人がキャリアを選択する際に、最も大切で、どうしても譲れない価値観や欲求のことです。様々な経験を通じて自己理解が深まる成人中期(30代〜40代)に形成されると言われています。
試験に出る!重要ポイント
中高年期のキャリア相談では、クライエントが自身のキャリア・アンカーに気づき、それを軸に今後のキャリアを考える支援が求められます。
- キャリア・アンカーの8つの分類
- 専門・職能別コンピテンス
- 全般管理コンピテンス
- 自律・独立
- 保障・安定
- 起業家的創造性
- 奉仕・社会貢献
- 純粋な挑戦
- 生活様式(ライフスタイル)
✅ここを覚えよう! シャイン=「キャリア・アンカー」と、8つの分類の名称を覚えておくことが重要です。特に「生活様式(ライフスタイル)」など、仕事だけでなく人生全体のバランスを重視するアンカーがある点を理解しておきましょう。
6.ナンシー・シュロスバーグ(N. Schlossberg):転機はプロセスで乗り越える
シュロスバーグは、キャリアにおける「転機(トランジション)」を乗り越えるためのフレームワークを提唱しました。
理論の概要
彼女の理論は、「何歳で何が起こるか」というステージ理論ではなく、転機が起きたときに、それをどう乗り越えるかというプロセスに焦点を当てています。そのため、年代を問わず活用できますが、特に変化の多い中高年期の支援に有効です。
試験に出る!重要ポイント
転機を乗り越えるために評価すべき資源として「4Sモデル」を提唱しました。
- 4Sモデル
- Situation(状況): 転機の深刻度、タイミング、影響範囲などを評価する。
- Self(自己): 自身の性格、価値観、過去の転機経験などを評価する。
- Support(支援): 家族、友人、同僚、専門家など、利用できるサポートを評価する。
- Strategies(戦略): 状況を変えるための行動戦略、意味づけを変える認知戦略など、具体的な対処法を評価する。
✅ここを覚えよう! シュロスバーグ=「転機(トランジション)」と「4Sモデル」です。4つのSがそれぞれ何を指すのかを正確に答えられるようにしておきましょう。
7.岡本祐子:日本人女性の「キャリアの転機」
岡本祐子は、日本の働く女性の中年期に焦点を当て、そのキャリアの転機について研究しました。
[カフェで話し込む女性二人組の画像]
理論の概要
40歳前後の働く女性が経験するキャリア・ミッドライフ・トランジションについて、そのきっかけと乗り越えていくプロセスを4段階で示しました。子育てや介護など、日本の女性が直面しやすい状況が反映されています。
試験に出る!重要ポイント
転機を乗り越えるプロセスである4つの段階が特に重要です。
- キャリア・ミッドライフ・トランジションの4段階
- 気づきと揺らぎの時期: これまでの生き方への違和感や漠然とした不安を感じる。
- 手探りと模索の時期: 資格取得を考えたり、情報収集をしたりと、方向性が定まらないまま試行錯誤する。
- 自分なりの方向性を見出す時期: 模索の中から、自分らしいキャリアや生き方の軸を見つける。
- 新たな自分として歩み出す時期: 見出した方向性に向かって具体的な一歩を踏み出し、新しいアイデンティティを確立していく。
✅ここを覚えよう! 岡本祐子=「日本人女性」「キャリア・ミッドライフ・トランジション」「4段階のプロセス」です。レビンソンの転機が普遍的なものであるのに対し、より日本の文化的背景に根ざした理論として理解しましょう。
まとめ:各理論の視点を比較しよう
最後に、今回取り上げた理論家の視点を簡単に整理します。
| 理論家 | キーワード | 中高年期への視点 |
|---|---|---|
| スーパー | ライフスパン、発達段階 | キャリアを維持し、やがて仕事から解放されていく人生の大きな流れ |
| レビンソン | 人生の四季、生活構造 | 人生半ばの転機で過去を問い直し、新たな人生の構造を作る時期 |
| エリクソン | 世代継承性、停滞 | 次世代への貢献(育成や指導)を通じて発達課題を乗り越える時期 |
| ハヴィガースト | 発達課題 | 社会や家庭の中で求められる多様な役割・課題を達成していく時期 |
| シャイン | キャリア・アンカー | 経験を通じて確立された譲れない価値観を再確認し、キャリア選択の軸とする |
| シュロスバーグ | 転機(トランジション)、4S | 予期せぬ出来事も含め、様々な転機を乗り越えるための資源を評価するプロセス |
いかがでしたか? 中高年期のキャリアは、これまでの経験の「維持」だけでなく、新たな「問い直し」や「転機」に満ちています。これらの理論を横断的に理解し、クライエントの状況に合わせて活用できる視点を持つことが、キャリアコンサルタントには求められます。
試験勉強、応援しています!

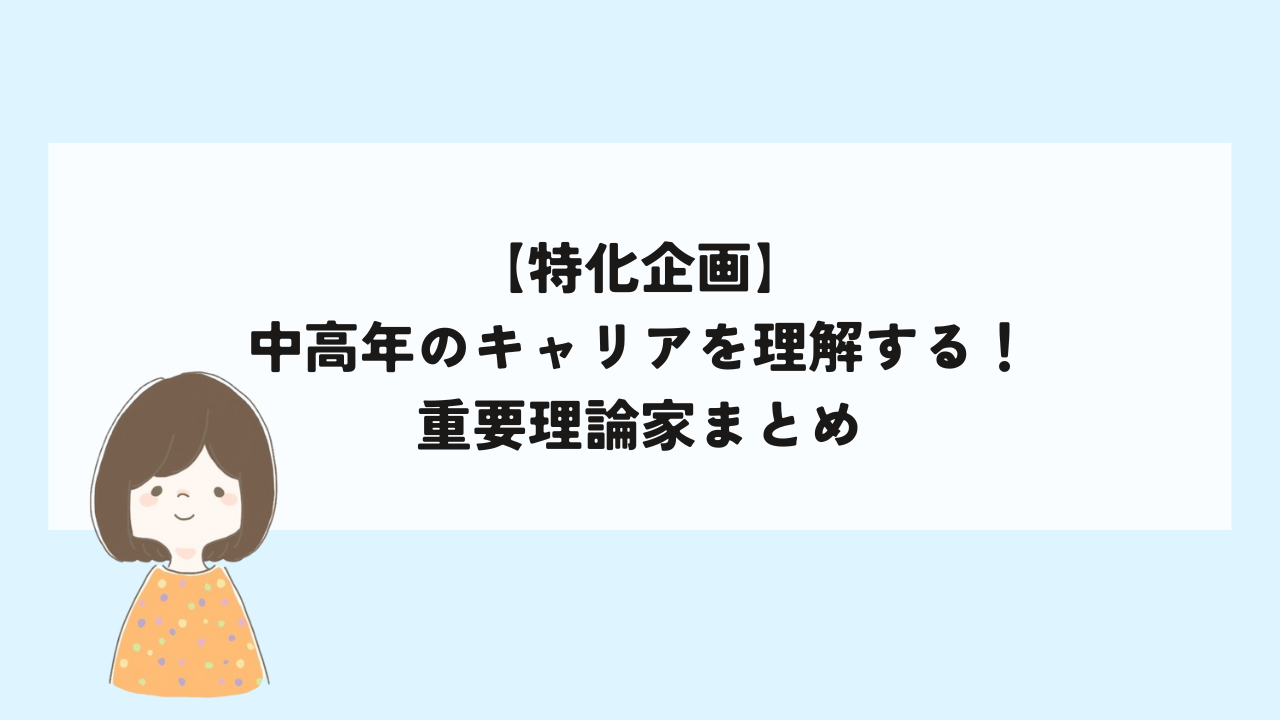
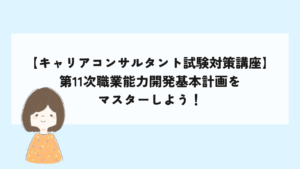


コメント