 チャチャ
チャチャ「パートタイム・有期雇用労働法」、いわゆる「同一労働同一賃金」の原則は、働き方の多様化が進む現代において非常に重要なテーマ。
「このテーマ、今後も試験に出るの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
答えは「YES」。 これは単なる法律知識にとどまらず、キャリアコンサルタントとして実務を行う上での必須知識だからです。



今回は、この「同一労働同一賃金」について、試験で問われる重要ポイントを、過去問の選択肢を分解しながら分かりやすく解説していきます。
そもそも「同一労働同一賃金」とは?
この原則の目的は、同じ企業で働く「通常の労働者(正社員)」と「パートタイム・有期雇用労働者(非正規社員)」との間の不合理な待遇差をなくすことです。
ポイントは「不合理な」という部分です。仕事内容や責任、転勤の有無などが違えば、待遇に差があること自体は問題ありません。
しかし、その違いを考慮しても「それはおかしい」と言えるような、説明のつかない格差は許されない、ということです。
【ポイント1】規制の対象は「すべての待遇」
(NG例) 法律上の規制範囲は、基本給と賞与の決定に限定される。
これは典型的なひっかけ問題です。
同一労働同一賃金の原則が対象とするのは、基本給や賞与といった金銭だけではありません。
- 基本給、賞与、各種手当(通勤手当、家族手当、住宅手当など)
- 福利厚生(食堂の利用、社宅、慶弔休暇など)
- 教育訓練(研修への参加機会など)
これら**「すべての待遇」**について、不合理な差を設けることが禁止されています。
【ポイント2】「均衡待遇」と「均等待遇」の考え方
この原則には、2つの重要な考え方があります。
- 均等待遇(差別的取扱いの禁止)職務内容や責任の程度、配置転換の範囲などが「同じ」場合、待遇も「同じ」にしなければなりません。
- 均衡待遇(不合理な待遇差の禁止)職務内容などに「違いがある」場合、その「違いに応じた範囲」で待遇に差を設けることは許されます。しかし、その違いを考慮しても不合理(説明がつかないほど大きい)な格差は違法となります。
【ポイント3】職務給(ジョブ型雇用)の導入は義務ではない
(NG例) 職務の内容や責任の程度が同一であれば賃金を同一とする、職務給制度の導入が義務付けられている。
「仕事内容が同じなら給料も同じ」という考え方は、職務給(ジョブ型雇用)に近いものです。しかし、この法律は、企業に対して特定の賃金制度(例:職務給)の導入を義務付けるものではありません。
あくまで、各企業が自社の賃金制度の中で、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を解消することを求めています。
【ポイント4】法律の適用範囲と「民法」の役割
パートタイム・有期雇用労働法が直接規制しているのは、あくまで「正社員 vs 非正規社員」の間の格差です。



じゃあ、「正社員同士」や「契約社員同士」の間の格差はどうなるの?
この法律は「正社員同士」や「契約社員同士」の間には直接適用されません。



しかし、だからといってどんな格差も許されるわけではありません。
あまりにも格差が大きく、社会の常識から見て著しく不公平である場合、民法上の「公序良俗違反(民法90条)」などにより、その待遇差が違法・無効と判断される可能性があるのです。
これは、特定の法律に規定がなくても、より大きな法秩序の観点から個人の権利を守るという考え方に基づいています。
まとめ



「同一労働同一賃金」を理解するための鍵は以下の4点です。
- 対象は給与だけでなく「すべての待遇」
- 「違い」があるなら「違いに応じた」待遇差はOK(均衡待遇)
- 特定の賃金制度(職務給など)の導入は義務ではない
- 法律の適用外(正社員間など)でも、民法で違法になるケースがある
このテーマは、相談者の権利を守り、企業の健全な発展を支援するキャリアコンサルタントにとって、避けては通れない知識。
試験対策としてだけでなく、将来の実務のためにも、しっかりとマスターしておきましょう!

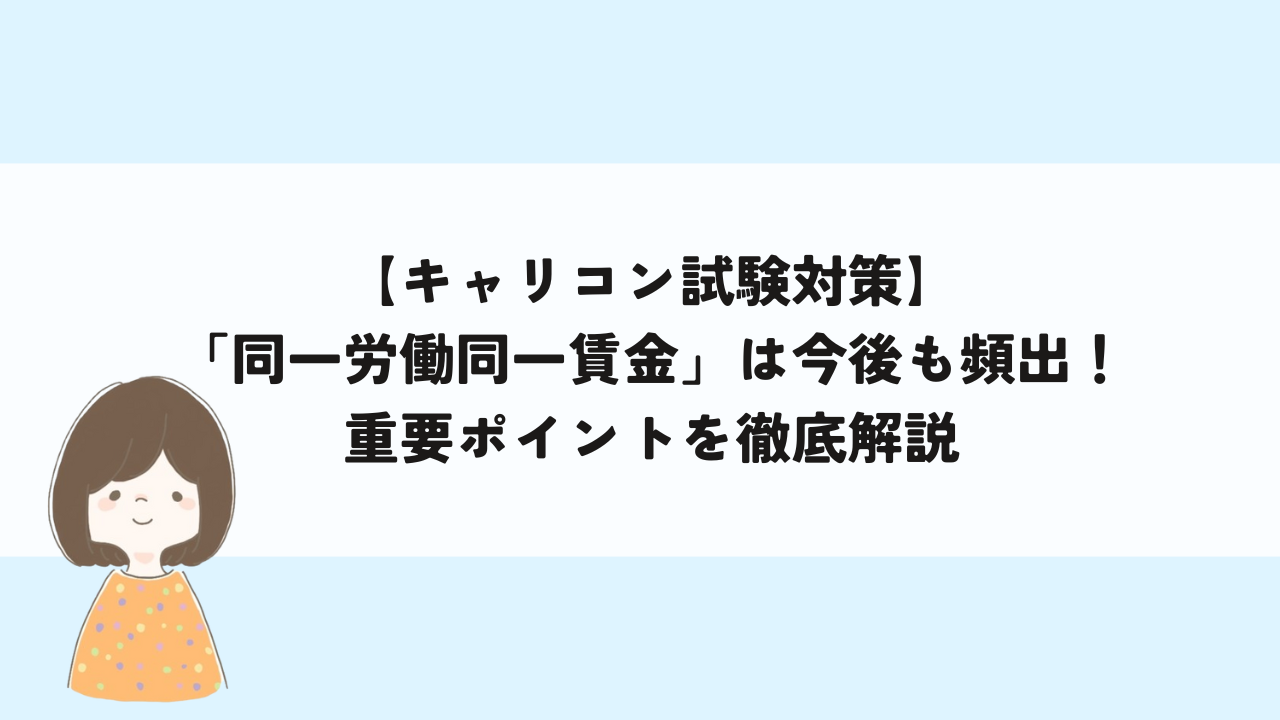
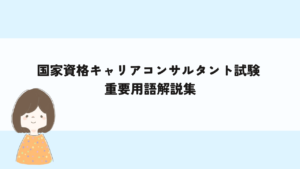
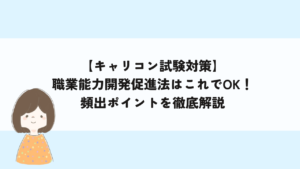

コメント