 チャチャ
チャチャカウンセリング技法たくさんあって覚えられない…それぞれの違いがよくわからない…
キャリアコンサルタント国家試験の学習、順調に進んでいますか? 学科試験でも実技試験でも、カウンセリングの基本となる「技法」の理解は避けては通れない最重要項目です。
この記事では試験に頻出のカウンセリング技法に絞って、その目的や使い方を具体例とともに徹底的に解説します。



一つひとつ丁寧に理解すれば、きっと得意分野になりますよ!
インタラクティブ学習版
頻出カウンセリング技法を学ぶ
キャリアコンサルタント国家試験の合格には、カウンセリング技法の深い理解が不可欠です。このアプリは、試験に頻出する技法を効率的に学習するために作られました。
カウンセリング技法の基本:「マイクロカウンセリング技法」
これから紹介する技法の多くは、マイクロカウンセリング技法に基づいています。これは、カウンセリングを構成する個々のスキルを分解し、トレーニングしやすくしたものです。左のメニューから学習したい技法を選んで、理解を深めていきましょう。
カウンセリング技法の基本:「マイクロカウンセリング技法」
これから紹介する技法の多くは、マイクロカウンセリング技法(マイクロギル・カウンセリング)に基づいています。これは、カウンセリングを構成する個々のスキルを分解し、トレーニングしやすくしたものです。まずは、その中でも特に基本的な「かかわり行動」と「傾聴」から見ていきましょう。
1. かかわり行動(Attending Behavior)
カウンセリングの土台中の土台です。相談者が安心して話せるような雰囲気を作るための、カウンセラーの非言語的な態度や行動を指します。
- 視線の合わせ方: 威圧的にならないよう、柔らかく自然に視線を合わせる。
- 身体言語: 少し前傾姿勢で、リラックスした態度を示す。腕や足を組まない。
- 声の調子: 相談者の声のトーンや話すペースに合わせる。
- 言語的追跡: 話が逸れないように、相談者のテーマに沿って応答する。
これらができているだけで、相談者は「この人は真剣に話を聴いてくれている」と感じ、信頼関係(ラポール)が築きやすくなります。
2. 傾聴(Active Listening)
ただ耳で聞くのではなく、相手の伝えたいこと(言葉の内容、感情、価値観など)を深く理解しようと、全身で真摯に耳を傾ける姿勢のことです。これから紹介する多くの技法は、この傾聴の姿勢を具体化したものと言えます。
【超頻出】応答の基本技法5選
ここからは、実際のカウンセリング場面での応答で使われる具体的な技法です。学科試験では「この応答で使われている技法は何か」という形で問われることが多いです。
3. 感情の反映(Reflection of Feeling)
相談者の言葉の背後にある感情をカウンセラーが言葉にして返す技法です。相談者は自分の気持ちを客観的に認識でき、「感情を理解してもらえた」と感じることができます。
CL(相談者): 「新しいプロジェクトリーダーに任命されたんですが、正直、自分に務まるのか、夜も眠れないくらいなんです…。」 CC(キャリアコンサルタント): 「大きな役割を任されて、期待に応えたい気持ちと同時に、大きなプレッシャーで不安を感じていらっしゃるのですね。」
【ポイント】 「〜と感じていらっしゃるのですね」「〜というお気持ちなのですね」といった形で返します。断定するのではなく、あくまで「そのように感じ取れました」というニュアンスで伝えるのが大切です。
4. 言い換え(Paraphrasing)
相談者が話した事実や内容を、カウンセラーが別の言葉で要約して返す技法です。相談者は「話を正確に理解してもらえた」と感じ、自分の考えを整理することができます。
CL(相談者): 「今の仕事は残業も多いし、休日も呼び出されることがある。給料は悪くないけど、このままでいいのかって思うんです。」 CC(キャリアコンサルタント): 「お給料には満足しているけれど、労働時間が長く、プライベートとのバランスに疑問を感じていらっしゃる、ということですね。」
【ポイント】 感情の反映が「気持ち」に焦点を当てるのに対し、言い換えは「出来事・内容」に焦点を当てます。オウム返し(相手の言葉をそのまま繰り返す)とは違い、カウンセラーの言葉で整理して返すのが特徴です。
5. 明確化(Clarification)
相談者の話が曖昧だったり、漠然としている部分について、より具体的にしてもらうために問いかける技法です。
CL(相談者): 「なんだか、今の職場が自分に合わない気がするんです。」 CC(キャリアコンサルタント): 「『合わない気がする』というのは、具体的にどのような時にそう感じますか?」
【ポイント】 相談者が自分自身の考えを掘り下げ、自己理解を深める手助けになります。「もう少し詳しく教えていただけますか?」といった問いかけも明確化の一種です。
6. 要約(Summarizing)
それまでの話をカウンセラーが整理してまとめる技法です。話の節目や面談の最後に行うことで、論点が明確になり、次のステップに進みやすくなります。
CC(キャリアコンサルタント): 「ここまでのお話をまとめると、現在の仕事のやりがいと、将来のキャリアアップへの希望、その両方を実現できる働き方を模索している、ということでしょうか。」
【ポイント】 言い換えよりも長いスパンの話をまとめます。相談者との間で認識のズレがないかを確認する目的もあります。
7. 質問(Questioning)
質問には大きく分けて2種類あり、使い分けが重要です。
- 開かれた質問(Open Question): 「はい/いいえ」で答えられない、自由な回答を促す質問。「いつ?」「どこで?」「何を?」「どのように?」などを使います。相談者の自己探索を深めるのに有効です。例:「その時、どのように感じましたか?」
- 閉じられた質問(Closed Question): 「はい/いいえ」や、特定の事実を確認するための質問。話が逸れた時に戻したり、具体的な情報を得たい時に有効ですが、多用すると尋問のようになってしまうので注意が必要です。例:「転職を考えたことはありますか?」
【中級編】さらに理解を深める技法
基本技法と組み合わせて使うことで、よりカウンセリングが深まります。
8. 自己開示(Self-disclosure)
カウンセラー自身の経験や感情を、相談者の利益になる範囲で伝える技法です。親近感が湧き、相談者が心を開きやすくなる効果がありますが、使い方には注意が必要です。
CL(相談者): 「未経験の業界に挑戦するのが、すごく怖くて…」 CC(キャリアコンサルタント): 「そうですよね、とても勇気がいることだと思います。実は私も以前、全く違う分野に転職した経験があり、当時は同じように不安でいっぱいでした。」
【ポイント】 あくまで主役は相談者です。カウンセラーの話が長くなったり、自慢話になったりしないよう、簡潔に、相談者の気持ちに寄り添う形で使うことが鉄則です。
9. 直面化(Confrontation)
相談者の言動や感情の中にある矛盾点を、カウンセラーが指摘して伝える技法です。相談者が目を背けている問題に気づかせ、自己理解を促す目的がありますが、信頼関係が十分に築けていない段階で使うと、反発を招く可能性があります。
CL(相談者): 「もっと成長できる環境で働きたいんです。でも、今の会社は安定しているし、転職活動も面倒で…」 CC(キャリアコンサルタント): 「『成長したい』というお気持ちがありながら、一方で『安定した環境を維持したい』というお気持ちもある。その二つの間で揺れ動いているようにお見受けします。」
【ポイント】 相手を非難するのではなく、あくまで「〜という側面と、〜という側面があるようですね」と、客観的な事実として優しく伝えることが重要です。
10. 情報提供(Information Giving)
相談者の意思決定に役立つ客観的な情報(求人市場の動向、資格、教育訓練など)を提供することです。
【ポイント】 キャリアコンサルタントの個人的な意見やアドバイス(指導)とは明確に区別されます。「〜すべきです」ではなく、「〜という選択肢や、〜というデータがありますよ」と、判断材料を中立的な立場で提供する姿勢が求められます。
まとめ
いかがでしたか? これらのカウンセリング技法は、それぞれ独立しているようで、実際の面談では複雑に絡み合いながら使われます。
- まずは相談者の話をじっくり「傾聴」し、
- 「感情の反映」や「言い換え」で理解を示し、
- 「明確化」や「質問」で話を深めていく。
この流れが基本です。 まずは各技法の名前と意味、そして目的をしっかり覚えることから始めましょう。それができたら、逐語録などを読んで「ここはこの技法が使われているな」と分析する練習がおすすめです。
試験本番まで、頑張ってください!応援しています。

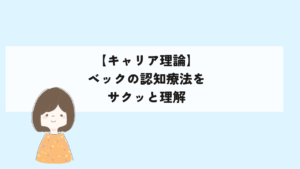

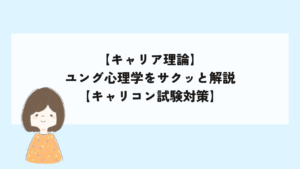
コメント