 チャチャ
チャチャ意思決定理論ってなぜごっちゃになっちゃうのか……
理論家の名前は似てないのに、言っていることがなんだかごちゃごちゃになるキャリア理論。
「誰がどのキーワードだっけ…?」
「結局、この理論ってどうやって使うの?」
そんなお悩みを抱えるあなたのために、今回は試験頻出の4大理論家【ティードマン、ジェラット、ヒルトン、ディンクレッジ】の理論を、どこよりも分かりやすく徹底解説します!



この記事を読み終える頃には、苦手意識が「得点源」に変わっているはずです。それでは、早速見ていきましょう!
概要
キャリアの意思決定アプローチ
ティードマン:自己同一性の発達プロセス
キャリアの意思決定は「自分とは何か」を探求するプロセス。大きく2つの段階を経て、自己同一性を確立していくと考えました。
第1段階:予期の段階 (Anticipation)
行動を起こす前の思考と準備の期間
第2段階:実行・調整の段階 (Implementation & Adjustment)
実際にその環境に入ってからの適応期間
ジェラット:変化する時代の意思決定
時代の変化と共に、理論を大きく転換させました。初期の「合理的アプローチ」から、後期の「積極的不確実性」へ。
初期理論:連続的意思決定プロセス
客観的な情報に基づき、論理的に決定する。
- 予測システム:各選択肢の結果を予測する
- 価値システム:結果の望ましさを評価する
- 決定基準システム:目的達成のための基準で選択
後期理論:積極的不確実性
不確実な未来を、柔軟性と直観で乗りこなす。
- 目標は柔軟に:こだわりすぎず、変化を許容する
- 情報は創造的に:直観や想像力も活用する
- 論理は非合理に:矛盾を受け入れ、多角的に考える
ヒルトン:認知的不協和理論の応用
自分の考え(前提)と環境からの情報が矛盾したときに生じる「不快感(不協和)」を解消するために、意思決定が行われると考えました。
意思決定のプロセス
① 前提の検証
自分と仕事の世界を吟味
② 不協和の発生
考えと情報が矛盾
③ 不協和の解消
計画の探索・選択
クルンボルツ:学習理論的意思決定(7つのステップ)
意思決定は学習可能なスキルであると捉え、問題解決のための具体的な7つのステップを提唱しました。(ティンクレッジらとの共同研究)
問題の明確化
何を決めたいのかはっきりさせる
目標の設定
自分の価値観と関連付ける
代替案の作成
考えられる選択肢を洗い出す
情報収集
各選択肢について調べる
結果の予測
成功の可能性などを考える
選択肢の再評価
目標や価値観に照らし合わせる
決定と行動
決断し、実行に移す
1. ティードマン:キャリアは「自分らしさ」を探す成長の旅だ!
トップバッターは、デイビッド・ティードマン。彼の理論を一言でいうと、**「キャリア選びは、自分らしさ(自我同一性)を見つけていく一生続くプロセスである」**という考え方です。
💡 ココがポイント:「分化」と「統合」
ティードマン理論を理解する上で欠かせないのが、この2つのキーワードです。
- 分化(区別化):たくさんの選択肢の中から、「自分はこっちの道に進みたい!」と、自分の興味や価値観をハッキリさせていくこと。
- 統合(統合化):決めた道を、現実の社会(会社や学校など)にうまく適応させて、自分の一部にしていくこと。
つまり、「自分だけの道を見つけて、社会と折り合いをつけながら成長していく」というイメージですね!
🚀 超重要!「予期」と「実行」の7ステップ
ティードマン理論で試験に一番出やすいのが、この2フェーズ・7段階のプロセスです 1。時系列で進んでいくので、物語のように覚えるのがおすすめです!
【フェーズ1:予期】(頭の中で考える段階)
- 探索:「将来何になろうかな〜?選択肢は無限大!」と夢を広げる段階 1。
- 結晶化:「うーん、やっぱり自分にはこっちの2つかな」と選択肢を絞り込む段階 1。
- 選択:「よし、これに決めた!」と一つの道を選ぶ段階 1。
- 明確化:「じゃあ、そのために具体的に何をすればいいかな?」と計画を立てる段階 1。
【フェーズ2:実行】(実際に行動する段階)
- 導入:新しい環境(会社や学校)に飛び込み、そこの一員になろうとする段階 1。
- 変革:環境に慣れてきたら、「もっとこうしたい!」と自分らしさを出して周りに働きかける段階 1。
- 統合:自分と環境のバランスが取れて、「ここが自分の居場所だ!」と満足感を得る段階 1。
✅ 試験対策のポイント
「予期が4段階、実行が3段階」という構成と、各段階の順番をしっかり覚えましょう!「探して→固めて→選んで→ハッキリさせる」という流れをつかむのがコツです 3。
2. ジェラット:未来は予測不能?だから面白いんだ!
次にご紹介するのは、H.B.ジェラット。彼の理論は、時代と共に考え方がアップデートされたのが最大の特徴です。
昔のジェラット先生:「意思決定は、論理的に!」
初期の理論は、とても合理的 4。データに基づいて、最適な選択をするための3つのシステムを提唱しました 6。
- 予測システム:どんな選択肢があって、どんな結果になりそうか、確率を予測する。
- 価値システム:その結果が、自分にとってどれくらい嬉しいかを評価する。
- 決定システム:予測と価値を天秤にかけて、ベストな選択をする。
これはこれで分かりやすいですが、変化の激しい現代では、これだけだとちょっと厳しいかも…?
今のジェラット先生:「不確実性を、むしろ楽しもうぜ!」
そこで登場するのが、後期理論の超重要キーワード**「積極的不確実性(Positive Uncertainty)」**です! 8
これは、「未来なんて誰にも予測できないんだから、ガチガチに計画するより、不確実性を前向きに受け入れて、柔軟に対応していこうよ!」という考え方 9。
そのためのアプローチが**「全脳型(Whole-Brain)」アプローチ**です 6。
- 左脳(合理的):データや分析もちゃんと使う。
- 右脳(直感的):でも、自分の直感やひらめき、ワクワクする気持ちも信じる。
論理と直感のハイブリッドで、予測不能な時代を乗りこなそう!というわけですね。
✅ 試験対策のポイント
初期理論と後期理論は対立するものではなく、後期が初期を補う(補完する)関係である、という点を押さえましょう 6。積極的不確実性というキーワードは絶対暗記です!
3. ヒルトン:心の”モヤモヤ”が、次の一歩を決める!
3人目は、トーマス・ヒルトン。彼の理論は、私たちの心の中の葛藤に焦点を当てます。
💡 ココがポイント:「認知的不協和」
ヒルトン理論の心臓部が、この**「認知的不協和」**という心理学用語です 12。
これは、**「自分の理想や考え(前提)」と「外部からの新しい情報」**が食い違ったときに生まれる、居心地の悪い”モヤモヤ”した感情のこと。
例えば、「クリエイティブな仕事がしたい!(前提)」と思っている人が、「でも、そういう仕事って給料が不安定らしい…(外部情報)」と知った時の、「うーん、どうしよう…」という気持ちがまさにこれです。
🌀 モヤモヤ解消の3ステップサイクル
ヒルトンによれば、意思決定とは、このモヤモヤを解消するプロセスそのものだと言います 13。
- 前提:まず、自分の中に「こうありたい」という理想や価値観がある。
- 不協和:そこに、矛盾する情報が入ってきて、モヤモヤが発生!
- 再調整:モヤモヤを解消するために、行動を起こす。
- 前提を変える:「仕事じゃなくて、趣味でクリエイティブなことをするのもアリかも?」
- 情報を探し直す:「安定して稼げるクリエイティブな仕事はないかな?」
- 情報を否定する:「いや、自分ならきっと成功できるはずだ!」
このサイクルを繰り返して、心がスッキリした(不協和が解消された)ときに、意思決定がなされるのです 17。
✅ 試験対策のポイント
ヒルトン = 認知的不協和の組み合わせは鉄板です 16!前提、不協和、再調整の3つのキーワードもセットで覚えましょう。
4. ディンクレッジ:あなたはどのタイプ?意思決定スタイル診断!
最後は、リリアン・ディンクレッジ。彼女の理論は、これまでの3人とは少し違い、**「人にはそれぞれ意思決定の”クセ”(スタイル)がある」**という類型論です 19。
✨ 理想のスタイル:「計画型」
ディンクレッジは、まず理想的な意思決定の進め方として、7つの段階を提示しました 20。
- 決定事項の明確化
- 情報収集
- 選択肢の明確化
- 根拠の評価
- 最終選択
- 行動
- 結果の検討
この7段階をしっかり踏めるのが、唯一望ましいとされる**「計画型(Planner)」**スタイルです 20。
🤔 あなたはどれ?7つの”お悩み”スタイル
問題は、多くの人が陥りがちな、あまり効果的ではない7つのスタイルです 20。あなたはどのタイプに近いですか?
- 苦悩型:情報が多すぎて悩みすぎ、決められない…。
- 衝動型:深く考えず、勢いで決めちゃう!
- 直観型:理屈じゃない、私の勘がそう言ってる!
- 無力型:「どうせ自分なんて…」と諦めて行動できない。
- 延期型:「明日から本気出す…」と先延ばしにする。
- 運命論型:「なるようになるさ」と運命に身を任せる。
- 従順型:周りの意見に流されてしまう。
キャリアカウンセラーとしては、クライエントがどのタイプなのかを見極め、理想の「計画型」に近づけるようサポートすることが求められます 22。
✅ 試験対策のポイント
ディンクレッジ = 8つのスタイル + 7つの段階という公式を覚えましょう 20。それぞれのスタイルの特徴を説明できるようにしておくと、事例問題にも対応できます!
まとめ:一目でわかる!4大理論家 比較早見表
最後に、今日の内容を表でスッキリ整理しましょう!この表をスクリーンショットしておけば、試験直前の見直しにも役立ちますよ。
| 比較軸 | ティードマン | ジェラット | ヒルトン | ディンクレッジ |
| 一言でいうと? | キャリアは成長の旅 | 不確実性を楽しむ! | 心のモヤモヤが原動力 | 意思決定のクセ診断 |
| キーワード | 自我同一性 予期と実行 | 積極的不確実性 全脳型 | 認知的不協和 前提 | 8つのスタイル 計画型 |
| アプローチ | 発達プロセス | 哲学的アプローチ | 心理的プロセス | 行動スタイル(類型論) |
| カウンセラーの役割 | 成長のガイド役 | パラダイムを変える人 | モヤモヤ解消の伴走者 | 診断家 兼 コーチ |
いかがでしたか?
複雑に見えた意思決定理論も、それぞれの理論家の「個性」や「視点の違い」を理解すると、スッと頭に入ってきませんか?
これらの理論は、クライエントを支援する上での強力な武器になります。このブログが、あなたの試験合格、そして未来のキャリアコンサルタントとしての活躍に繋がることを心から願っています。
頑張ってください!💪


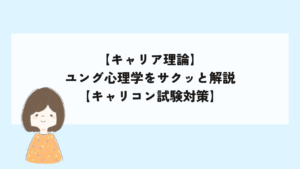

コメント