 チャチャ
チャチャ障害者雇用について知りたいけど、「障害者の雇用の促進等に関する法律」内容がたくさんありすぎて読めない……



まずは重要な部分を押さえよう!
障害者雇用について、まずは障害者雇用促進法の重要ポイントをサクッと理解しましょう。
ひと目でわかる!重要ポイント
障害者雇用促進法の最重要項目をまとめました。特に試験で問われやすい数値をしっかり押さえましょう。
民間企業の法定雇用率
2.5%
(2024年4月〜)
対象事業主
40.0人以上
常時雇用する労働者数
納付金額(未達成時)
50,000円
/ 不足1人あたり月額
【深掘り】障害者雇用率制度
障害者雇用率制度は法律の根幹です。ここでは、法定雇用率の推移と、複雑な実雇用率の算定方法をインタラクティブに学習します。
法定雇用率の推移(民間企業)
下のボタンで年を切り替えると、法定雇用率の変化をグラフで確認できます。段階的な引き上げが重要なポイントです。
実雇用率カウント シミュレーター
雇用する労働者の種類にチェックを入れると、実雇用率の算定に使われる合計人数がどう変わるか体験できます。「ダブルカウント」などのルールを体感しましょう。
算定上の合計人数
0.0
【実践】企業の義務と責任
事業主には、差別の禁止と「合理的配慮の提供」が義務付けられています。ここでは、合理的配慮の具体例をカード形式で学びます。カードをクリックして、課題と解決策のペアを確認しましょう。
【財務】障害者雇用納付金制度
法定雇用率の達成状況に応じて、企業間の経済的負担を調整する制度です。自社の状況を入力して、納付金または調整金がどうなるかシミュレーションしてみましょう。(※常用労働者100人超の企業を想定した簡易計算です)
【時系列】近年の法改正と今後の動向
法律は常に変化しています。キャリアコンサルタントとして、最新の動向を把握しておくことは非常に重要です。ここでは、近年の主な改正点を時系列で確認します。
2024年4月
- 法定雇用率引き上げ (民間: 2.3% → 2.5%)
- 週10~20hの特定短時間労働者を実雇用率に算定 (0.5カウント)
2025年4月 (予定)
- 除外率の引き下げ (一律10ポイント)
2026年7月 (予定)
- 法定雇用率の再引き上げ (民間: 2.5% → 2.7%)



特に障害者雇用率は頻出だよ、ぜひチェックしてね。
法律の目的と基本理念
まず、この法律が何を目指しているのかを理解することが重要です。
- 目的: 障害者の雇用の安定を図ること。(法第1条)
- 基本理念:
- すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(ノーマライゼーション)の実現。
- 障害者である労働者は、職業生活においてその能力を有効に発揮する機会を与えられる。
- 責務:
- 事業主: 社会連帯の理念に基づき、障害者の能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与え、雇用の安定を図る責務がある。
- 国・地方公共団体: 事業主や国民の理解を高め、必要な施策を総合的かつ効果的に推進する責務がある。
【最重要】障害者雇用率制度
試験で最も出題されやすいのが、この雇用率制度です。具体的な数値を正確に覚えましょう。
1. 法定雇用率(2024年4月1日〜)
事業主は、その雇用する労働者に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
| 対象事業主 | 法定雇用率(2024年4月〜) | 法定雇用率(2026年7月〜) |
|---|---|---|
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |
| 国・地方公共団体 | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
ポイント:
- 民間企業の法定雇用率 2.5% に伴い、雇用義務の対象は常時雇用する労働者数が40.0人以上の事業主となります。
- 2026年7月からは 2.7% となり、対象は37.5人以上の事業主に拡大されます。
2. 実雇用率の算定方法
法定雇用率を達成しているかどうかを判断するための「実雇用率」の計算方法も重要です。
実雇用率(%) = (雇用されている障害者数) ÷ (全常用労働者数) × 100
障害者数のカウント方法
| 労働者の区分 | 週所定労働時間 | カウント |
|---|---|---|
| 身体障害者・知的障害者・精神障害者 | 30時間以上 | 1人 |
| 重度身体障害者・重度知的障害者 | 30時間以上 | 2人(ダブルカウント) |
| 短時間労働者 | 20時間以上30時間未満 | 0.5人 |
| 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者(短時間) | 20時間以上30時間未満 | 1人 |
| 特定短時間労働者(2024年4月〜)<br>(重度身体・重度知的・精神障害者) | 10時間以上20時間未満 | 0.5人 |
ポイント:
- ダブルカウント: 重度身体障害者・重度知的障害者は1人で2人分としてカウントします。
- 精神障害者の特例: 精神障害者は、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)であっても1人としてカウントされます。
- 2024年4月からの改正: 週10時間以上20時間未満で働く重度身体・知的障害者、精神障害者も0.5人として算定対象になりました。これは、より多様で柔軟な働き方を推進するためです。
企業の義務と責任
雇用率の達成だけでなく、雇用における具体的な対応も義務付けられています。
1. 差別の禁止
募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練など、雇用のあらゆる段階で、障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いは禁止されています。
2. 合理的配慮の提供義務
障害のある労働者が能力を発揮する上で支障となっている「社会的障壁」を取り除くため、事業主は合理的配慮を提供しなければなりません。
- 社会的障壁の例:
- 車椅子での移動が困難な段差
- 聴覚障害者への口頭のみでの指示
- 視覚障害者が見にくい書類
- 発達障害者が混乱しやすい曖昧な業務指示
- 合理的配慮の具体例:
- スロープの設置、机の高さの調整
- 筆談や手話通訳者の配置、指示の文書化
- 拡大読書器の導入、音声読み上げソフトの活用
- 業務内容の図式化、指示の明確化、定期的な面談
- 提供のプロセス:
- 障害のある本人から申し出がある。
- 事業主と本人が建設的対話を行い、必要な配慮を検討する。
- 事業主に過重な負担とならない範囲で配慮を提供する。
ポイント: 「過重な負担」であるかどうかは、事業規模、財務状況、配慮にかかる費用などを総合的に考慮して個別に判断されます。
障害者雇用納付金制度
法定雇用率の達成状況に応じて、企業間の経済的負担を調整するための制度です。
- 対象: 常用労働者100人超の事業主
- 障害者雇用納付金(未達成の場合):
- 法定雇用率未達成の場合、不足する障害者1人につき月額50,000円を納付する。
- 障害者雇用調整金(達成の場合):
- 法定雇用率を超えて雇用している場合、超過する障害者1人につき月額29,000円が支給される。
- 報奨金(100人以下の企業):
- 常用労働者100人以下の事業主が、一定数(各月の労働者数の4%か72人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合、超過1人につき月額21,000円が支給される。
第5章:職業リハビリテーションの推進
キャリアコンサルタントとして連携する可能性のある支援機関の役割を理解しておきましょう。
- ハローワーク(公共職業安定所): 専門の職員・相談員を配置し、求職登録から就職後のフォローまで一貫した支援を提供。
- 地域障害者職業センター: ハローワークと連携し、専門的な職業リハビリテーション(職業評価、職業指導、ジョブコーチ支援など)を実施。事業主への相談・援助も行う。
- 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ): 就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う身近な地域の支援機関。
近年の法改正と今後の動向
- 2024年4月施行:
- 法定雇用率の引き上げ(民間: 2.3% → 2.5%)
- 週10~20時間未満の特定短時間労働者を実雇用率に算定(0.5カウント)
- 2025年4月施行予定:
- 除外率の引き下げ: 障害者の就業が困難とされる業種で雇用労働者数を計算する際に一定率を控除する「除外率制度」が、さらに10ポイント引き下げられます。
- 2026年7月施行予定:
- 法定雇用率の再引き上げ(民間: 2.5% → 2.7%)
これらの改正は、障害のある人がより多様な形で社会参加できる環境を整備していくという国の強い意志の表れです。
キャリアコンサルタントによる障害者雇用の環境へのはたらきかけ
キャリアコンサルタントによる障害者雇用の支援
環境へのはたらきかけをインタラクティブに学ぶ
「環境へのはたらきかけ」とは?
障害者雇用における「環境へのはたらきかけ」とは、障害のある方が能力を最大限に発揮し、安定して働き続けられるように、企業内の物理的・制度的・心理的な環境を整えるためのアプローチです。キャリアコンサルタントは、ご本人と企業の間に立ち、専門的な視点からこの「環境」に積極的に介入し、調整していく重要な役割を担います。このページでは、その具体的なアプローチを3つの対象に分けて探求します。
企業が抱える不安や誤解を解消し、スムーズな受け入れと定着ができる体制構築を支援します。
① 意識啓発・理解促進 ▶
- 情報提供: 障害の特性や必要な配慮について、偏見や誤解に基づかない正確な情報を提供します。
- 成功事例の共有: 他社の障害者雇用の成功事例を紹介し、具体的なイメージを持ってもらいます。
- メリットの提示: ダイバーシティ推進、新たな視点の獲得、社会的責任(CSR)向上といったメリットを伝えます。
② 受入体制の整備支援 ▶
職務の切り出し(ジョブ・カービング): 社内の業務を分析し、本人の特性や能力に合った職務を創出する提案を行います。
合理的配慮の提案:
- 物理的配慮: スロープ設置、机の高さ調整、音声読み上げソフト導入など。
- 制度的配慮: 通院への配慮、休憩の工夫、フレックスタイム制の活用提案など。
- 人的配慮: 指示の出し方の工夫、メンター役の設定、チーム内の役割分担の調整など。
助成金・支援制度の活用支援: 国や自治体の関連制度の情報を提供し、申請をサポートします。
③ 採用後の定着支援 ▶
- 定期的なフォローアップ: 本人と上司・同僚の双方と面談し、課題の早期発見と解決を支援します。
- コミュニケーションの橋渡し: 双方の意図がすれ違っている場合に間に入り、円滑な対話を促進します。
- 社内研修の企画・実施: 管理職や同僚向けの障害理解研修などを提案・実施し、職場全体の理解を深めます。
支援者に求められる4つの重要な視点
中立的な立場
企業と本人のどちらか一方に偏らず、双方の利益と成長を考える視点を持ちます。
個別性の尊重
「障害」という枠で捉えず、一人ひとりの特性、希望、状況を深く理解し、個別に対応します。
長期的視点
目先の就職だけでなく、その後のキャリア形成と職業生活の安定・向上までを見据えます。
法令・制度の知識
障害者雇用促進法や関連助成金など、最新の知識を常にアップデートし、適切に活用します。
「環境へのはたらきかけ」とは
障害者雇用における「環境へのはたらきかけ」とは、障害のある方が能力を最大限に発揮し、安定して働き続けられるように、企業内の物理的・制度的・心理的な環境を整えるためのアプローチです。
キャリアコンサルタントは、障害のあるご本人と企業の間に立ち、双方にとって最適な雇用関係が築けるよう、専門的な視点からこの「環境」に積極的に介入し、調整していく役割を担います。これは、単に求人を紹介するだけでなく、雇用の「質」を高め、長期的な定着を実現するために不可欠な支援です。
はたらきかけの対象と具体的なアプローチ
環境へのはたらきかけは、主に「企業」「障害のある本人」「関係機関」の3つの対象に対して行われます。
(1) 企業へのはたらきかけ
企業が障害者雇用に関する不安や誤解を解消し、スムーズな受け入れと定着ができる体制を構築できるよう支援します。
① 意識啓発・理解促進
- 情報提供: 障害の特性や必要な配慮について、偏見や誤解に基づかない正確な情報を提供します。
- 成功事例の共有: 他社の障害者雇用の成功事例を紹介し、具体的なイメージを持ってもらいます。
- メリットの提示: 障害者雇用がもたらすダイバーシティの推進、新たな視点の獲得、社会的責任(CSR)の向上といったメリットを伝えます。
② 受入体制の整備支援
- 職務の切り出し(ジョブ・カービング): 社内の業務を分析し、障害のある方の特性や能力に合った職務を創出する提案を行います。
- 合理的配慮の提案:
- 物理的配慮: スロープの設置、机の高さ調整、音声読み上げソフトの導入など。
- 制度的配慮: 通院への配慮、休憩の取り方の工夫、フレックスタイム制の活用提案など。
- 人的配慮: 指示の出し方(口頭だけでなくメモを添えるなど)、相談しやすいメンター役の設定、チーム内での役割分担の調整などを助言します。
- 助成金・支援制度の活用支援: 国や自治体が提供する障害者雇用関連の助成金やサポート制度の情報を提供し、申請手続きをサポートします。
③ 採用後の定着支援
- 定期的なフォローアップ: 採用後も定期的に本人と上司・同僚の双方と面談し、課題の早期発見と解決を支援します。
- コミュニケーションの橋渡し: 双方の意図がすれ違っている場合などに間に入り、円滑なコミュニケーションを促進します。
- 社内研修の企画・実施: 管理職や同僚向けの障害理解研修などを提案・実施し、職場全体の理解を深めます。
(2) 障害のある本人への支援
本人が自身のことを理解し、企業に適切に伝え、職場で能力を発揮できるよう支援します。
- 自己理解の促進: 自身の障害特性、得意なこと・苦手なこと、必要な配慮などを客観的に整理し、言語化するのを手伝います。(アセスメントツールの活用など)
- 職業能力開発の支援: 業務に必要なスキルや知識を習得するための訓練機関や学習方法について情報提供します。
- コミュニケーションスキルの向上: 自分の言葉で必要な配慮を企業に説明する「セルフ・アドボカシー(自己権利擁護)」のスキルを高めるための練習(ロールプレイングなど)を行います。
(3) 関係機関との連携(チームアプローチ)
キャリアコンサルタント一人で全てを抱えるのではなく、専門性を持つ様々な機関と連携し、多角的な支援体制(チームアプローチ)を築きます。
- ハローワーク(公共職業安定所): 専門援助部門と連携し、求人情報の共有や紹介依頼を行います。
- 障害者就業・生活支援センター: 就労面だけでなく、生活面も含めた一体的な支援が必要な場合に連携します。
- 就労移行支援事業所: 職業訓練や職場実習の場として連携し、本人の適性や能力を見極めます。
- 医療機関(主治医など): 本人の健康状態や就業に関する医学的な意見を、本人の同意を得た上で確認し、配慮に活かします。
キャリアコンサルタントに求められる重要な視点
- 中立的な立場: 企業と本人のどちらか一方に偏るのではなく、双方の利益と成長を考える中立的な視点を持ちます。
- 個別性の尊重: 「障害」という大きな枠で捉えるのではなく、一人ひとりの特性、希望、状況を深く理解し、個別に対応します。
- 長期的視点: 目先の就職だけでなく、その後のキャリア形成と職業生活の安定・向上までを見据えた長期的な支援を心がけます。
- 法令・制度の知識: 障害者雇用促進法や関連する助成金制度など、最新の知識を常にアップデートし、適切に活用できることが求められます。
1. 経営上のメリット
企業の成長と安定に直接貢献するメリットです。多様な人材の確保から生産性向上、そして社会的信用の確立まで、企業の基盤を強化する効果を探ります。
障害のある方は、独自の視点や発想、高い集中力など、多様な能力を持っています。これまで見過ごされてきた優秀な人材を発掘し、組織のダイバーシティを促進することで、新たなイノベーションや問題解決の糸口が生まれる可能性があります。
障害のある方に適した業務を切り出し任せることで、他の従業員はより専門性の高い業務に集中できます。また、業務プロセスを見直す過程で組織全体の非効率な部分が改善され、生産性が向上するケースも少なくありません。
国や自治体は、障害者雇用を推進する企業に様々な助成金制度を設けています(例:特定求職者雇用開発助成金、障害者トライアルコースなど)。これらを活用し、採用や設備投資の経済的負担を軽減できます。
法定雇用率の達成と社会的信用
法定雇用率(2024年4月時点: 2.5%)の達成は法的義務であり、企業の信頼性の証です。自社の状況を確認してみましょう。
必要な雇用者数: 0 人
2. 組織・社内へのメリット
職場環境や従業員の意識に良い影響を与えます。一人の採用が、組織全体にポジティブな連鎖反応を生み出す様子をご覧ください。
ポジティブな影響の連鎖
(ユニバーサルデザイン化)
(多様性の受容)
(協力体制の構築)
障害のある方が働きやすい環境整備(段差解消、通路確保など)は、結果的に高齢者や妊婦など、全従業員にとって働きやすい「ユニバーサルデザイン」な職場につながります。
障害のある従業員と共に働くことを通じ、他の従業員に多様性を受け入れる心や思いやりが育まれます。自然なサポートの中から、管理職のマネジメント能力向上や若手社員の人間的成長が期待できます。
新しい仲間を部署全体でどうサポートするかを考える過程で、従業員間のコミュニケーションが活発化し、協力体制が生まれます。これが組織全体のチームワーク強化につながります。
3. 社会・対外的なメリット
企業のブランドイメージや社会との関係性にプラスの効果をもたらします。社会貢献が、いかにして企業の持続的な成長と新たなビジネスチャンスに繋がるかを見ていきましょう。
障害者雇用に積極的な姿勢は、人権を尊重し社会貢献に意欲的な企業として、顧客、取引先、投資家、地域社会から高く評価されます。ポジティブな評判は、製品選択や優秀な人材獲得においても有利に働きます。
障害のある従業員の視点や意見は、これまでになかった商品やサービスの開発に活かされることがあります。高齢化が進む社会において、多様なユーザーのニーズを理解することは、新たな市場を開拓する上で大きな強みとなります。
まとめ
障害者雇用の環境へのはたらきかけは、キャリアコンサルタントの専門性が大いに発揮される領域です。企業と障害のある方の「橋渡し役」として、丁寧なコミュニケーションと多角的なアプローチを重ねることで、誰もが活躍できるインクルーシブな職場環境を創り出すことができます。これは、当事者だけでなく、企業組織全体の成長にも繋がる価値ある取り組みと言えるでしょう。

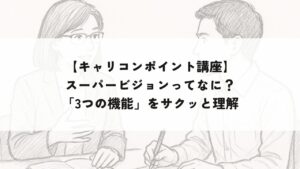

コメント