 まい
まい「令和6年版 労働経済の分析」に基づき、キャリアコンサルタント試験で問われやすい重要ポイントを網羅的に解説します。
目次
インフォグラフィック版
労働市場の概観
現在の日本の労働市場が直面する主要な課題である「人手不足」と「賃金動向」を概観します。
データを通じて、経済の構造的な変化とその影響を読み解きます。
産業別人手不足の状況
企業の雇用人員判断D.I.(「過剰」-「不足」)。マイナスが大きいほど不足感が強いことを示す。
名目賃金と実質賃金の推移
給与の額面(名目)は上昇していますが、物価の影響を考慮した購買力(実質)は低下しています。
人手不足の歴史的変遷
過去半世紀で3回の人手不足局面がありましたが、現在は構造的な要因により「長期的かつ粘着的」な状況です。
1
1970年代前半
高度経済成長による超過需要
2
80年代後半~90年代前半
サービス経済化と労働時間短縮
今
2010年代以降
人口減少・高齢化による構造的不足
多様な人材の活躍と課題
人手不足解消の鍵を握る女性、高齢者、外国人材。それぞれの就業状況と特有の課題をデータで探ります。
主な課題とポイント
人手不足への具体的対策
人手不足は、採用だけでなく「離職率の低下」が鍵となります。
ここでは、効果的な取り組みやマクロな市場動向を解説します。
【分野別】効果的な取り組み
介護分野
- 標準以上の賃金確保
- リフト等の福祉機器導入
- ICT機器による事務負担軽減
- 定期的な賞与の支給
- 相談体制の整備
小売・サービス分野
- 月額20万円以上の賃金確保
- スキルを評価する給与制度
- 研修制度の整備
- 多様な人材が活躍できる環境
- 月20h以上の残業はマイナス効果
労働移動と賃金の関係性
人手不足により中小企業から大企業への労働移動が活発化。日本では、企業の求人未充足(欠員率)が賃金上昇に繋がりやすい特徴があります。
欠員率上昇に対する賃金上昇の感応度
高い
今後の賃金上昇圧力となる可能性を示唆
企業の先進的取り組み
DX推進
生産管理システム導入などで業務効率化を図る中小企業の事例
働き方改革
物流の「リレー輸送」などで長時間労働を是正(2024年問題対応)
ダイバーシティ推進
国籍を問わない採用と、外国人材の定着を支援するタクシー会社の事例
第1章:労働経済の全体像(2023年の動向と特徴)
1-1. 雇用失業情勢
- 全般:求人は底堅く推移し、雇用情勢は改善の動きが見られます。
- 正規雇用:特に女性を中心として正規雇用労働者数は9年連続で増加しました。
- 人手不足感:企業の雇用人員判断D.I.は、全産業で不足超過となっており、コロナ禍以前よりも人手不足感が強まっています。特に「宿泊業、飲食サービス業」「建設業」「運輸業、郵便業」で深刻です。
1-2. 賃金動向
- 名目賃金:現金給与総額は3年連続で増加。2023年の民間主要企業の春季賃上げ率は**3.60%**と、1993年(3.89%)に次ぐ30年ぶりの高水準を記録しました。
- 実質賃金:しかし、消費者物価指数の上昇が賃金の伸びを上回ったため、**実質賃金は前年比▲2.5%**と2年連続のマイナスとなりました。これは、個人の購買力が低下していることを意味します。
- パートタイム労働者の賃金:パートタイム労働者の時間当たり給与は増加傾向にありますが、依然として一般労働者との格差は存在します。
1-3. 人手不足の歴史的背景と現状
- 過去の人手不足局面:過去半世紀で、人手不足は大きく3つの期間で生じています。
- 1970年代前半:高度経済成長を背景とした超過需要が主因。
- 1980年代後半~90年代前半:経済のサービス化と労働時間短縮が寄与。
- 2010年代以降~現在:景気回復に加え、人口減少・高齢化という構造的要因が複合的に影響。
- 現在の特徴:2010年代以降の人手不足は、過去の局面に比べて人手不足を感じる企業の割合が高く、期間も長い「長期的かつ粘着的」なものとなっています。
第2章:多様な人材の活躍推進と課題
2-1. 女性の活躍推進
- 就業状況:女性の就業率は上昇し諸外国並みですが、パートタイム労働者の比率が高いのが特徴です。
- M字カーブ:出産・育児期に就業率が低下する「M字カーブ」は、近年底が浅くなるなど解消が進んでいますが、依然として課題は残ります。
- 賃金格差:育児休業などを利用して就業を継続した正規雇用の女性と、一度離職して再就職した女性とでは、40歳以降に賃金カーブに大きな差が見られます。
- 潜在的労働力:就業を希望しながら求職していない理由として、59歳以下の女性では「出産・育児・介護・看護・家事のため」が約4割を占めており、両立支援の重要性を示唆しています。
2-2. 高齢者の活躍推進
- 就業率:日本の高齢者の就業率は国際的に見て非常に高い水準です。
- 就業形態の変化:60歳を境に正社員比率が大幅に低下し、非正規雇用比率が急上昇します。これは定年制や継続雇用制度の影響です。
- 65歳の壁:高齢者雇用確保措置などにより、かつて60歳に見られた「就業率の崖」は65歳へとシフトしています。65歳以降の就業機会の確保が課題です。
2-3. 外国人材の受け入れ
- 現状:特定技能で就労する外国人は、ベトナム人を中心に増加しています。
- 課題:日本の賃金が伸び悩んだ結果、アジアの主要な送出国との賃金差が縮小傾向にあります。今後は、賃金だけでなく、休日数や労働環境を含めた総合的な待遇改善が人材確保の鍵となります。
- 求職者の動向:ハローワークの分析では、外国人求職者の応募を増やす最も大きな要因は募集賃金であり、次いで年間休日120日以上も効果があることが示されています。
第3章:人手不足への具体的対策と労働市場の動向
3-1. 【分野別】人手不足緩和に効果的な取り組み
人手不足の緩和には、新規採用だけでなく離職率を低下させることが極めて重要です。
- 介護分野:
- 標準的な水準以上の賃金の確保
- 職員の身体的負担を軽減する介護福祉機器(リフト等)やICT機器の導入
- 定期的な賞与、相談体制の整備
- 小売・サービス分野:
- 正社員において、少なくとも月20万円以上の月額賃金(残業代・ボーナス除く)の確保
- 研修制度や、仕事内容・スキルを評価し給与に反映させる仕組みの整備
- (※月20時間以上の時間外労働は、人材確保にマイナスの効果)
3-2. 企業の先進的取り組み
- DX(デジタルトランスフォーメーション):中小企業において、生産管理システム等の導入による業務効率化。
- 働き方改革:物流業界における「リレー輸送」や「モーダルシフト」による長時間労働の是正(2024年問題への対応)。
- ダイバーシティ&インクルージョン:国籍を問わない積極的な採用と、定着支援の取り組み。
3-3. 労働移動と賃金の関係
- 労働移動の活発化:人手不足を背景に、特に中小企業から大企業への労働移動が活発化しています。
- 欠員率と賃金の関係:日本はアメリカ等と比較して、欠員率(求人が充足されない割合)の上昇が、賃金の上昇に結びつきやすい(感応度が高い)という特徴があります。これは、今後人手不足が続くことで、さらなる賃金上昇圧力となる可能性を示唆しています。
復習問題
クイズ終了!
あなたのスコア:

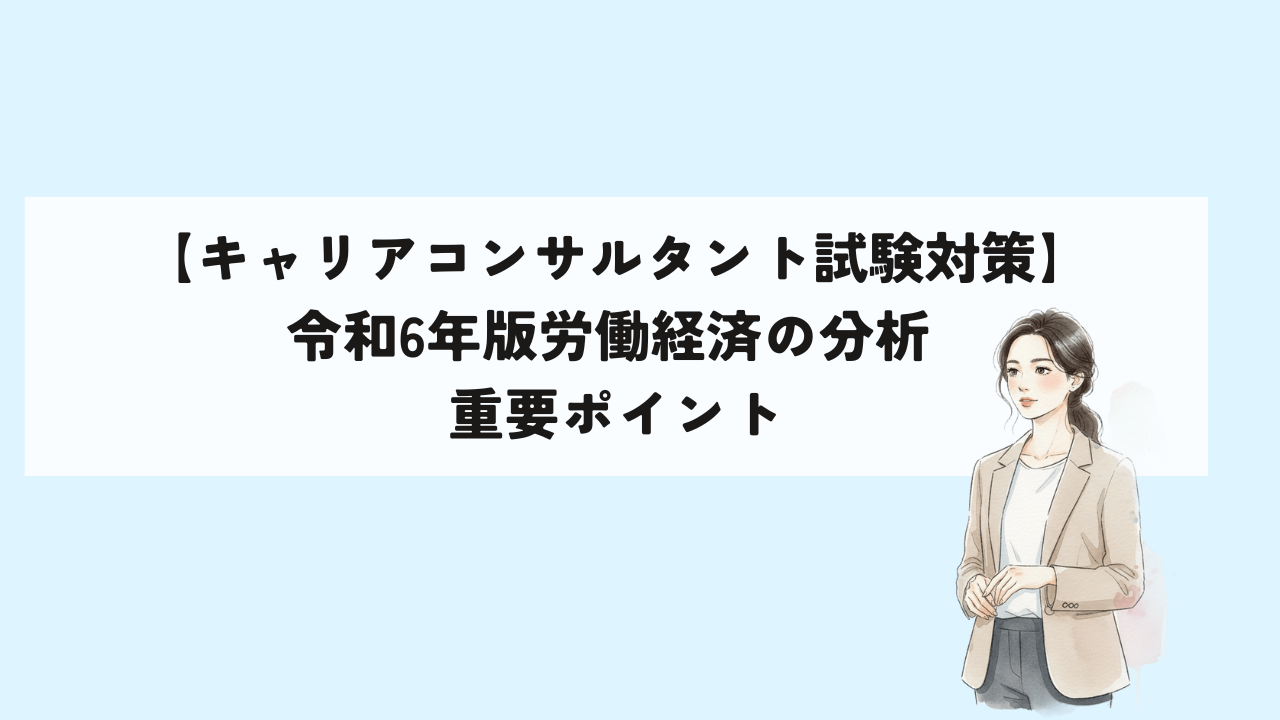
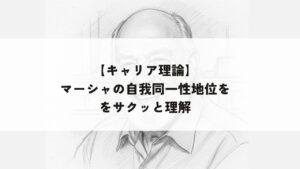
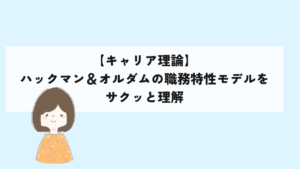

コメント