今回は、国の経済政策の大きな柱である「成長戦略実行計画」について、特にキャリアコンサルティングに関連する部分をピックアップして、分かりやすく解説していきます。
インタラクティブ学習版
1. 日本経済の現状と課題
日本の経済成長を読み解く鍵は「労働生産性」と「労働参加率」にあります。また、コロナ禍は雇用構造に大きな影響を及ぼしました。ここでは、データを通じて日本の「働く」環境が直面する課題を可視化し、今後のキャリアを考える上での出発点を探ります。
G7比較:労働生産性と労働参加率
日本の労働参加率は女性や高齢者の就業拡大によりG7で最高水準にありますが、労働生産性は最も低い水準に留まります。このギャップの解消が、持続的な賃金上昇と「成長と分配の好循環」を実現する上で不可欠です。
コロナ禍が雇用に与えた影響
コロナ禍で特に影響が大きかったのは、宿泊・飲食業などの産業で働く非正規雇用の労働者、とりわけ女性でした。正規雇用が微増する一方、非正規雇用は大幅に減少し、雇用の二極化が浮き彫りになりました。
2. 未来を創る2つの成長エンジン
ポストコロナ時代の新たな成長を牽引するため、国は「デジタル化(DX)」と「グリーン化(GX)」を車の両輪として強力に推進します。これらの分野への集中投資は、新たな産業を創出し、未来の雇用を生み出す源泉となります。
💻 デジタル化 (DX)
- ✓ デジタル庁の司令塔機能:国・地方のシステム統一やマイナンバーカード普及を加速。
- ✓ 通信インフラ整備:5Gの全国展開、さらに次世代の6G技術開発を推進。
- ✓ デジタル人材の育成:社会全体で求められる人材像を共有し、教育コンテンツ整備や学びの場を提供。
🌿 グリーン化 (GX)
- ✓ 2050年カーボンニュートラル:再生可能エネルギーの最大限の導入を目指す。
- ✓ 成長分野への投資:洋上風力、次世代太陽光、水素、蓄電池などの産業を強力に支援。
- ✓ 地域脱炭素ロードマップ:全国100か所以上の「脱炭素先行地域」を創出し、脱炭素ドミノを狙う。
3. 「人」への投資:新しい働き方の設計図
成長の果実を実感できる社会の実現には、一人ひとりのキャリア自律を支える「人」への投資が不可欠です。多様な働き方の選択肢を広げ、産業構造の変化に対応できる円滑な労働移動を支援することで、誰もが活躍できる環境を整備します。
テレワーク定着
サテライトオフィス整備などで場所を選ばない働き方を推進。
兼業・副業促進
個人のスキルを活かす多様なキャリア形成を後押し。
フリーランス保護
契約ルールの法制化などで安心して働ける環境を整備。
選択的週休3日制
育児・介護や学び直しと仕事を両立しやすくする。
特に注目:失業なき労働移動の円滑化
産業構造の転換期には、成長分野への人材移動が鍵となります。国は、学び直しを支援するリカレント教育を推進すると共に、コロナ禍で影響を受けた非正規雇用者などが、簡単なトレーニングを経て時間的制約の少ない事務職などへスムーズに移行できる仕組みを検討。これは、キャリアチェンジを目指す人々にとって重要な支援策となります。
4. 企業の変革とダイナミズムの復活
新たな成長の担い手であるスタートアップの創出と、日本経済の屋台骨である中小企業の変革は喫緊の課題です。挑戦する企業が生まれ育つ環境を整備し、企業全体の生産性を高めることで、経済の活力を取り戻します。
スタートアップ育成環境の課題
時価総額10億ドル超の未公開企業「ユニコーン」の数は、米中欧に比べて日本は極端に少ない状況です。これは、リスクマネーの供給不足やIPO(新規株式公開)プロセスの課題を示唆しており、成長するスタートアップが生まれにくい環境の一因とされています。
主な取り組み
-
🚀
スタートアップ支援強化
IPO時の価格設定プロセスの見直しや、SPAC制度の検討を通じて、資金調達を円滑化。 -
🏢
中小企業の事業再構築
コロナ禍で増加した債務問題に対応しつつ、新分野への挑戦や業態転換を補助金等で支援。 -
🤝
事業承継・M&Aの促進
後継者不在の中小企業に対し、M&A支援や経営人材のマッチングを強化し、事業の存続を図る。
解説
なぜ「成長戦略実行計画」が試験で重要なのか?
国の政策は、労働市場の動向、企業の採用活動、そして個人のキャリア形成に大きな影響を与えます。キャリアコンサルタントは、こうした社会全体の流れを理解し、相談者のキャリアプランニングに活かす視点が求められます。
この計画書を読むことで、**「今、国がどの分野に力を入れようとしているのか」「働き方はどう変わっていくのか」「どんな人材が求められるようになるのか」**といった未来のヒントが見えてきます。相談者に対して、より広い視野で情報提供や支援をするために、しっかりポイントを掴みましょう!
第1章:日本の「働く」の現状と課題を知ろう!
まず、今の日本がどんな状況にあるのかを見ていきましょう。
ポイント1:日本の課題は「労働生産性」の低さ
- 労働参加率:女性や高齢者の就業が進んだおかげで、G7諸国(先進7カ国)の中でもトップクラスです。たくさんの人が働くようになった、ということです。
- 労働生産性:しかし、一人ひとりの働き手が生み出す価値(成果)を示す「労働生産性」は、残念ながらG7諸国の中で最も低い水準です。
- 目指すもの:この労働生産性を上げて、その成果を働く人たちの「賃金」としてしっかり分配し、**「成長と分配の好循環」**を実現することが大きな目標です。
【キャリコン視点】 相談者が「頑張っているのに給料が上がらない」と感じている背景には、こうした日本全体の課題があるかもしれません。生産性を上げるためのスキルアップ(リスキリング)や、付加価値の高い分野へのキャリアチェンジが、今後のキャリアを考える上で重要になります。
ポイント2:コロナ禍が雇用に与えた影響
- 影響の偏り:コロナ禍の影響は、すべての業界に均一ではありませんでした。特に宿泊、飲食、娯楽業などが大きな打撃を受けました。
- 非正規雇用への打撃:正規雇用者は微増した一方で、非正規雇用者は大幅に減少しました。
- 特に女性への影響大:減少した非正規雇用者のうち、特に女性への影響が大きかったことがデータで示されています。これは、影響が大きかった業界で働く女性が多かったことなどが理由として挙げられます。
【キャリコン視点】 コロナ禍で職を失った、あるいは働き方に不安を感じている相談者、特に非正規雇用の女性は多いと想定されます。こうした方々への支援は、キャリアコンサルタントの重要な役割です。後述する「労働移動の円滑化」などの支援策と結びつけて理解しておきましょう。
第5章:「人」への投資強化【最重要ポイント!】
この章は、キャリアコンサルタントの業務に直結する内容が満載です。必ず押さえてください!
1. フリーランス保護制度の検討
- 背景:フリーランスとして働く人が増える一方、取引先との契約トラブルなども起きています。
- 対策:安心して働ける環境を整備するため、契約を書面で交わすルールの法制化などを検討するとしています。
2. テレワークの定着
- 推進策:サテライトオフィスの整備などを進め、どこでも質の高いテレワークができる環境を整えます。
3. 新しい働き方の実現(兼業・副業、短時間正社員)
- 目的:多様な働き方を希望する人のニーズに応えるため、企業に兼業・副業や短時間正社員制度の導入を促します。
- 選択的週休3日制も、企業の導入を促し、普及を目指します。
【キャリコン視点】 「副業を始めたい」「正社員として働き続けたいけど、時間は短くしたい」といった相談は今後ますます増えるでしょう。国の後押しがあることを伝え、具体的な選択肢として提示できるよう準備しておきましょう。
4. 多様性の推進(ダイバーシティ)
- 企業の成長力を高めるため、女性、外国人、中途採用者が管理職などで活躍できる組織への変革を促します。
5. 労働移動の円滑化【特に注目!】
- 目的:産業構造の変化に対応し、失業者を出すことなく、成長分野へ人々がスムーズに移動できるように支援します。
- リカレント教育の推進:学び直しを促進します。
- コロナ禍で影響を受けた人への支援:特に影響が大きかった非正規雇用の女性などが、簡単なトレーニングで時間的制約の少ない事務職などに失業なく労働移動できるシステムを検討するとしています。
【キャリコン視点】 これぞキャリアコンサルタントの腕の見せ所です!成長分野はどこか、どんなスキルが必要かといった情報を提供し、リカレント教育の機会を紹介するなど、具体的な「労働移動」の支援が求められます。相談者の希望と能力、そして社会のニーズを結びつける重要な役割を担います。
今後のキャリアを考える上での重要トレンド
「人」への投資以外にも、キャリアの未来を考える上で知っておきたい大きな流れがあります。
- デジタル化・グリーン化(DX/GX)
- 第2章・第3章で、国がデジタル分野とグリーン(環境)分野に集中的に投資することが示されています。
- これらの分野は、今後新たな産業や雇用が生まれる成長分野です。
- 中小企業の支援(第10章)
- 事業承継やM&A(企業の合併・買収)を後押しします。
- これにより、後継者不足に悩む企業の存続や、新たな経営者による事業の活性化が期待されます。
- 地方創生(第14章)
- テレワークの推進により、都会から地方への人の流れを加速させます。
- 地域企業のための経営人材のマッチングを促進します。
【キャリコン視点】 「どんな仕事が将来伸びますか?」という質問は定番です。DX/GX関連の仕事、事業承継で新たな経営者を目指すキャリア、地方でのテレワークといった選択肢は、国の政策という裏付けをもって情報提供できます。
まとめ:試験に向けて
この講義で取り上げたポイントは、キャリアコンサルタント試験の学科試験だけでなく、論述や面接でも活かせる視点です。
- 現状認識:日本の労働市場の課題(低い生産性、コロナ禍での非正規女性への影響)を理解する。
- 国の方向性:国は「人への投資」を強化し、多様な働き方と円滑な労働移動を推進しようとしている。
- 未来のキャリア:DX/GX、事業承継、地方創生といったキーワードが、今後のキャリアの選択肢を広げる。
これらの知識を頭に入れておくことで、相談者の状況をより広い文脈で捉え、根拠に基づいた的確な支援ができるようになります。頑張ってください!

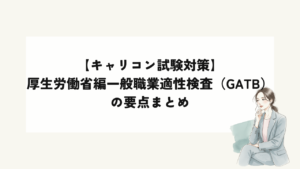

コメント