 チャチャ
チャチャキャリアコンサルタント試験に出る用語の解説まとめだよ



おさらいしましょう
キャリアコンサルタント試験で問われる幅広い分野から、特に重要な用語をピックアップして解説します。
第1章:労働関係法規・制度


労働者
労働基準法において、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されます。正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態を問いません。
使用者
労働基準法において、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」を指します。社長や役員だけでなく、人事部長や工場長なども含まれます。
- 15歳以上人口
- 労働力人口:働く意思と能力のある人
- 就業者:実際に仕事をしている人
- 完全失業者:仕事を探しているが、見つかっていない人
- 非労働力人口:働く意思がない、または働けない人(学生、専業主婦・主夫、高齢者など)
- 労働力人口:働く意思と能力のある人
「完全失業者」と認められるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 仕事がない:調査週間中に収入を伴う仕事を少しもしなかった。
- 仕事を探している:ハローワークに通ったり、求人に応募したりするなど、具体的な求職活動をしていた。
- すぐに仕事に就ける:仕事が見つかれば、すぐ働き始めることができる。
| 用語 | 説明 |
| 有効求人倍率 | 求職者1人あたりに何件の求人があるかを示す指標。ハローワークのデータが基になります。倍率が1を上回ると求職者より求人数が多く、下回ると求人数より求職者が多い状況を意味します。 |
| 休業者 | 仕事を持ちながら、病気や休暇などの理由で調査週間中に全く仕事をしなかった人。就業者に含まれます。 |
| 若年無業者(ニート) | 15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない人。求職活動をしていないため、完全失業者とは区別されます。 |
| フリーター | 15~34歳で、パート・アルバイトとして働く人、または働く意思のある無職の人を指す俗称です(統計上の明確な定義とは少し異なります)。 |
| 摩擦的失業 | より良い条件の仕事を求めて、自発的に離職している期間に生じる失業。転職活動中の失業などがこれにあたります。 |
| 構造的失業 | 企業が求めるスキルと、求職者が持つスキルのミスマッチなど、労働市場の構造的な問題によって生じる失業。 |
| 景気的失業 | 景気の後退によって企業の求人が減少し、発生する失業。需要不足失業とも呼ばれます。 |
労働契約
労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する契約です。
就業規則
職場の服務規律や労働条件(賃金、労働時間など)に関する具体的な事項を定めた規則集です。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る義務があります。
労働基準法
労働条件に関する最低基準を定めた法律です。労働時間、休日、賃金、解雇などについて定められており、これに満たない労働契約は、その部分については無効となります。
労働契約法
労働契約に関する基本的なルールを定めた法律です。労働契約の原則、解雇権濫用法理の明文化、有期労働契約の無期転換ルールなどが定められています。
36協定(さぶろくきょうてい)
労働基準法第36条に基づく労使協定のこと。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働者(残業)をさせたり、法定休日に労働させたりする場合に、事前に労使で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
男女雇用機会均等法
募集・採用、配置、昇進、教育訓練、解雇など、雇用管理の各段階において、性別を理由とする差別を禁止する法律です。間接差別の禁止や、セクシュアルハラスメント対策の事業主への義務付けも定めています。
育児・介護休業法
労働者が育児や家族の介護のために、休業や短時間勤務などの支援措置を受けられるように定めた法律です。性別を問わず取得できます。マタニティハラスメント対策も事業主に義務付けています。
労働者派遣法
派遣労働者の保護と、労働者派遣事業の適切な運営を目的とした法律です。派遣期間の制限(個人単位・事業所単位)、派遣先への直接雇用の申込み義務などが定められています。
解雇
使用者による一方的な労働契約の解約のこと。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効となります(解雇権濫用法理)。
ハラスメント
個人の尊厳を不当に傷つける行為。パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどがあり、事業主には防止措置を講じることが義務付けられています。
セルフ・キャリアドック
企業が従業員のキャリア形成を支援するために、定期的にキャリアコンサルティングやキャリア研修などを提供する総合的な仕組みのことです。
ジョブ・カード制度
個人のキャリアプランニングや職業能力証明に活用できるツールです。職務経歴、学習歴、訓練歴、免許・資格などを記録し、キャリアコンサルティングを通じてキャリアプランを作成します。
第2章:キャリアカウンセリング理論


スーパー(D. Super)
「人は生涯にわたって発達・変化する」という考えに基づき、キャリア発達を提唱した理論家。「ライフキャリアレインボー」を用いて、人生における様々な役割(子、学生、職業人、親など)の組み合わせがキャリアを形成するとしました。
ホランド(J. Holland)
個人のパーソナリティを6つのタイプ(現実的・研究的・芸術的・社会的・企業的・慣習的:RIASEC)に分類し、職業環境も同様に6つに分類。個人のパーソナリティと職業環境が一致(コングルーエンス)することで、職業的満足度が高まるとしました。VPI職業興味検査の基礎理論です。
シャイン(E. Schein)
個人がキャリアを選択する際に、最も大切で犠牲にしたくない価値観や欲求を「キャリア・アンカー」と名付けました。専門・職能別、管理、自律・独立など8つのタイプに分類されます。
クランボルツ(J. Krumboltz)
個人のキャリアは「計画された偶発性(プランド・ハップンスタンス)」によって形成されると提唱。予期せぬ出来事をキャリアの機会として最大限に活用するために、好奇心、持続性、楽観性、柔軟性、冒険心の5つのスキルが重要であるとしました。
ロジャーズ(C. Rogers)
来談者中心療法を提唱。カウンセラーに求められる3つの基本的態度として、「自己一致(純粋性)」「無条件の肯定的関心(受容)」「共感的理解」を挙げました。カウンセリングの基本姿勢として極めて重要です。
バンデューラ(A. Bandura)
ある目標を達成するために必要な行動を、自分はうまく遂行できると信じる認知(期待)を「自己効力感(セルフ・エフィカシー)」と呼びました。自己効力感は、目標設定や行動遂行に大きな影響を与えます。
エリクソン(E. Erikson)
人の一生を8つの発達段階に分け、各段階で達成すべき心理社会的課題(発達課題)があるとしました。例えば、青年期における課題は「自我同一性(アイデンティティ)の確立」です。
第3章:自己理解・仕事理解・メンタルヘルス


自己理解
自分自身の興味、価値観、能力、強み・弱みなどを客観的に把握し、理解すること。キャリアを考える上での出発点となります。
仕事理解
様々な職業や職務の内容、求められる能力、労働条件、業界の動向などを理解すること。自己理解と仕事理解を深め、両者をすり合わせることがキャリア選択において重要です。
エンプロイアビリティ
「雇用されうる能力」のこと。特定の企業だけでなく、労働市場全体で通用するような、個人の知識・スキル・経験などを指します。
動機付け理論
人のやる気を引き出す要因に関する理論。マズローの「欲求5段階説」や、ハーズバーグの「二要因理論(動機付け要因と衛生要因)」などが有名です。
アセスメントツール
個人の特性を客観的に測定するためのツール(検査)。VPI職業興味検査(ホランド理論)、GATB(一般職業適性検査)、職業レディネス・テスト(VRT)などがあります。
メンタルヘルス
心の健康状態のこと。ストレス、過労、人間関係の悩みなどが原因で不調をきたすことがあります。キャリアコンサルタントは、必要に応じて専門家(リファー)につなぐ役割も担います。
ストレス
外部からの刺激(ストレッサー)によって心や体に生じる緊張状態や歪み(ストレス反応)のこと。適度なストレスは良い影響をもたらすこともありますが、過度なストレスは心身の不調につながります。
第4章:キャリアコンサルタントの役割と倫理
守秘義務
キャリアコンサルティングで知り得た個人の情報を、本人の同意なく他者に漏らしてはならないという義務。キャリアコンサルタントの最も重要な倫理の一つです。
リファー(紹介)
相談内容が自身の専門領域を超える、あるいは他の専門家による支援が適切と判断した場合に、相談者の同意を得て、適切な専門家や機関(医療機関、ハローワークなど)に紹介すること。
スーパービジョン
指導者(スーパーバイザー)から、自身のカウンセリング実践について指導や助言を受けること。キャリアコンサルタントの専門的能力の維持・向上に不可欠です。
第5章:労働市場・能力開発


有効求人倍率
ハローワークにおける、月間の有効求職者数に対する有効求人数の割合。1を上回ると求職者数より求人数が多く、下回ると求人数より求職者数が多いことを示し、景気動向の指標として用いられます。
OJT (On-the-Job Training)
日常業務を通じて、上司や先輩が部下や後輩に対して必要な知識・スキルを指導・育成する手法。
Off-JT (Off-the-Job Training)
職場を離れて行われる研修や教育訓練のこと。集合研修、セミナー、eラーニングなどが含まれます。
働き方改革
「一億総活躍社会」の実現に向け、長時間労働の是正、正規・非正規の格差是正、多様で柔軟な働き方の実現などを目指す政府の取り組み。
ダイバーシティ&インクルージョン
性別、年齢、国籍、障がいの有無など、個人の持つ多様性(ダイバーシティ)を受け入れ、尊重し、その能力を最大限に活かす(インクルージョン)ことで、組織の成長につなげようとする考え方。
リカレント教育
学校教育を終えて社会に出た後も、個人の必要なタイミングで再び教育を受け、仕事と学びを繰り返すこと。人生100年時代において重要性が高まっています。

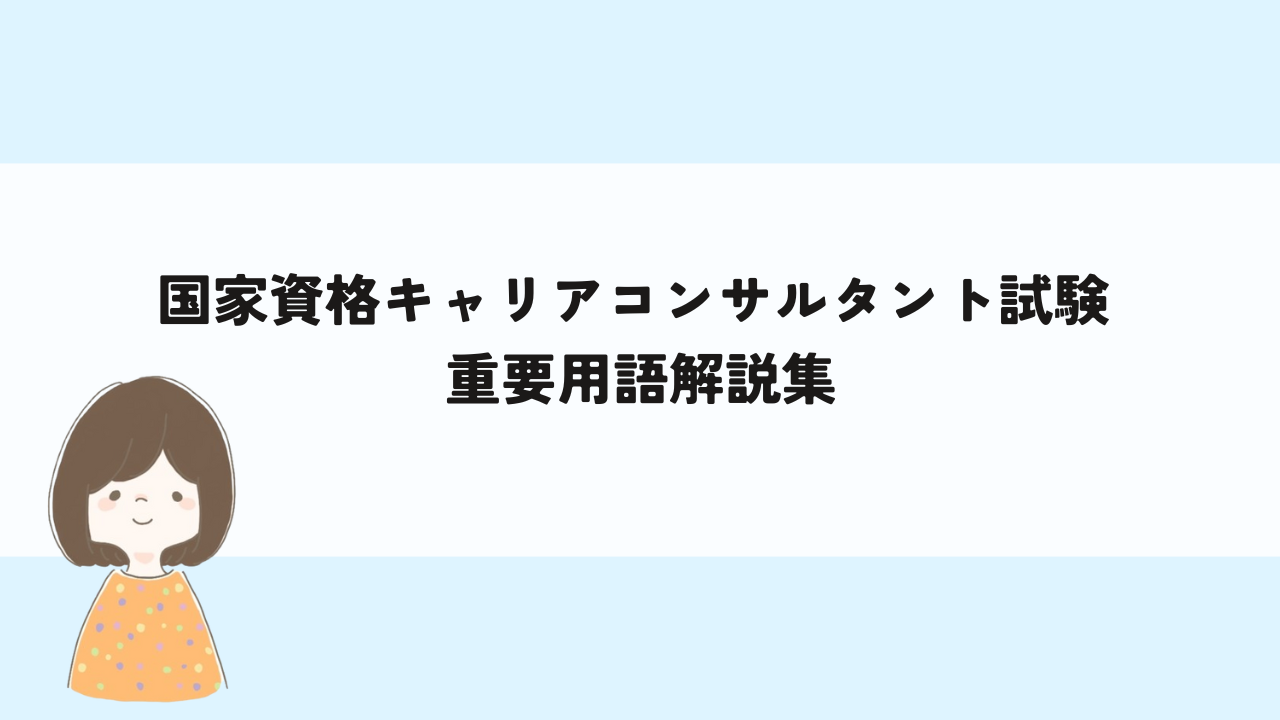
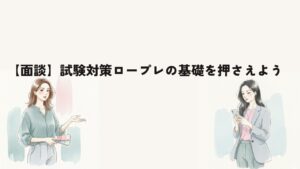
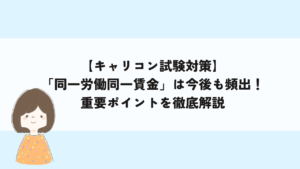

コメント